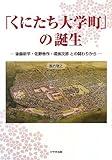先に後藤新平 の本を探して「大風呂敷」に到達した折に、
その延長線上で見つけた本がありまして。『「くにたち大学町」の誕生』という一冊です。
たいへんローカルな話ではありますが地元のことだものですから、どうぞご容赦のほどを。
東京都の多摩地区(かつては東京都下と言われておりましたなあ)にある国立市。
地名としては「くにたち」と読むのですが、漢字で見る限りどうしたって「こくりつ」ですなあ。
だもんで、国立中央図書館なんつう記載があるとあたかも国がやっているかのように
見えてしまうことから「くにたち中央図書館」と地名をひらがな書きしたりするケースもままありまして。
そんな「国立」という地名の出自は、中央線沿線にあって立川と国分寺の間だから
それぞれから一文字ずつとって「国立」となったと伝えられておるところながら、
実は文教都市として教育機関を中心として、この場所が教育を通じて
国を立てる基となるようにてな意味合いが込められていたといことも、
この本には書かれておりましたよ。
いずれにせよ、あたり一面雑木林であったという頃に
ここを開発して町を作り上げたのは堤康次郎であったとは聞き知っておりました。
ですが、地名に込められた(本当かどうかはわかりませんが)意図や町づくりの形が
後の西武グループの総帥であった堤本人から出たとは考えにくいわけでして、
そこに関係してくると思われるのが本書のタイトルに添えられた
「後藤新平・佐野善作・堤康次郎との関わりから」という部分となりましょうか。
後藤新平、堤康次郎と並ぶもう一人、佐野善作というのは
東京商科大学(今の一橋大学)の学長であった人ということです。
明治18年(1885年)以来、神田一ツ橋(地名では「ツ」が入るようで)に校舎のあった
東京商業学校(後の東京商科大学、一橋大学)は大正12年(1923年)の関東大震災で
壊滅状態となった校舎の移転先を検討せざるを得なくなったようなのですね。
そこで、堤の箱根土地株式会社(後の国土計画、コクド、現在はプリンスホテルに吸収)が
広大な雑木林を買収して造成し、大学側は臨むとおりの「大学を中心にした街づくり」を
してみたらどうでしょう的な話になっていったようでもある。
Wikipediaの佐野善作の項にあるように
「ドイツ・ゲッティンゲンをモデルに学園都市として開発」することを目したことは
このあたりの関係でありましょうね。
ですが、本書の書き手が言っているように、
古くからの大学町であるドイツのゲッティンゲンと国立の町のようすは全く似ていない。
そこでゲッティンゲンをモデルにということの意味が町の外観ではなくして、
町が大学を中心に成り立ち、独自の文化・気風を育んできたという
「町のありよう」の方がだったのでしょう。
では、基本的に碁盤の目状に街区が作られ、駅から南には広い直線道路があり、
また駅前のロータリーを基点にして左右には放射状に2本の道路が走るという
今の町の外観はどこから出てきたことなのか。
そこで登場するのが後藤新平なのですなあ。
初代満鉄総裁となった後藤新平は、鉄道そのものの経営と同時に
満鉄付属地の開発、つまりは沿線開発にも携わります。
満州国成立にあたっては首都・新京となる長春も
鉄道駅を中心にした町づくりが検討され、駅からまっすぐに伸びる広いメインストリート、
駅前ロータリーに始まる放射状の路、碁盤の目状の街区などが図面として残されてますが、
後にこれを見た人は「くにたちの町か?」と見紛うこともあったとか。
おそらく関わりのありそうな図面によって国立の大学町は作られていったようですが、
如何せん箱根土地は営利会社であって、放射状道路などは当初の目論見よりも
かなり幅員が狭められているのだとか。
でもって驚いたことには、
今も駅前からまっすぐに伸びる「大学通り」には並行してたっぷりした緑地帯が取られていて、
春は桜、夏は緑陰、秋はイチョウの黄葉、冬には葉の落ちた木を使ったイルミネーションと
四季折々に独自の景観をもたらしてくれているわけですが、この緑地帯の土地はいまでも
箱根土地会社から繋がる国土計画、プリンスホテルが持ち続けているのだそうな。
よもや私有地であろうとは思いもよりませんでした。
…とまあ、国立駅前のようすをご存知無い方には全くもって何のことやら?というお話ですが、
地元民(住んで20数年ではありますが)にとっては、ほお~と思うところなのでありました。