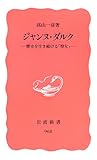先に「ユトリロとヴァラドン」展 を見ました折、会場の解説の中に
「ユトリロはジャンヌ・ダルクに憧れていた…」てなふうがあったのですね。
世界史のあれこれに興味を持って目を向けてはいるものの、思い返してみると
ジャンヌ・ダルクに関してはあんまり知識を持ち合わせていないなと気付いたものですから、
この際、本の一冊にでも当たっておくか…と考えたわけでして。
取り上げたのは岩波新書の「ジャンヌ・ダルク~歴史を行き続ける『聖女』~」でありました。
15世紀初め、フランス北東部のロレーヌ地方、ドンレミ村で生まれた少女ジャンヌは
敬虔な信仰をもって育っていきますが、ある時天からの声を聴き、
当時百年戦争の渦中にあった戦陣へと出立。
イギリスに押しまくられていたフランス兵の先頭に立って、オルレアンの地を解放するとともに
王太子シャルルをランス大聖堂での戴冠式に導く…という大活躍を見せる。
その後のイギリス軍との戦いの中でジャンヌは囚われの身となってしまい、
当時はイギリス勢力下にあったルーアンに引っ立てられて宗教裁判を受けることに。
結果、哀れジャンヌは二十歳にもならぬ若いみそらで火刑の炎に焼かれてしまうのでありました。
こうした辺りのことは断片的にもだいたい知っていることではありますが、
先ほど「フランス兵の先頭に立って…」と言ったものの、
ジャンヌ・ダルクが敵兵をばったばったと切り倒し…てなことは全く無いのだ
ということは(恥ずかしながら)ちいとも知りませんでした。
てっきり「オール・ユー・ニード・イズ・キル」
の
リタ(エミリー・ブラントの役どころ)的な活躍ぶりだと思っていたのは、とんだ勘違い。
ジャンヌがやったことはもっぱらフランス軍の士気を鼓舞したということであるそうな。
ですが、天の声を聴いて馳せ参じた少女(といっても十代後半)となれば、
誰しも「神がかり」の印象を抱くでしょうし、
仏軍側にすればジャンヌが付いておれば向かうところ敵無し、
反対に英軍側にすれば「祟られたらやだな…」といった思いもあって
逃げ腰てなことでもあったろうかと。
かように目立つ存在であって、それが活躍の時期がほんの3年くらいとなると、
当然に数々の神話や物語が生まれてしまうのもむべなるかなとは思いますですね。
本書の著者は九郎判官義経を引き合いに出してきたくらいですから、
「義経は大陸に渡ってチンギスハンになった」的な大層な話のジャンヌ版が作られていたりして。
(実際の話として、後にジャンヌを騙る詐欺事件はあったようです)
一方で、ジャンヌ・ダルクという存在そのものが実は架空なのでは…
という想像も働くところながら、こちらの方に関しては、
かの裁判記録がかなりかっちり残っていて、本人の証言も記載され、
ドンレミ村の生まれであるとか、育った環境とかはしっかりと考証されているようでありますね。
ところで、ジャンヌの活躍として王太子をランスで戴冠させたことがありますが、
これはフランス王はランス大聖堂で戴冠を受けてこその慣わしがある中、
フランス王位の継承を主張していたイギリス王に先手を打った恰好となる点が肝心。
それだけにジャンヌが火刑にされたのは、
ジャンヌを異端者(天の声を聴いたなどと不埒なことを言ってるしと…)とすることにより、
異端者が加担した戴冠式など無効であってフランスの王位継承は正式になされてはいない、
つまりイギリス王にとってフランス王位継承の望みは絶たれていない…とまあ、
こうした論法を展開せんがためであったという。
ということは、イギリスにとってはジャンヌが異端者であるかどうかはともかくも、
異端者だということにして葬り去ることが大事だったわけですね。
ですが、ジャンヌの「神がかり」(そうであるという思い込み)に助けられたフランス側にしてみれば、
処刑によってジャンヌは殉教者に祭り上げられ、ジャンヌの遺骸や衣服などの一部分でも残されれば
「聖遺物」として、これまたフランス軍の求心力の源になるてなことも考えられる。
これを嫌ったイギリスが敢えて何もかも燃やし尽くすように火刑という方法を選び、
なおかつ本書から引用すれば、このようなことまでやるという念の入れようであったそうな。
多くの証人が語るように、火刑の最中に火勢を一旦止めて、焼けた死体を見物人に示してこの娘が死んだことを確認させたことや、遺骸の灰をセーヌ川に投げ捨てさせた措置も、その効果(ジャンヌが持つと噂された魔力の恐れを排除する)を意図してのことでしょう。
ことほどかほどに影響力を持った(あるは持つと考えられた)ジャンヌが、
何故そのように受け止められたかには諸説(噂話の延長のようなものまで含めて)あるわけですが、
とにもかくにも周囲(そして後世)の人々に強い印象を残して去っていったのですな。
ジャンヌの死後、国王シャルル7世は戦いを続けて、
フランスの国土からイギリス勢力を追い払うことに成功、ついに百年戦争は終結を迎える。
一方で、そうした流れに至る弾みをつけることになったジャンヌの活躍を思うにつけ、
異端として処刑された事実を何とかしたいと、今度は「復権裁判」が行われるのですね。
結果、異端との宣告は取り消されて、
ジャンヌへの崇敬の念を明らかにするのも全く遠慮がいらなくなった。
オルレアンでは毎年ジャンヌ・ダルク祭が催され、
ジャンヌが「オルレアンの乙女(la Pucelle d'Orléans)」と呼ばれたことから生誕地ドンレミ村は
今やドンレミ・ラ・ピュセルと呼ばれるようにもなっているそうな。
…とまあ、ご存知の方には今さらながらのことではあろうものの、
改めて「ジャンヌ・ダルクはこういう人であったか」と知ったわけですが、
さてユトリロが何故ジャンヌ・ダルクを気に掛けたのか…に関しては、
別途ゆっくり想像を巡らすとしてみますかね。