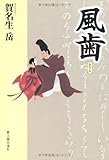足利荘のあれこれ
を書いてきたことでもあり、
何かしら関わりのありそうな本でも読もうかと探しているときに
「こりゃ、なかなか変わった内容のようで…」と思われるものに出くわしたのですね。
賀名生岳さんの「風歯」という連作、
大括りで言えば「時代小説」ということになりましょうけれど、
主人公の職業は今風に言うと歯科医なのですよ。
元は本職の歯医者さんであった作者が、
幕府は成立したものの未だ安定には諸々の問題が山積状態であった
室町将軍・足利尊氏の時代を背景に歯科医を主人公として描く物語とは?
少々気になるところではありませんか。
しかしながら、歯医者といえば
ある種技術者でもあるかのように機械を駆使して治療にあたるイメージがあるものですから、
そうした機械類が一切無い室町時代のことなれば、そも主人公からして架空の人物…
かと思えば、そうではないらしい。
律令以来の制度で
「宮廷官人への医療、医療関係者の養成および薬園等の管理を行った」とされる典薬寮、
その長官職にあたる典薬頭を和気氏とともに世襲していた丹波氏の当主・丹波兼康は、
日本で初めての歯科・口腔科の専門医であったと言われる実在の人物だそうで。
お役目柄、貴人の病いに際して治療を施したりする立場であったのでしょうけれど、
どうも兼康は典薬頭としての知識・技量に自信が持てないご様子。
それが治療の分野でも一段と低く見られていただけに
療法も定まっていない歯科・口腔科に関する対応に迫られ、
自信のない知識・技量を総動員して患者の病いを治癒させていくことになってしまった。
こうしたことから歯科・口腔科にこそ生きる道を見つけた兼康であった…てなことなんですが、
この辺りの顛末から先、ざっくりフィクションなのでありましょうね、きっと。
先に「歯科・口腔科に関する対応に迫られ…」と言いましたけれど、
何しろ対応を迫ってくる相手(患者ですが、みな高飛車)というのが足利尊氏であり、
佐々木道誉(本書では京極導誉)であり、北畠親房であり…となれば、
南北朝の、北からだろうが、南からだろうがどっからでもかかってこい!状態ではないかと。
足利尊氏が持ち込んだ病いは、本書のタイトルとなっている「風歯」というもの。
早い話が今で言う「虫歯」のことなんですが、作中から引用すれば、
当時は虫歯はこのように考えられていたそうな。
…歯に入るは手の陽明脈の末端なり。日かに、頬に入りて歯に通じる足の陽明脈がある。その脈路が虚であると、千病万病のもとである風(ふう)の気が血気に相乗し、歯間を攻撃する。さすれば、歯茎が腫れ、熱気が加われば膿汁が出、息が臭くなる。風の気が虚なる歯にとどまるを風歯という…
なんだか「ほぉ、そうだったのか…」と思ってしまいそうな気もしますですが、
ところで、酷くなった「風歯」は抜くしかないというのが当時の処方。
へら状のものを歯の根元に差し込んで、ぐいぐい!!やったそうでありますよ。
抜歯後に高熱が出て命を落とすこともある、大変な治療だったようです。
ですが、尊氏の命は「抜かずに治せ」というもの。困じ果てた兼康は無い知恵から絞りだしたのが
(作中、本人は無いと思ってますが、やはり典薬頭を世襲する家柄なりの蓄積はありましょう)
現在の治療のように歯の虫食い部分をこそげとって治療薬を塗布するというもの。
今から考えれば当然なんでしょうけれど、
当時とすればコロンブスの卵的治療法と言えましょうか。
しかしまあ、治療薬とは言いましたが、室町時代ですから当然に生薬というか、
本草学の成果である、主として植物類が持つ効能を適宜組み合わせて利用するもの。
よく食べ物に関して
「今では美味いと誰でも食べるけれど、初めてこれを口に入れた人は勇気がいったろうねえ」
みたいな話がよく出ますけれど、薬に関しても植物の根っこや葉っぱを煎じて飲むとか
いったい誰がどんなつもりでやってみたんだろうか…と思いますですね。
一方で道誉が持ち込んだのは「舌強」という病い、また親房の病いは「緊唇」というもの。
前者は舌に、後者は唇(口の内側ですね)に腫れができてしまうといった病いのようですが、
兼康はいずれも切開して直してしまう。このあたり口腔科の領分でしょうか。
ただお話としてこれだけでは身も蓋もないようなふうですが、
兼康の娘が将軍家姫君の遊び相手としてお傍近くいるときに
(実のところは兼康に是が非でも特別な治療をさせんがため、娘を人質として尊氏が拉致した)
南北朝絡みの謀りごとから毒をもられ姫君ともども兼康の娘までが命を落としたらしいとの話が。
事実は厳秘とされ、兼康にもはっきりしたことは分からない中で
尊氏憎し、何かを知っているようでいて明かさない道誉も恨めし、
ましてや毒を提供したと思しき親房許すまじと果敢な行動に出る…という筋書き。
こうした怨み辛みを抱きつつ、しかも医術の知識・技量の拙さを感じつつも
相手を悩ます病いには立ち向かってしまう兼康。
人がいいとも言えないではないですが、どこか「医は仁術なり」という言葉に通ずるような。
兼康の時代とは知識も技量もそして器材も大変革を遂げた医術の世界ですけれど、
「医は仁術なり」という言葉の意はちゃあんと今に受け継がれていると思いたいところだぁね…
てなことに思いを巡らせながら読み終えた一冊でありました。