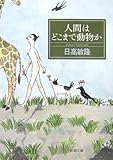先日は遺伝子のレベルで考えれば、ヒトもやはり動物であるか …てなことを紹介しましたけれど、
たまたま図書館でこういうタイトルの本に出くわしたものですから、読んでみたのですね。
題して「人間はどこまで動物か」。
ですが、生物学的に「人間はどこまで動物か」ということを考察したという本ではありませんで、
ということは後から気が付いたんですが、動物行動学者の日高敏隆さんのエッセイ集でありました。
タイトルになっているのはその中の一文ということであって、何と5ページ。
日頃からキャッチーなタイトルにはああだこうだ言っておきながら、
ここでは見事に編集者の企てに釣り込まれてしまった感ありでありますよ。
しかしながら普段の興味からして、
こうした機会でもないと手に取ることもない一冊だったと思われますが、
なかなかどうして興味深い内容が綴られておりました。
例えば、程なくシーズン・インするものと思われるセミの鳴き声に関して。
日本の夏の暑さを弥増す感のあるセミの声ですけれど、
その実態は求愛行動だということはすでによく知られたこと。
ですが、何だってあんなにやかましいのか。
いったいセミの耳はどうなっておるのか?と疑問をもったのがかの有名なファーブルであります。
セミの大合唱に向けて、お祭り用の大砲をどかん!と放ったところ、
何食わぬ顔で?セミは鳴き続けていたそうな。
こうしたことからセミには耳はないのだと考えたファーブルは、
耳がないならメスを呼ぶ求愛行動であるはずがない、何しろメスには聴こえていないのだから・・・として、
セミは夏が楽しいから鳴いているのだと結論付けたことが「ファーブル昆虫記」に出てくるそうなのですね。
もちろんこれは誤りであって、セミにも聴覚はあるけれど人間とは音の可聴範囲が異なっていて、
セミには大砲の音は聴こえないけれど、人間にはやかましいと思える泣き声の方は
甘いメロディに聴こえているのかもしれんですね。
こうしたエピソードの紹介に併せて、
アリストテレスの「セミの夫たちは幸せだ」」というひと言を引いてくる。
なんとなれば「セミの妻たちはしゃべらないからだ」というのでして、
この辺りの軽妙さが日高エッセイのひとつの魅力でしょうか。
とはいえ軽口ばかりではありませんで、環境のことなどに話が及ぶと
とかく地球温暖化とかゴミ問題とかということの対策で話が終始することに疑義を呈しています。
「人間の存在そのものが地球に負荷を掛けている」てなことがよく言われますけれど、
そもそも人間の進化・進歩は自然と対決することから生まれ、培われてきたものだということを
念頭に置く必要があろうということなんですね。
小手先のことではすまない大括りの地球環境を考えるとき、
人間そのもののあり様を変えようとしても難しく、
ともすると人間の社会、行動、文化等々を否定することにもなりかねない。
では、どうするか?それを考えましょうというわけです。
リサイクルに一所懸命になるのはもちろん良いとして、
一方でリサイクルしなきゃいけないものがどんどん作り出されている事実を
とりあえず措いといて…というわけにもいきませんものね。
ところでところで、改めて「人間はどこまで動物か」という点ありますけれど、
一番上にちらりと書いた「ヒト」というカタカナ言葉は
動物としての人間を表すときに使われるのが一般的なのだとか。
そうした区分けを前提にすると、とかく人間の側には
「人間は単なるヒトではない」という強固な信念がつきまとっているのではないかと指摘しています。
先日の文章の中でも、結局のところそれに類するようなことも言ってしまったりしてますし。
とかく生物の進化の最前線、最上級に人間がいて…のように思ってしまうところですけれど、
それぞれの生物はそれぞれに人間とは別の進化を遂げて、
ともすると人間の思いもよらぬ仕組みを作り上げていたりもする。
つまり、発展形態のありようはひとつに限らない。
とすれば、それら異なるものどうしを比べることにどんな意味がありましょうか。
日高センセイの仰る「イヌはどこまでネコか?」と考えても仕方がないように。
ただ、だからといって先日読んだように
遺伝子レベルでのいかんともしがたい性のようなものも一方ではありはするものの、
「どこまで?」と考えるときの「ものさしは一本だけ」というのがそもそもどうよ?的なのでは。
こんなふうに説く著者に返す言葉の見つからない…そんな一冊なのでありました。