広島大学の柳瀬先生のブログで、大修館から、『英語教師のための第二言語習得論入門』が出版されたことを知り、早速読んでみました。
いい本でした。
この本を購入したきっかけは、
柳瀬先生が、「これくらいは読みましょう」とブログに書かれていたこと(笑)や、タイトルに、「英語教師のための」がついていて、思わず「読まなきゃ」と思ったこと(見事にかかりました)ですが、
読んでみて、本当にいい本だと思いました。良書です。
まず、購入して気づいたのですが、
本の装飾がオシャレでかわいい(笑)
いろんな色が使ってあり、読むのを気分的にも楽しくさせてくれます。
そして、内容。
下記の目次をご覧ください。
英語教師が知りたいことがざっくざくです。
まず、第1章は、「英語の先生ならこれだけは知っておきたい」という、
「第二言語習得論のエッセンス」をまとめています。
これまで大学や現場で学んできた実践や理論を、シンプルにエッセンスを整理してくださっているのがありがたいです。
いろんな本を読んでいると、どれも大切に思えてきて、重要性の軽重がつきにくくなったりすることもあるのですが、この本は、そんな人をも救ってくれます。
もちろん、はじめて第二言語習得論を学ぶ人や、学生さんにもやさしく書かれています。忙しい教員でも、しっかりと読めるつくりになっています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
第1章 第二言語習得論のエッセンス
~英語の先生ならこれだけは知っておきたい~
第二言語習得と英語教育
母語の影響
○言語転移
○普遍的な習得順序
○スピーキング重視の弊害
○文化の転移
年齢要因(臨界期仮説)
母語によるフィルター
バイリンガルの利点
外国語学習における個人差
外国語学習適性とは
動機づけ(motivation)
動機づけと学習の成果の関係
SLA 研究からみた効果的学習法とは
言語ができるとはどういうことか
○外国語教育が目指す能力とは
○単語と文法を習得すればいいのか
言語習得の本質とは何か
○クラシェンの「インプット仮説」
○インプットだけで習得できるのか
○インプット+「アウトプットの必要性」がカギ
○なぜインプットで言語習得ができるのか
○自動化理論
まとめ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ここから、第2章です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
第2章 SLA からみた日本の英語教育
~現状とこれから~
効果的な外国語学習法・教授法
オーディオリンガル教授法(オーラル・アプローチ)とは
SLA 研究の誕生と重要な発見
インプットかアウトプットか?
インプット仮説の「落とし穴」
アウトプットの効用
インプットとアウトプットをどう組み合わせるか
日本の現状
自動化モデルの英語教育
なぜ自動化をしない自動化モデルになってしまうのか
○誤った英語学習理論
○正確さを過大に重視した入学試験
○不十分な教員養成システム
今後どうすればいいか
自動化モデルからインプットモデルへ
「自動化を行わない自動化モデル」からの脱却
自動化理論の限界を認識する
教員養成をどう変えるか
入試を巡る問題
まとめ
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
続いて第3章から6章までは、これまで学んだ知見を、どう現場に活かすことができるか、それを小学校・中学校・高校・大学(社会人)と、具体的に理論の活かし方を述べます。
このへんは、著者がもと現場の先生だった体験が活かされていると感じました。
理論だけを教えるのでなく、「で、結局、教室でどう活用するの」を知りたい現場の先生のニーズに応えています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
第3章 小学校英語教育のこれから
~インプットモデルを中心に~
SLA と小学校英語教育
臨界期仮説と小学校英語教育
母語に対する悪影響はあるか
小学校英語で何をするべきか
小学校では動機づけが大事
言語面のねらいをどうするか
○TPR
○自主的読書教育
○その他の有効な教材
アルファベットの扱い
先生の日本人的発音はだめか
まとめ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
第4章 中学校英語教育のこれから
~「流暢さ」と「正確さ」のバランスが大事~
英語嫌いを生まないために
初級におけるコミュニカティブ・アプローチの例
自分の指導法をどう評価していくか
アウトプットを強制することの弊害を最小限に
文字と音声の関係をどうつかませるか
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
第5章 高校英語教育のこれから
~大量のインプットと少量のアウトプット~
「英語の授業は英語で」とは?
インプットモデルに基づいた高校英語実践例
文法処理も促す
多聴多読をどうすすめるか
5文型の扱い
英語の苦手な生徒をどうするか
<実践報告> Krashen 理論の英語教育への示唆
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
第6章 大学生、社会人のための英語教育
~最終目標は自律した学習者~
自律した学習者を育てるために
インプット処理の質をいかに高めるか
理解度を保証する
感情に訴えるインプット教材
自分に関するインプットとアウトプット
リスニングとリーディングの連携
自律学習につなげる:ポートフォリオ学習
インプット処理の質を高めるアウトプットの効用
インプットからアウトプットへ
CMC (Computer-Mediated Communication)の無限の可能性
この本の帯には、次のようなことも書かれていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
知っていれば効果的な指導法が見えてきます
★小学校のアルファベットは「テストしない」が基本
★先生の発音は完璧である必要はない
★三単現の-s は上級者にも難しい
★「英語の授業は英語で」は、最小限の日本語を効果的に使うこと
★[多量のインプット+少量のアウトプット]が言語習得のカギ など
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
特に最後の、「多量のインプット+少量のアウトプットが言語習得のカギ」という言葉には、ハッとさせられました。
まだの方は、おすすめです。
値段も、1260円と良心的です。
ぜひ、ご覧ください。
英語教師のための第二言語習得論入門/白井恭弘
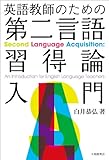
¥1,260
Amazon.co.jp
いい本でした。
この本を購入したきっかけは、
柳瀬先生が、「これくらいは読みましょう」とブログに書かれていたこと(笑)や、タイトルに、「英語教師のための」がついていて、思わず「読まなきゃ」と思ったこと(見事にかかりました)ですが、
読んでみて、本当にいい本だと思いました。良書です。
まず、購入して気づいたのですが、
本の装飾がオシャレでかわいい(笑)
いろんな色が使ってあり、読むのを気分的にも楽しくさせてくれます。
そして、内容。
下記の目次をご覧ください。
英語教師が知りたいことがざっくざくです。
まず、第1章は、「英語の先生ならこれだけは知っておきたい」という、
「第二言語習得論のエッセンス」をまとめています。
これまで大学や現場で学んできた実践や理論を、シンプルにエッセンスを整理してくださっているのがありがたいです。
いろんな本を読んでいると、どれも大切に思えてきて、重要性の軽重がつきにくくなったりすることもあるのですが、この本は、そんな人をも救ってくれます。
もちろん、はじめて第二言語習得論を学ぶ人や、学生さんにもやさしく書かれています。忙しい教員でも、しっかりと読めるつくりになっています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
第1章 第二言語習得論のエッセンス
~英語の先生ならこれだけは知っておきたい~
第二言語習得と英語教育
母語の影響
○言語転移
○普遍的な習得順序
○スピーキング重視の弊害
○文化の転移
年齢要因(臨界期仮説)
母語によるフィルター
バイリンガルの利点
外国語学習における個人差
外国語学習適性とは
動機づけ(motivation)
動機づけと学習の成果の関係
SLA 研究からみた効果的学習法とは
言語ができるとはどういうことか
○外国語教育が目指す能力とは
○単語と文法を習得すればいいのか
言語習得の本質とは何か
○クラシェンの「インプット仮説」
○インプットだけで習得できるのか
○インプット+「アウトプットの必要性」がカギ
○なぜインプットで言語習得ができるのか
○自動化理論
まとめ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ここから、第2章です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
第2章 SLA からみた日本の英語教育
~現状とこれから~
効果的な外国語学習法・教授法
オーディオリンガル教授法(オーラル・アプローチ)とは
SLA 研究の誕生と重要な発見
インプットかアウトプットか?
インプット仮説の「落とし穴」
アウトプットの効用
インプットとアウトプットをどう組み合わせるか
日本の現状
自動化モデルの英語教育
なぜ自動化をしない自動化モデルになってしまうのか
○誤った英語学習理論
○正確さを過大に重視した入学試験
○不十分な教員養成システム
今後どうすればいいか
自動化モデルからインプットモデルへ
「自動化を行わない自動化モデル」からの脱却
自動化理論の限界を認識する
教員養成をどう変えるか
入試を巡る問題
まとめ
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
続いて第3章から6章までは、これまで学んだ知見を、どう現場に活かすことができるか、それを小学校・中学校・高校・大学(社会人)と、具体的に理論の活かし方を述べます。
このへんは、著者がもと現場の先生だった体験が活かされていると感じました。
理論だけを教えるのでなく、「で、結局、教室でどう活用するの」を知りたい現場の先生のニーズに応えています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
第3章 小学校英語教育のこれから
~インプットモデルを中心に~
SLA と小学校英語教育
臨界期仮説と小学校英語教育
母語に対する悪影響はあるか
小学校英語で何をするべきか
小学校では動機づけが大事
言語面のねらいをどうするか
○TPR
○自主的読書教育
○その他の有効な教材
アルファベットの扱い
先生の日本人的発音はだめか
まとめ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
第4章 中学校英語教育のこれから
~「流暢さ」と「正確さ」のバランスが大事~
英語嫌いを生まないために
初級におけるコミュニカティブ・アプローチの例
自分の指導法をどう評価していくか
アウトプットを強制することの弊害を最小限に
文字と音声の関係をどうつかませるか
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
第5章 高校英語教育のこれから
~大量のインプットと少量のアウトプット~
「英語の授業は英語で」とは?
インプットモデルに基づいた高校英語実践例
文法処理も促す
多聴多読をどうすすめるか
5文型の扱い
英語の苦手な生徒をどうするか
<実践報告> Krashen 理論の英語教育への示唆
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
第6章 大学生、社会人のための英語教育
~最終目標は自律した学習者~
自律した学習者を育てるために
インプット処理の質をいかに高めるか
理解度を保証する
感情に訴えるインプット教材
自分に関するインプットとアウトプット
リスニングとリーディングの連携
自律学習につなげる:ポートフォリオ学習
インプット処理の質を高めるアウトプットの効用
インプットからアウトプットへ
CMC (Computer-Mediated Communication)の無限の可能性
この本の帯には、次のようなことも書かれていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
知っていれば効果的な指導法が見えてきます
★小学校のアルファベットは「テストしない」が基本
★先生の発音は完璧である必要はない
★三単現の-s は上級者にも難しい
★「英語の授業は英語で」は、最小限の日本語を効果的に使うこと
★[多量のインプット+少量のアウトプット]が言語習得のカギ など
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
特に最後の、「多量のインプット+少量のアウトプットが言語習得のカギ」という言葉には、ハッとさせられました。
まだの方は、おすすめです。
値段も、1260円と良心的です。
ぜひ、ご覧ください。
英語教師のための第二言語習得論入門/白井恭弘
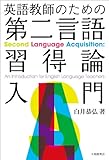
¥1,260
Amazon.co.jp