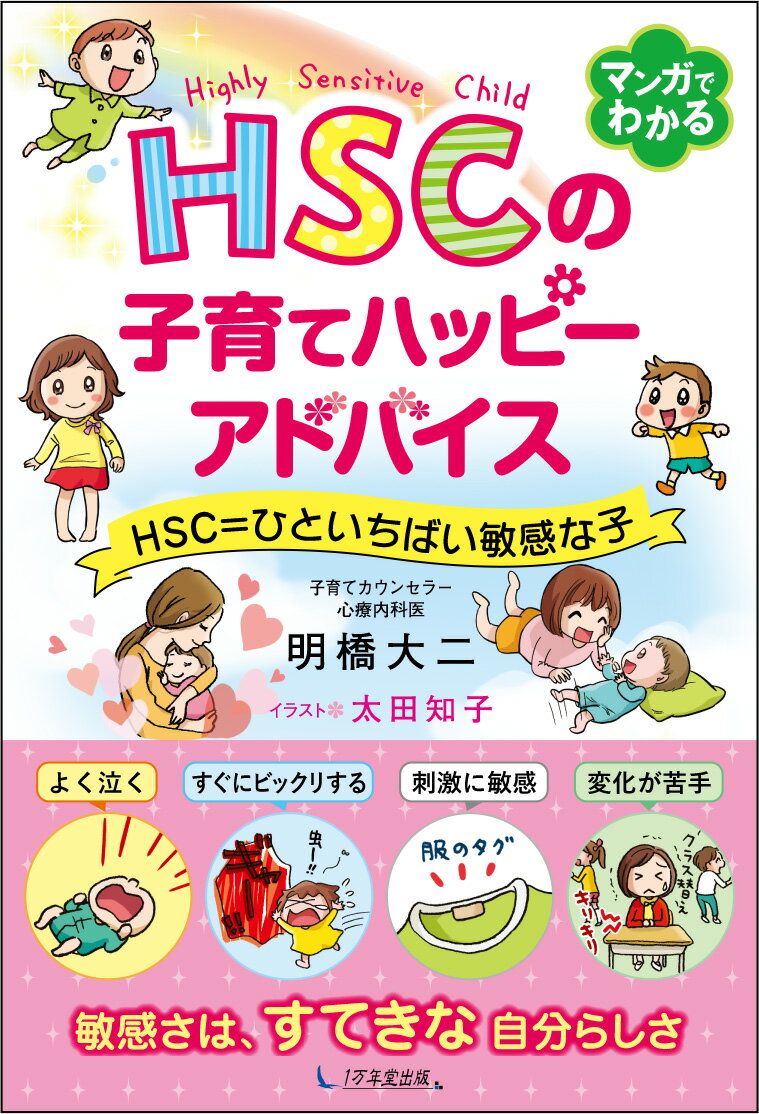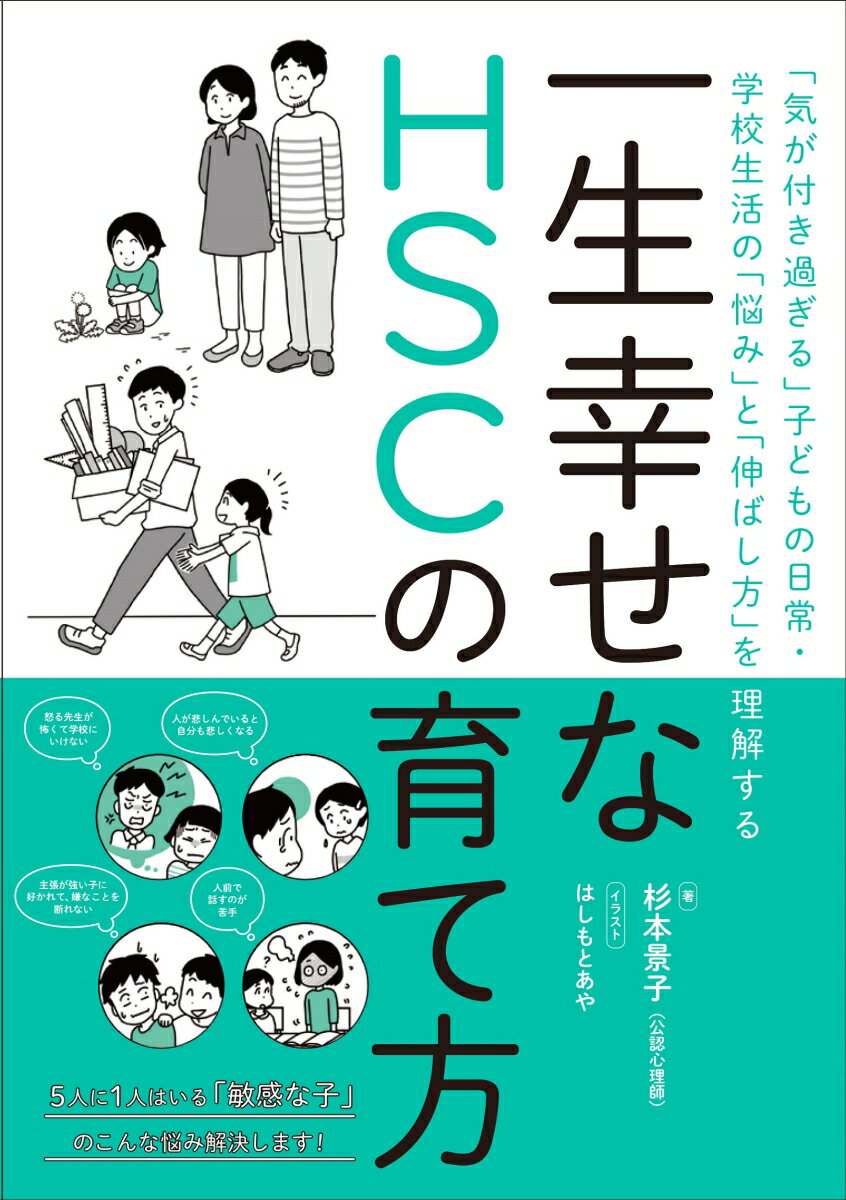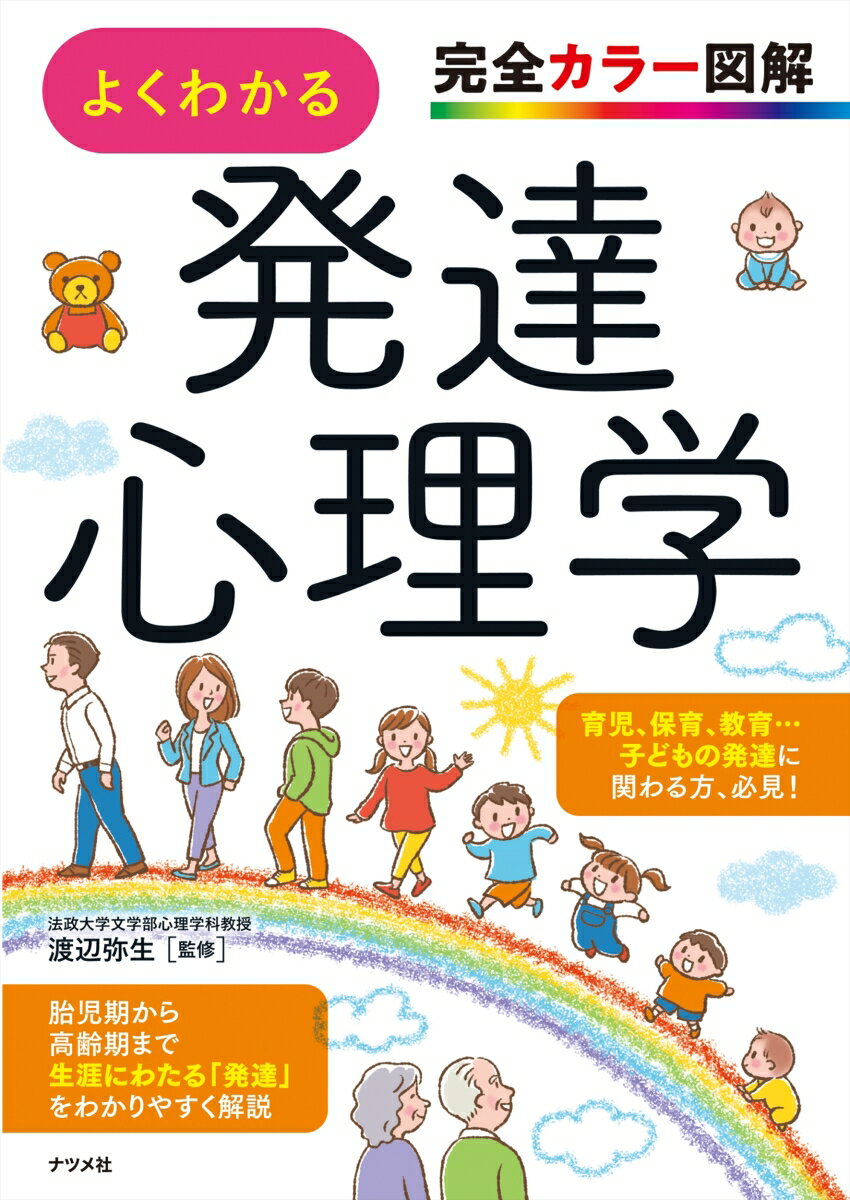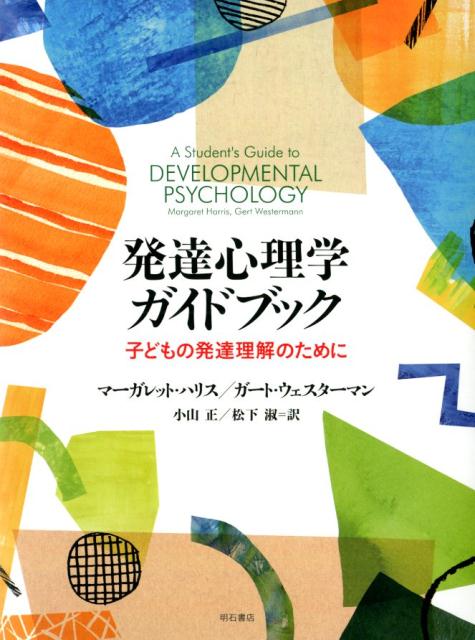息子の発達のことで
初めて教育センターを訪ねてから
約一年が経ちます![]()
これまでの事を
まとめてみることにしました
記事を書いている私は、医療従事者や専門家ではなく
ギフテッド児童を育てている、ただの主婦です
![]()
以下は、私の主観による「まとめ」と所感です
☆;:*:;☆;:*:; 前記事 ;:*:;☆;:*:;☆
ギフテッドは
「英才型」と「2E」に分類されるそうですが
わが家の場合、その「間」の気がすると思い
これまでの成長記録を綴っております![]()
この記事では、幼稚園前後で
やって良かった事を挙げてみます![]()
幼稚園を選ぶ時、しっかり見学を
先に簡単にまとめると
実際に足を運んで見学しつつ
「明るく元気でタフな子に育ってほしい」
「みんなが出来るように、出来てほしい」
という、親の願いや理想、ではなく
「現状の本人が、自分のままで
無理せず安心して過ごせる場所」
を探して、幼稚園を選びました![]()
![]()
例えば、虫が怖い男の子に対して
「いや、どろんこで駆け回れたり
隣に公園があって、よく虫取りに行く
園にして、克服しよう!」
ではなく
「人工芝で、虫の出づらい園にしとこ」
みたいな感じです…![]()
正直、自分でも、幼稚園って
近さとか、給食の有無とかで
決めちゃって良いと思ってたのですが
たまたま息子の入園の代から
幼稚園に補助金が出るようになって
私立も視野に入れられるようになったので
せっかく選択肢が広がったから
「いろいろ見てみよう!」と思ったんです
結果的に、それがラッキーでした
![]()
当時の私は、まだ
特性や発達の知識は無いながらも
息子について「少し個性的かも」と
考えていたので
まず、自由な校風を謳う園の見学に行きました
たいへん人気の私立の園で
行く前は、ほぼほぼ、
そこにしようと思ってたのですが
実際に行ってよかったです![]()
大人の想定する「自由」と
幼稚園児の「自由」には隔たりがありました
(そりゃ、当たり前ですよね![]() )
)
私の目に映った、自由な園とは
もはやカオス…!!
直感的に
「うちの子は、これは苦手だ…」と思い
そこを、検討から外しました![]()
ここは確かに、
はつらつとしたお子様には
とても合うと思います
元気いっぱいに走り回って
思う存分大きな声を出して
一見したら混沌の中にもルールがある事を知り
周りとの兼ね合い・自分の立ち位置を考え
オンオフの切り替えも覚えて
自律した、タフで明るい子に育ちそうです![]()
でも、なんというか…
うちの子は、そういうのが苦手というか
ちょっとまだ未熟で対応できないような?
そんなふうに感じました
![]()
そして、私はべつに
おとなしくて、一人遊びが好きな息子を
そのように改造したいワケじゃなかった
「苦手を克服し、強い子に育てる」
「みんなと同じように出来る」 ではなく
「本人の苦手なものが少ない、
そのままで居心地が良さそうな園」
に、行かせてあげたいと思いました
そのような基準で選んだ園は
幼児の集まる中では、比較的秩序があり、
元気や体力より、思いやりなどの
「心」を育むことに比重があり、
そしてお勉強や資格取得も肯定的で
息子に合っていたと思います
特にトラブルなく卒園することができ
息子もその幼稚園が今も大好きです
合理的配慮
後から考えれば、
発達のことをまだ知らないながらに
いわゆる「合理的配慮」に近いようなことを
幼少期からずっとしていたのかなと思います![]()
例えば、息子は
タグのチクチクや服の締め付けがダメ
また、赤ちゃんの泣き声も超苦手です![]()
やはり後から知るのですが
これらは、ASDの子によく見られる
感覚過敏の特性、またはHSCと呼ばれるものに
良く似ていますよね
私は
「それくらい我慢しなさい」
「ふつうは平気だよ、慣れなさい」
とは、あまり言いませんでした
(なんか疲れてて面倒くさい時とかは、言いました。![]() )
)
基本的に、タグならすぐ取ってあげるし
(familiarはいつも泣きながら取りました・笑)
近くで乳幼児さんが騒いでいる場合
失礼のないように気をつけつつ遠ざかるか
息子にイヤホンをつけて胸に抱き込みます
慣れろ、耐えろと言うよりも
ママは味方だ、辛い気持ちをわかってくれる
お家でもお外でも、苦手なことから守られる
と、安心感を与えてあげることが
今の彼にとって、社会に出る前に
まず育むべきことだと感じていました
人によっては、
これを甘やかしだと思われる方も
いらっしゃるかと思うのですが
我が家は、これでいいと思っているし
結果的にも我が子には合っていたと
思っています![]()
息子のような子は
人一倍不安が強かったり
色々なことに過敏だったりするようで
それは、生来の脳の個性のため
耐えさせても慣れません&治りません
そして、
その特性を持たない者が思うよりずっと
本人は苦痛に感じていると思います
一緒に寄り添って、なるべく避けるか
緩和する対処法を模索していくことが
ベストだと、今も思います
![]()
また、最近の研究では
IQが特に高い(121〜)児童は
脳の前頭前野の発達のピークが
それ以外の児童よりも遅れてくる
ことが分かってきたそうです
https://kidsna.com/magazine/article/entertainment-report-230228-00014642
どういうことかというと、高IQ児は
小学校低学年の時点では
一般的な児童より、非認知機能が未熟
だということです
最近よく
「IQばかり高くてもダメ、EQのが大事」とか
「どちらもバランスよく育てないと」
って言われたりして
高IQ児をお持ちの親御さんの中には
EQが追いついていなくて
頭を悩ませている方もいらっしゃるのでは![]()
(うちもそうです)
でも、この実験を「正」とするなら
そもそも、高IQ児は
EQの発達がやや遅めに出来ているので
協調性、コミュニケーション能力、
自制心、忍耐力、やり抜く力などは
幼いうちは、人並みより遅れててOK
12〜13歳で発達のピークが来るから
その時に成長を促してあげるとGOOD!
ということになります
![]()
脳の発達や、認知については
どんどん新しい研究が出てくるので
育児での必要性を抜いても
個人的にも面白く
これからも情報を追っていきたいです![]()
やって良かったこと、
もうひとつ書いている途中なのですが
書きたい情報が多すぎて散らかってしまい
長くなってしまったので
もう少し後でまた記事にします![]()
お読みいただき、ありがとうございました![]()