この記事の続きである。
14日に、東京・京橋の『国立映画アーカイブ』で見た、1959年製作の日本映画『人間の壁』(原作・石川達三、監督・山本薩夫、山本プロ作品)について感想を書いている。

この映画、2月14日と18日に2回だけ上映されている(明日、18日は、私は他のスケジュールが入っているし、再び、この作品を見る予定は当面ない)。
だが、現在、原作の石川達三の『新聞小説』に興味がわいてきて、その内容を読んでみようかと思っている。

というのも、(歳のせいかどうかわからないが)上映時間146分のこの映画の細部をあまり思い出すことが出来ないでいる。
何れにしても、かなり長大な小説であった『原作』(何しろ文庫本三冊分の分量で、あしかけ三年にわたって、『新聞小説』として連載された)のほんの一部を、抜粋したような作品であることは、間違いないだろう(脚本は、八木保太郎という人の名前になっていた)。

この映画で主人公の小学校の女性教師『ふみ子』を演じているのは香川京子さんである。

彼女については、こんな記述がネットでされていた。
いろんな監督に好まれて、演じてきた女優さんであり、なおかつ90歳を超えた今でも、映画やテレビに出たり、映画館でトークショーに出たりしているその活力には、驚かされる。
さて、この映画のなかでは、彼女は、『共働き』であるとして、『肩叩き(退職勧奨)』の対象とされ、自主退職=(実質)解雇を迫られている。

その夫役で出ているのが、この人である。
この映画では、『南原伸二』というクレジットが出ているが、私としては『南原宏治(なんばら・こうじ)』という芸名で記憶のなかにインプットされている俳優である。
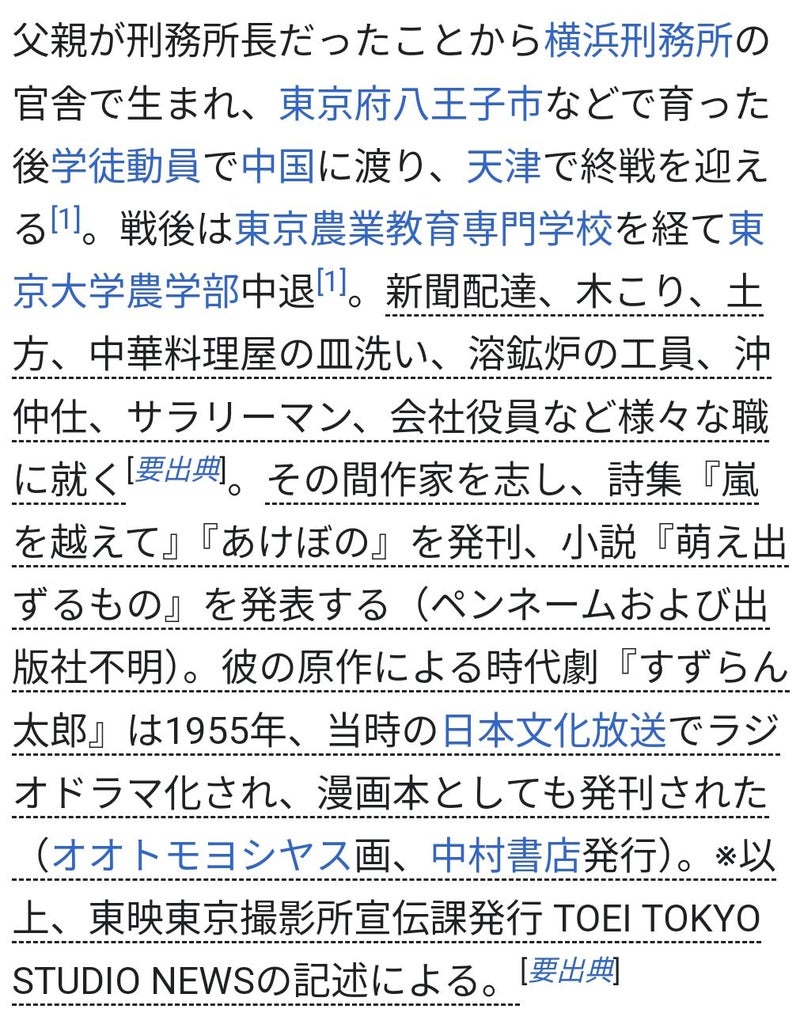
ネットで調べてみると、『1927年生~2001年没』ということで、既に20年以上前に、満74歳で亡くなっている。
(これまた、現在の私の年齢と一緒なので、ちょっとだけ気になる。)

(ネットで見ると、このようにいろんなことが書かれているが、どこまで本当かわからない。
ただ、強烈な存在感のあった役者だったと記憶している。)
この人は、1951年にデビューするが、東映移籍後の1954年より、『南原伸二』という芸名に変更し、主演作など多数で活躍を始めたという。1960年に、芸名を『南原宏治』に改名している。
ということで、『南原伸二』名で出演している作品が多数あるらしい。
『南原宏治』というと、何やらアクの強い登場人物のイメージがあるが、この作品でもまさにそうである。
香川京子(『志野田ふみ子』、旧姓『尾崎ふみ子』である)の夫(志野田健一郎)は、彼女と同じく『佐賀県教職員組合』に所属しているが、夫の方は、元中学校の教師で、現在は組合の専従役員をしている。

(残念ながら、彼の出演シーンの画像は見つけることが出来ていない。なかなかの『悪役ぶり』だったのだが…。)
『出世主義者』として描かれていて、組合の執行部を絶えず(裏では)『無能』であるとして批判している。自分がとって代わり、委員長になることを画策していた。
しかし、それは、何か労働組合の仕事について、自分の理想があってそうしているというよりも、単なる『不平分子』、ギラギラした『出世主義者』に過ぎないようだ。
『ふみ子』は、彼と見合い結婚をしたらしい。
最初は、夫・健一郎に好意を寄せていたようだが、今や、(健一郎の本質というか本性を知って)夫婦仲は冷え切っている。
健一郎は、『ふみ子』に単に『家政婦的な役割』を期待しているだけであり、しょっちゅう、自分の不満の爆発の対象として、『ふみ子』に対して暴言を吐き、また暴力をふるっている。
この健一郎が、(なぜそうなっているのか、知らないが)共産党の『秘密党員らしい』というデマが流されているらしい。
(現執行部に対して、絶えず、批判・攻撃を繰り返しているためなのかもしれない。)
『ふみ子』は、『夫が共働きだから、生活は他の人たちよりも保証されているでしょ』と教育委員会や校長などから言われて、『退職勧奨』の対象とされている。同時に夫に、『共産党の秘密党員のうわさ』があることも、彼らの『肩叩き』をより強いものにさせている。
しかし、この映画の途中で、夫の健一郎は、組合の婦人部長(沢村貞子さんが演じている)に『浮気』を仕掛けて、拒否されたりし、その後は、『組合の現在の委員長は無能である』として、委員長選挙に立候補したりしている。
だが、(人望がないため?)この委員長選挙で敗北してしまうと、今度は、組合から逃亡(脱走?)してしまうようだ。
(オルグの途中で、カネなどを持ち逃げして、姿をくらましてしまったようだ。この時、『ふみ子』の金も持ち出そうとしていた。)
そして、映画の最後のほうでは、健一郎が今度は、『日教組』全体を批判する『右派』の評論家として、突然、『その手の雑誌』に登場するに至る。
まあ、いかにもといった感じの役回りであるが、これが『南原伸二』いや『南原宏治』の肉体を借りて演じていると、『いかにも、存在していそうな人物』になっている。
いや『もしかしたら、自分もその一人かも知れない』という気がしてしまうところもある(『男性中心主義』で『自分勝手』であるところ)ので、やや複雑な気分である。
この1959年当時でも彼は、『問題の人物』として描かれているのであるが、実際、今でもこうした男性(いや、女性でもそうかもしれない)は、残っていそうだ。
そして、これは(前回も書いたように)、少し松竹伸幸氏に対して、失礼過ぎるだろうという気もしてしまうのだが、今日、(ひょっとすると)松竹氏の名前にかぶせて、イメージされている事柄とも重複している部分があるような気がする。
(といっても、世間では、必ずしも松竹氏だけを、『ピエロ』と見ているわけではない。『日本共産党』の現在の執行部に対しても、どちらに対しても、『シラケた気分』でいる人が、少なくとも党外においては多いのだろう。)
なお、この映画、石川達三氏の長編『新聞小説』を大胆に編集(カット?)した内容であり、『ふみ子』に同情(共感)した女性教師たちが、一斉に『校長室』に談判のために押しかけるところで、映画は終わっている。
(この辺は、『明日に希望を残す』という意味で、東宝争議後、日本共産党員であることが、ほぼ『公然化』していた、山本薩夫監督の作品らしい終わり方のような気がする。
もっとも、山本薩夫監督は、『いかにも日本共産党員らしい』というような鯱張った教条主義者ではなく、むしろ、『娯楽としての映画を大事にする、職人肌の人物』でもあったようだ。
こういう筋書きの映画を今回見てしまい、『さて、原作のほうはどうなっているんだろう』という気がして、今、図書館から『原作本の文庫三冊』を取り寄せている。
なお、この映画を『国立映画アーカイブ』で見た日、100人以上が会場に入っていたと思うが、妙に会場内は、普段よりも『静かだったという印象』を受けた。
私と同じ世代あるいは上の世代の人なども結構、来ていた気がするのだが、普段なら上映前の会場内でも、それなりに『おしゃべり』をする人たちがいるものだが、この日はほとんどいないという感じだった。
もしかしたら、『松竹氏の問題』で共産党内やあるいは世間でも話題になっているおりだから、その影響もあるかもしれない、という感じも多少受けてしまった。
