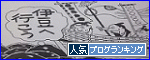国清寺 から 平安時代の僧 文覚上人配流地
毘沙門堂に向かいました。
文覚上人と”伊東”との繋がりは前にこんな形で紹介
しました(^_^) → ☆
毘沙門堂に行く途中に七つの石があるという。
この夫婦石は源頼朝と政子夫婦が毘沙門堂にいた文覚上人を
訪ねて来た折、この石に腰をおろして一息を入れたという
伝承が残っています。
蛇石 白蛇を国清寺の高僧がこの石に封じ込めたという伝説が
残っているようです。
赤牛のように暴れたのかな。
蛇石
こだま石は奥に200mぐらい入って行かないと見ることが
できません。
文覚上人配流の地、毘沙門堂
ここに奈古屋寺と呼ばれ、後に授福寺となった寺があった
そうですが、今は毘沙門堂と山門が残っています。
こちらが山門。
金剛の像
○慶の作!? いろいろ言われているようです。
授福寺
洞窟!?
木の根(゚Ω゚;)
護摩石(ごまいし)
ここに授福寺があったということです。
文覚上人が護摩を焚いたとか、硯にしたと伝えられて
います。
上はこのようになっていました。
文覚上人が修行をしたと伝えられている滝がある(あった?)
ようです。
毘沙門堂 授福寺の鎮守
ただ、明治39年に建て替えられたということです。
文覚上人は後白河法皇に逆らったために伊豆に流罪となり、
伊東祐親の水軍船でこちらに送り込まれたようです。
源頼朝が伊豆に流されたのは、1160年、文覚は1173年。
文覚はこの地で打倒平家を祈ったという。
頼朝は伊東の北の小御所で流人生活 & 初恋!?(^o^)
頼朝と文覚の回合が実現され、
文覚が頼朝に旗揚げして平家を打ち、大将軍になるように
説得したとのこと・・・