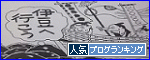江戸時代、元禄期に入ると経済的に厳しい状況に陥って
しまいました
この頃の幕府の大きな収入源は年貢が中心
他にも戦国時代に全国各地に開発された金銀鉱山からの
収入、鎖国以降も中国やオランダとの間で行われていた
貿易による収入もあった。
が、鉱山は枯渇の状態で大きな収入源にはならず、貿易も
大きな利益には繋がらなかった。
年貢による収入が唯一の便りだった。
(年貢って今の時代でいえば、税金でしょ?
ずっと減っている。
貿易収支?ここの所マイナスだよね)
この頃、米の生産高は増えて上がっていたみたいだが、市場に
出回っている通貨の量は増えない。
そのため、米の価値は下がる↓ いくら米を作って年貢として
納めさせても幕府の収入は増えません。
デフレ です。
5代将軍綱吉の浪費がひどく、幕府の収入が約80万両の時に
140万両もの支出をしたということです。
(今の時代の収入と支出のバランスと似ている)
こんなひどい時代に何をやったか・・・
貨幣政策です。
貨幣の質を変えることで幕府の収入を増やそうとしたのです。
金貨と銀貨を作る際の金と銀の含有量の割合を変えて銀の方を
多くしたのです。
金よりも銀の方が安かったのです。
金貨成分を少しずつ変化させ、幕府の収入も増加して行きました。
しだいに人々の生活も豊かになって行きます。
その後、度重なる天災、自然災害、綱吉の浪費などにより、
貨幣改鋳を繰り返しました。
貨幣の流通量が予想よりも上回り、以上なインフレとなります。
物価高騰↑ 庶民の生活はますます苦しくなりました。
図説伊東の歴史より
銅貨である寛永通宝も小判などの金銀の貨幣と同様に幕政改革の
度に改鋳されて品位は低下する傾向にあり、庶民も通貨の相場
変動の影響を強く受けていた。
改めて思いました。今だって同じではないか・・・。
応援していただけたら嬉しいです![]()