iOSアプリのバグのせいか、夜アップした記事の後半が消えていました
仕事納めでどんだけ浮かれているんだ という、訳の分からない記事になっており申し訳ありません・・・。
という、訳の分からない記事になっており申し訳ありません・・・。
書いたことを思い出しながら復元したので、再読頂けると幸いです
*********************
昨日、無事に仕事納めと相成り、今日から9連休です  嬉
嬉
復職後初の長期休暇なので、今、ものすごい解放感の中にいます 笑
そして最近バタバタと仕事が忙しかったので実は娘にまだクリスマスプレゼントのマグフォーマーを渡しておらず、さっきようやく枕元に置いてきました
朝起きた時の反応が楽しみです
「クリスマスプレゼントが遅延しているのって我が家だけかな 」と思い、同僚たちに聞いてみたところ、お子さんに「今年はサンタさんが忙しいから○○ちゃんの所には27日に来るみたいよー」と言い聞かせていた人多数・・・。
」と思い、同僚たちに聞いてみたところ、お子さんに「今年はサンタさんが忙しいから○○ちゃんの所には27日に来るみたいよー」と言い聞かせていた人多数・・・。
季節感の無い生活をしていたのは我が家だけではありませんでした
が、一応言い訳をすると、ゆず湯のような大して手間のかからないことはやっていました
ゆず湯もそうですが、最近図書館で季節・行事にちなんだ書籍を2冊借りて読んでいたところで、私にとっては知らないことばかりで面白かったです。
まず1冊めはこちら
- おうちで楽しむ にほんの行事/技術評論社

- ¥1,598
- Amazon.co.jp
月毎に暦の知識をまとめたページがあり、
2冊めはこちら

- 日本の七十二候を楽しむ ―旧暦のある暮らし―/東邦出版

- ¥1,728
- Amazon.co.jp
1年間を72に区分してそれぞれについて旬の行事、兆し、魚介、草花などがあるというのはすごいですよね。
それを聞いただけで「今に比べればずっと季節の移り変わりに敏感で、自然と共に生きていたんだろうな・・・」という気がします。
本のなかみは節気の解説が先ずあり、
次いでそれぞれの候についての解説があります。
上記2冊とは別途、こちらの本も書店で見て分かりやすくて良かったです

- 大切にしたい、にっぽんの暮らし。/サンクチュアリ出版
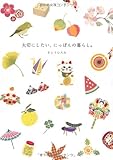
- ¥1,620
- Amazon.co.jp
娘用には『きせつの図鑑』を購入してあり、それはそれで娘が家の中を持ち歩いてはよく眺めていたり、お散歩の後には一緒に眺めて「これあったねー」などとお話したりしてとても重宝しており購入して良かった一冊なのですが、前述した3冊の中からどれか自分用にも購入したいなと思っています。
ちなみに、「お正月」に関するtipsを手元の2冊から抜粋すると以下の通りです。 1月の正月と7月のお盆の年に2回、収穫に感謝し、豊作を願い、先祖を敬う儀式を行ってきた。
1月の正月と7月のお盆の年に2回、収穫に感謝し、豊作を願い、先祖を敬う儀式を行ってきた。
正月にお招きする年神さまは田の神さまであり、ご先祖さまでもある。 お正月に食べる年越しそばには、細く長く暮らせますようにという願いが込められている。
お正月に食べる年越しそばには、細く長く暮らせますようにという願いが込められている。
除夜の「除」には1年の穢れを取り除くという意味があり、年の改まる節目に新そばを頂きながら心身を一新する習わしである。 お正月は節気では「冬至」、候では「雪下麦を出だす」に区分されている。
お正月は節気では「冬至」、候では「雪下麦を出だす」に区分されている。
この時期の旬の野鳥は雀であり、元旦の朝の雀や、そのさえずりを初雀という。
関連記事: 『きせつの図鑑』と無料工作素材



