今日も暑い。。
朝から暑い中を歩くのはダルイが、FMを聴きながらなら飽きずに歩ける。
僕の好きな朝の番組「FM福岡モーニングジャム」にクイズの時間があるが、このクイズが結構骨がある。
普通、番組のクイズなんかは誰でも分りそうな物を出すのだが、正解者が沢山出ない事を好しとして、リスナーに迎合し無いと言うのが良い。
今日の問題は日本語の問題だった。
『広辞苑(第6版)からの逆引き問題です。
ある言葉を調べてみると3つの意味が載っていました。
①舌打ちして嘆く事
②息を吐くこと
③たちどころ
さて、これらの意味を持つ言葉とは一体何でしょうか?』
僕はこの問題は分からなかった。
答えは「咄嗟(とっさ)」
今は3番の意味でしか使われる事は無いが、「咄」と言うのはチェッと舌打ちする動作や音を表し、「嗟」の字は「ああ」と言う嘆息にあたるらしい。
両方とも一瞬の行為である為「あっと言う間」と言う意味に使われる様になったらしい。
日本語は難しい(+_+)
ちなみにこの「問題です」はここでバックナンバーも読める。過去問題も面白い問題ばかりなので一度御覧あれ。
http://fmfukuoka.co.jp/cgi-local/mondai/w_mondai.cgi?p=ichiran
先日、夕食を招待してくれた知人は、インドを放浪した事があるらしい。
彼は大学の哲学科とか何の役に立つか分らない学科へ行ってるが、仏教等に詳しい。
現在はちゃんとした会社の社長だが、この前飲んでいた時に「数字」の話しになって、後日、数字の呼び方を送ってくれた。
読み方 10の何乗
十 じゅう 1
百 ひゃく 2
千 せん 3
万 まん 4
百万 6
億 おく 8
十億 9
兆 ちょう 12
千兆 15
京 けい 16
百京 18
垓 がい 20
十垓 21
�� じょ 24
穣 じょう 28
溝 こう 32
澗 かん 36
正 せい 40
載 さい 44
極 ごく 48
恒河沙 ごうがしゃ 52
阿僧祇 あそうぎ 56
那由他 なゆた 60
不可思議 ふかしぎ 64
無量大数 むりょうたいすう 68
まあ、この辺までは詳しい人は知っているのかもしれないが、まだ先がある。。
※長いので省略するが最後は
不可説不可説転 ふかせつふかせつてん 37218383881977644441306597687849648128
となるらしい。
ブログでは続けて表示されないが、10の「この数字の羅列乗」となる(笑)
何とも気の遠くなる話で、知っていても、生きている間に使う事は無さそうな数字だ(笑)
最近気に入っているドラマに「日本人の知らない日本語」と言う夜中のドラマがある。
原作も面白いらしいが、ドラマも中々面白い。
見ていると、「あ~俺も全然わかって無いなぁ」って時が良くある。
こうして、ブログなんか書いていると、時々、「あれ?これってあってるのかな?」って表現もあるし、恐らく、かなり誤字・脱字含めて誤記があるのでは無いだろうか。(ごめんなさい)
とりあえずチェックはしているのだが、それでも、知らずに使っていたりする場合等はチェックの対象外となってしまう。
日本語でさへこれなので、音楽となると尚更かもしれない。
以前、音楽用語の話を書いたが、それ以外にも普通良く目にする音楽記号でもちゃんと説明しろと言われるとヘタレてしまう場合がある。
以前、非常に気になったのが「Diminuendo(ディミヌエンド)」と「Decrescendo(デクレッシェンド)」の違いだ。
日本語だと、どちらも「だんだん小さくする」だが、以前紹介したイタリア語の本の解説を読むと、Diminuendoと言う言葉の語源は「deminuere」強調を意味する「de」+「minuere」と言う形になっていて、「minuere」は「minus」の元となっている言葉だ。
「minus」と言うのは、算数で使う「マイナス」
音楽では「meno(メーノ)」と言う形で、meno f等でも使われている。
日常生活では「ミニチュア」と言う言葉も「ミヌ」が元となっているし、その他「ミニスカート」「メニュー」等も同じ語源らしい。
又、ダンスや音楽用語で「メヌエット」と言うのがあるが、これも「小さな歩幅で踊る舞踏」と言う意味だ。
これらの言葉から察すると、Diminuendoと言うのは、その場所から音を小さくする、そして、それが続くので、だんだん小さくする。となり、いわゆるデジタル的に小さくなるイメージ。(デジタル的にと言うのは和声的な動きと言っても良いかもしれない)
Diminuendoと言う言葉は実生活では「暑さが和らいできた」「出生率が減ってきた」と言う風に使われるらしい。
これに対して「Decrescendo」と言うのは「crescere(クレーシェレ)」と言う「成長する」「大きくなる」「増える」と言う意味の動詞、それが~doで継続する「crescendo」に「下に」と言う意味の接頭辞「de」が付いた物だ。
この「crescere」はラテン語の「creare(クレアーレ)」(想像する)が語源となっていて、英語の「creaiton(創造)」もこの「creare」が語源だ。
これらの言葉はcrescendoなら「子どもは元気に育っている」decrescendoなら「潮がだんだん引いてきている」等と使うようだ。
この辺りの語源から、「Decrescendo」は何かしら形の無い物が小さくなったりするイメージであり、これはアナログ的と言っても良いかもしれない。
作曲家がこの二つを厳密に使い分けているのかどうかは判らないが、この二つが出て来た時の僕のイメージはこんな感じだ。
この些細な違いが音楽にどの程度役に立つのかは不明だが、少なくとも、これらの記号が出て来た途端に音を小さくする様な事はしない(笑)
何れにしても、その箇所から小さくなるので、スタート地点はそれまでの大きさだ。
只、各奏者がこの様なイメージを持ちアンサンブルをする事で音楽もより深い表現となるだろうし、自分達の正しい意図も伝えられ、面白さも出る。
これは日本語に関しても同じなのでは無いだろうか。
僕は短い言葉で何かを伝えるのが下手で、すぐに長くなってしまうが、短い言葉で何かを伝えられる(例えば詩の様に)人はすごいと思う。
正しい日本語の使い方も、単に記憶として止めるのでは無く、使ってナンボだ。
言葉の意味を理解して、良いタイミングで伝えると言う事が出来れば、これだけ種類の多い日本語だ。自身の正しい意図も伝えられるし、もっと人間関係も深くなり面白くなるのかもしれない。
- 日本人の知らない日本語/メディアファクトリー
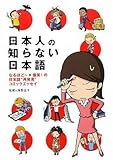
- ¥924
- Amazon.co.jp