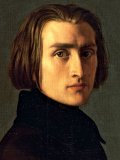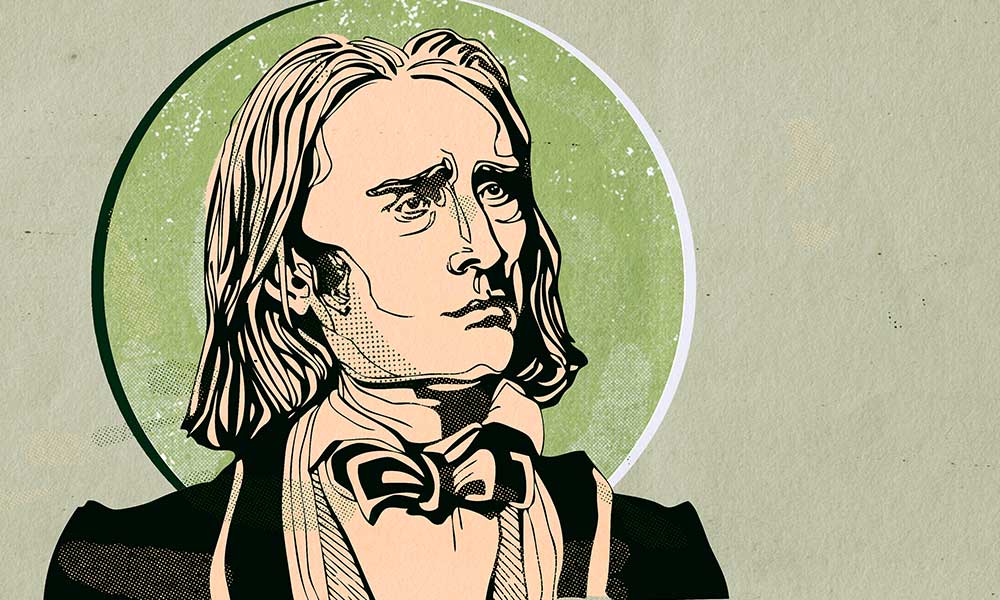フランツ・リスト(ドイツ語:Franz Liszt/ハンガリー語読み:リスト・フェレンツ[ハンガリー語: Liszt Ferenc]/1811年10月22日~1886年7月31日)は、ハンガリー王国出身で、現在のドイツやオーストリアなど欧州各地で活動したピアニスト、作曲家。
1811年10月22日、フランツ・リストは、オーストリア帝国領内ハンガリー王国ショプロン県ドボルヤーン(現:オーストリア共和国ブルゲンラント州ライディング)にて、ハンガリー貴族エステルハージ家に仕えていたオーストリア系ハンガリー人(ドイツ系)の父アーダム・リストとオーストリア人(南ドイツ人)の母アンナの間に誕生。
ドイツ人ヴァイオリン奏者フランツ・リストを叔父に、同じくドイツ人刑法学者フランツ・フォン・リストを従弟に持つのは、このゲルマン系の家系のためであり、リスト自身も最終的にはドイツに定住した。
家庭内においてはドイツ語が使われていたこと、またドイツ語およびドイツ系住民が主流の地域に生まれたため、彼の母語はドイツ語であった。しかし、後にパリに本拠地を移して教育を受けたため、後半生はフランス語の方を多く使っていた。この他数ヶ国語に通じながら、ハンガリー人を自認していた彼が生涯ハンガリー語だけは覚えなかったことを不可解とする向きもあるが、時代背景的に生地・血統共に生粋のハンガリー人でさえドイツ語しか話せない者も珍しくなかったという事情から、国民国家の価値観が定着した現代の感覚でこれを疑問視することは適切とは言えない。なお、歌曲は大部分がドイツ語(一部はフランス語)で書かれている。
家名の本来の綴りはドイツ系固有の List で、Liszt はそれをハンガリー語化した綴りである。ハンガリー名はリスト・フェレンツ(Liszt Ferencz/現代ハンガリー語表記:Liszt Ferenc)で、彼自身はこのハンガリー名を家族に宛てた手紙で使っていたことがある。リストのハンガリーのパスポートではファーストネームの綴りがFerenczとなっていたのにも拘らず今日ではFerencと綴られるが、これは1922年のハンガリー語の正書法改革で苗字を除く全ての語中のczがcに変更されたためである。1859年から1867年までの公式の氏名はフランツ・リッター・フォン・リスト (Franz Ritter von Liszt) だったが、これは1859年に皇帝フランツ・ヨーゼフ1世によりリッター(騎士)の位を授けられたためであり、リスト自身は公の場でこのように名乗ったことは一度もなかった。この称号はカロリーネ・ツー・ザイン=ヴィトゲンシュタインと結婚する際、カロリーネを身分的特権の喪失から守るために必要だったが、カロリーネとの結婚が婚姻無効に至った後、1867年にリストはこの称号を自身よりも年少の叔父のエードゥアルトに譲った。エードゥアルトの息子が法学者のフランツ・フォン・リストである。
幼少時より、父親の手引きで音楽に才能を現す。
10歳になる前にすでに公開演奏会を行っていた.
1822年、リストはウィーンに移住し、ウィーン音楽院でカール・チェルニーおよびアントニオ・サリエリに師事する。
1823年にはパリへ行き、パリ音楽院へ入学しようとしたが、当時の規定により外国人であるという理由で入学を拒否された。こうした規定が存在したのは学生数の非常に多いピアノ科のみであった。他の科においては、外国人であることを理由に入学を拒否された例はない。このため、リストはフェルディナンド・パエールとアントン・ライヒャに師事した。
1824年には、ルイジ・ケルビーニとパエールの手助けにより、オペラ『ドン・サンシュ』を書き上げて上演したが、わずか4回のみに終わった。
4月13日にウィーンでコンサートを開き、フンメルのピアノ協奏曲第3番やモシュレスのピアノと管弦楽のための変奏曲などを弾いた。その際、コンサートに出席していたベートーヴェンに賞賛され、その様子を描いた石版画なども後世に作られたが、当時の演奏会にベートーヴェンが出席した記録や報道がないことから今日ではこのエピソードは否定されている。
1826年、15歳の時、フランス(op.6)、ドイツ(op.1)で『すべての長短調のための48の練習曲』初稿を出版。実際には12曲であった。サール番号はS.136。後に『超絶技巧練習曲』(フランス語:Études d'exécution transcendante/サール番号:S.139, ラーベ番号:R.2b)として知られるようになる。第4曲“マゼッパ”、 第5曲“鬼火”が有名。
1827年、父アーダムが死去し、わずか15歳にしてピアノ教師として家計を支えた。この時、教え子であったカロリーヌ・ドゥ・サン=クリック伯爵令嬢と恋愛関係になるが、彼女の父の介入から身分違いを理由に破局となる。
生涯に渡るカトリック信仰も深め、思想的にはサン=シモン主義、後にはフェリシテ・ドゥ・ラムネーの自由主義的カトリシズムへと接近していった。
1831年にニコロ・パガニーニの演奏を聴いて感銘を受け、自らも超絶技巧を目指した。同時代の人間である、エクトル・ベルリオーズ、フレデリック・ショパン、ロベルト・シューマンらと親交が深く、また音楽的にも大いに影響を受けた。
ピアニストとしては当時のアイドル的存在でもあり、女性ファンの失神が続出したとの逸話も残る。また、多くの女性と恋愛関係を結んだ。
特に、マリー・ダグー伯爵夫人(後にダニエル・ステルンのペンネームで作家としても活動した)と恋に落ちた。
1835年にスイスへ逃避行の後、約10年間の同棲生活を送る。2人の間には3人の子どもが産まれ、その内の1人が、後に指揮者ハンス・フォン・ビューローの、さらにリヒャルト・ワーグナーの妻になるコジマである。
1838年のドナウ川の氾濫の時にチャリティー・コンサートを行い、ブダペストに多額の災害救助金を寄付している。
1844年にはマリーと離別。再びピアニストとして活躍した。
1847年、演奏旅行の途次であるキエフにて、当地の大地主であったカロリーネ・ツー・ザイン=ヴィトゲンシュタイン侯爵夫人と恋に落ち、同棲した。彼女とは正式の結婚を望んだが、カトリックでは離婚が禁止されている上に、複雑な財産相続の問題も絡み、認められなかった。
1848年、以前からリストとヴァイマール宮廷の間には緩やかな関係があってリストは客演楽長の地位にあったが、常任のヴァイマール宮廷楽長に就任した。カロリーネの助言もあって、リストはヴァイマールで作曲に専念した。
以後も機会があればコンサートでピアノを弾くことはそれなりにあったし小さなサロンではよく弾いたが、これを機にリストはヴィルトゥオーゾ・ピアニストとしてのキャリアを終え、指揮活動と作曲に専念するようになった。
リストが最も多産で活発な音楽活動を行ったのが、このヴァイマール時代である。
リストはこの地で、多数の自作を含めて、当時の先進的な音楽を多く演奏・初演したが、地方の一小都市に過ぎず、また保守的だったヴァイマールの市民に最後までリストは受け入れられなかった。実際、リストが指揮するコンサートはガラガラだったという。ヴァイマール宮廷のオーケストラの規模は貧弱で、オーケストラの団員はリストの在任中40名を越えたことは1度もなく、1851年の段階ではオーケストラ団員35名、合唱団員29名、バレエ団員7名という少なさで、その給料の低さもひどいものだった。リストはヨアヒムをコンサートマスターとして招聘したり、オーケストラ団員を増員するなど改革に努力したが、保守的だったヨアヒムは結局リストの先進性を受け入れることができずコンサートマスターを辞任するなどトラブルは絶えず、結果は実らなかった。
それにもかかわらずリストはこの地で新しい歌劇の演奏活動にも積極的に取り組んだ。
1949年2月中旬、ワーグナーの歌劇『タンホイザー』のヴァイマール初演。
同年、『ピアノ協奏曲第1番』(Piano Concerto No. 1)が完成。リストは26年の歳月をかけて、このピアノ協奏曲第1番変ホ長調を作曲した。彼は1830年、19歳の時に最初のピアノ協奏曲の主要主題を書いている。冒頭の力強いモチーフは、後続のすべての主題から派生した、本質的な要素を含んでいる。この協奏曲は4楽章で構成されているが、単一楽章のように連続して演奏される。
同年~1850年、“コンソレーション”(Consolations, Six Penseés poétiques)を作曲。日本では“慰め”のタイトルでも知られる。
1850年8月28日、歌劇『さまよえるオランダ人』のヴァイマール初演。
同日、歌劇『ローエングリン』の世界初演。特に『ローエングリン』の世界初演はエポック・メイキング的な演奏会であり、この初演は、『タンホイザー』のヴァイマール初演の時ほどの成功を勝ち取ることはできなかったにしても、これ以降、ヴァイマールは当時の最先端の音楽の中心と目されるようになった。
1851年、『パガニーニによる大練習曲』が完成。ニコロ・パガニーニの『24の奇想曲』と『ヴァイオリン協奏曲第2番』に基づいてフランツ・リストが作曲(編曲)した作品である。作曲は1838年だが、改訂1851年の方が一般的。第3曲“ラ・カンパネッラ”は特に抜粋されて演奏されることが多く、リストの曲の中でもっとも有名な作品の一つ。
1852年、シューマンの劇音楽『マンフレッド』の世界初演をヴァイマールにて実施。
同年、41歳の時、『超絶技巧練習曲』第3稿が出版。今日最も頻繁に演奏されているのはこの稿である。この曲集についても第2稿同様にカール・チェルニーに献呈された。
同年~1853年、『ピアノ・ソナタ ロ短調』(Piano Sonata In B Minor)を作曲。ただし現存する最も早いスケッチは1849年に遡り、また同年の時点で初期形が演奏されることがあったと考えられる。一般的にリストの傑作と認められており、彼の重要な技法である「主題変容」の模範となっている。この壮大な単一楽章のピアノ独奏のためのソナタは、音楽的にも技術的にも演奏者に最大限の力を要求するものであり、リストの最高傑作の一つである。リストは、シューマンがリストに『幻想曲ハ長調 作品17』を献呈したことへの返礼として、このソナタをロベルト・シューマンに献呈した。
1853年、『ハンガリー狂詩曲』の最初の15曲が出版された。採取的には1885年までに20曲で完成となるが、現在は15曲までが出版・演奏されることが多く、晩年に書かれた残りの4曲は書法も簡素となっており知名度は低い。この曲集の中で第2番(管弦楽用の第2番)は知名度が高い。また、ピアノ曲集であるが、その難易度の高さで知られており、作曲者自身によるオーケストラ、ピアノ二重奏、ピアノ三重奏のための編曲版もある。
1854年、『ファウスト交響曲—3つの人物描写による』(A Faust Symphony)を作曲。ゲーテの戯曲『ファウスト』に触発されて作曲された。リストはファウストの物語を追うのではなく、3人の主人公(ファウスト、グレートヒェン、メフィストフェレス)の肖像を音楽で描いている。
1855年、歌劇『ゲノヴェーヴァ』をヴァイマールにて演奏。
その他、ベルリオーズの歌劇『ベンヴェヌート・チェルリーニ』、劇的交響曲『ロメオとジュリエット』、マイアベーアやヴェルディの歌劇など、多くの大規模作品をヴァイマールで演奏している。
一方でリストはこれ以外にも保守的な歌劇も多く指揮した他、客演指揮者による歌劇の演奏も多く行われたため、ヴァイマールでは歌劇の演奏は非常に活発だった。
また、当時の最新の音楽が演奏されたこともあって、新しい音楽に敏感な音楽家がヴァイマール詣でをするようになった、
一方、リストがカロリーネ侯爵夫人と愛人関係にあることは保守派に攻撃の口実を与える不利な材料として作用した。カロリーネも市民から快く思われておらず、街中で市民から侮蔑の言葉を浴びせられることもあった。離婚問題に絡んだ政治的な策謀もからまって、カロリーネの社交パーティーにも宮廷の官吏は寄り付かないようになっていた。
1856~61年頃、『メフィスト・ワルツ第1番』(Mephisto Waltz No. 1)を作曲。第1番は、リストが作曲した4つの『メフィスト・ワルツ』の中で最も人気のある曲である。このワルツは、ドイツのファウスト伝説に登場する悪魔、メフィストにちなんで名づけられた。リストの名人芸的な音楽のスタイルは、これらの作品に見事に反映されており、彼の悪魔や標題音楽に対する強い興味が反映されている。
1858年には、弟子のペーター・コルネリウスによる歌劇『バグダッドの理髪師』で聴衆から激しいブーイングを受ける事件が起こり、これが原因で翌年には音楽長の職を辞すことにした。カール・アレクサンダー大公は友人でもあるリストに翻意するように説得を試みたが、リストの意思は固く復職することはなかった。辞職を翻意しなかった理由は複雑であまり明瞭ではないが、やはりカロリーネ侯爵夫人との結婚問題が大きな要因であったことは否定しがたいようである。
1860年5月、離婚問題を打開するため、カロリーネは現夫との結婚の無効を求め、同時にリストとの結婚をローマ法王ピウス9世に許可してもらうためローマに1人で出かけていった。
1861年8月17日、その後しばらくリストはヴァイマールのアルテンブルク荘で1人で自由な生活を送っていたが、結局カロリーネを追いかけてヴァイマールを後にした。
10月21日、途中ベルリン、パリを経由し、ローマに到着、以降はローマに定住するようになった。リストがローマに行った理由は、資料によって説明がばらついていてはっきりしない。ローマに行ったカロリーネを追いかけて行ったという説明もあれば、1859年にリストがドイツで会ったホーエンローエ (Hohenlohe) 枢機卿がリストの教会音楽改革計画に賛同し、後にリスト宛てにローマから手紙を書いて、リストのローマ定住を希望したからだと書くものもある。
同年、『ピアノ協奏曲第2番イ長調』が完成。1839年に着手し、完成後に何度も補筆や改訂を施し、ようやく決定稿が出された。
1865年、ローマに移住した後、リストは僧籍に入る。ただし下級聖職位で、典礼を司る資格はなく、結婚も自由である。それ以降『2つの伝説』などのように、キリスト教に題材を求めた作品が増えてくる。
同年、ピアノ独奏を伴う管弦楽曲『死の舞踏』(Totentanz)が初演。1832年にパリでコレラが流行した時の悲惨な光景をきっかけに、リストはグレゴリオ聖歌の旋律「怒りの日(Dies Irae)」を多くの作品で使用した。この曲はグレゴリオ聖歌の素材に基づいているため、中世的な響きを持つ模倣対位法が含まれているが、アレンジの最も革新的な点は、非常に現代的で打楽器的な響きのピアノ・パートにある。
1870年代になると、作品からは次第に調性感が希薄になっていく。
1877年の『エステ荘の噴水』は20世紀の印象主義音楽に影響を与え、ドビュッシーの『水の反映』に色濃く残っている。同時にラヴェルの『水の戯れ』も刺激を受けて書かれたものであると言われている。『エステ荘の噴水』の作曲時、エステ荘にたくさんある糸杉をみた印象をカロリーネ宛ての手紙に書いている。「この3日というもの、私はずっと糸杉の木々の下で過ごしたのである!それは一種の強迫観念であり、私は他に何も―教会についてすら―考えられなかったのだ。これらの古木の幹は私につきまとい、私はその枝が歌い、泣くのが聞こえ、その変わらぬ葉が重くのしかかっていた!」(カロリーネ宛て手紙1877年9月23日付)。
1882年、リストがヴェネツィアで義理の息子ワーグナーの死を予感していた時に、ヴェネツィアの 潟湖に浮かぶ葬送用ゴンドラの印象的な映像からインスピレーションを得て『悲しみのゴンドラ』 (S.200)を作曲。義理の息子であったがリストの敬愛するワーグナーは、リストがこの作品を作曲してから2ヵ月も経たない1883年2月、葬列の中で最期の安息の地へと運ばれていった。
1885年に『無調のバガテル』で無調を宣言したが、シェーンベルクらの十二音技法へとつながってゆく無調とは違い、メシアンの移調の限られた旋法と同様の旋法が用いられた作品である。この作品は長い間存在が知られていなかったが、1956年に発見された。
晩年は虚血性心疾患・慢性気管支炎・鬱病・白内障に苦しめられた。また、弟子フェリックス・ワインガルトナーはリストを「確実にアルコール依存症」と証言していた。晩年の簡潔な作品には、病気による苦悩の表れとも言うべきものが数多く存在している。
1886年7月31日、バイロイト音楽祭でワーグナーの楽劇『トリスタンとイゾルデ』を見た後に慢性気道閉塞と心筋梗塞で亡くなり、娘コジマの希望によりバイロイトの墓地に埋葬された(ただしカロリーネは、バイロイトがルター派の土地であることを理由に強く反対した)。
第二次世界大戦前は立派な廟が建てられていたが、空襲によりヴァーンフリート館(ワーグナー邸)の一部などともに崩壊。
戦後しばらくは一枚の石板が置かれているのみだったが、1978年に再建された。
(参照)
Wikipedia「フランツ・リスト」「Franz Liszt」
(関連記事)