『思考法を鍛えることで発想を促す方法』
今回の学習の中では、スイミーが考えた作戦をどれだけたくさん子どもたちが考え出すかに重点がありました。この場面で、子どもたちはスイミー自身になり切って、一生懸命考える。いろいろ考える。うんと考える。あきらめないで考える。こんなことはどうかな、あんなこともできるかなと考える。こうした「思考する児童の姿」があれば授業は成り立ちます。
一つの答えではなく、思考を広げていくための訓練方法がありますので紹介します。
(1)水平思考(ラテラル・シンキング)
ある問いに対して、いくつもの答えを考えていかなくてはならないクイズがあります。水平思考という思考方法を鍛えるためのクイズです。
『ウミガメのスープ』という本をぜひ読んでみてください。その本には例えば下記のようなクイズが載っています。
【問題】
ある男が、とある海の見えるレストランで「ウミガメのスープ」を注文しました。しかし、彼はその「ウミガメのスープ」を一口飲んだところで止め、シェフを呼びました。
「すみません。これは本当にウミガメのスープですか?」
「はい・・・ ウミガメのスープに間違いございません。」
男は勘定を済ませ、帰宅した後、自殺をしました。何故でしょう?
この問題は出題者と解答者が必要です。解答者は出題者にいろいろな質問をしながら答えにたどり着こうとします。出題者は質問に対して「はい」「いいえ」「関係ありません」としか答えられないルールになっています。
解答者は様々な状況を考えながら、思考の幅を広げて質問をしていきます。こうして、さも水平に広がっていくかのような数多くの答えを引き出していく力を伸ばすためのクイズです。
(答えを知りたい方は、私に質問をくり返して下さい。「はい」「いいえ」「関係ない」の言葉で対応させていただきます。)
こんな問題を、ちょっとした時間(給食中、授業が少し早く終わった時など)に出してあげるだけで、子どもたちの発想力を自然に鍛えることができます。出題している教師も楽しめますので、ぜひ試してみて下さい。
(2)論理的思考(ロジカル・シンキング)
水平思考とは違って、説明文でよく使われるものが論理的思考力です。この思考力を伸ばすためのキーワードは考えを「階層化」と「収束化」していくことです。
「階層化」とは論を広げていくことを言います。実は今回の学習の中でも階層化で考えさせることもできるのです。こんな感じです。
「作戦」と言えば、例えば、「変身したり」「作ったり」「泳いだり」「かくれたり」「話したり」
「力を合わせたり」することが考えられます。
「変身」といえば、みんなで集まって「大きな魚」「怖い魚」「魚ではないもの」「海そう」「岩」「潜水艦」などに変身することが考えられます。
「大きな魚」は「サメ」とか「エイ」のようになればいいし、「怖い魚」なら「ウツボ」とか「アンコウ」もいいかもしれません。
また、「作ったり」することといえば、「基地」「バリア」「うすまき」などが作れるかもしれません。
このように階層化して論理的に考えるだけでも10以上の意見が出てくるわけです。
「収束化」というのは「階層化」の逆をすることです。「つまり」とか「要するに」という言葉を使って、広げた発想を一つにまとめていきます。
「エビ」「タコ」「ウミカメ」「イソギンチャク」「クラゲ」に変身する作戦を考えました。つまり「魚ではない海にいるもの」になろうとしたのです。
という具合にまとめます。
この「階層化」「収束化」の作業は大人の論理的思考力も大いに鍛えてくれますので、何かを考えようとした際にはパターンにはめて考えることが楽だと思います。
(3)フレームワークのすすめ
「水平思考」「論理思考」の他にも、様々な思考方法があります。こうして「思考の型」「思考の枠」にはめて考えていくことを「フレームワーク」といいます。フレームワークには「マトリックス」や「PDCAサイクル」「ロジックツリー」「SWOT分析」「マインドマップ」「マンダラート」「偏愛マップ」など、いくらでも存在しています。ケースバイケースで使えるようになると、思考力アップにつながります。
読んでいただきありがとうございます。
できましたら応援の1クリックをお願い致します。
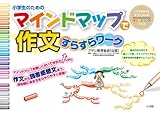 | マインドマップで作文すらすらワーク (ドラゼミ・ドラネットブックス) |
| クリエーター情報なし | |
| 小学館 |