「思想は逃がすな」
これは私が大学時代からモットーにしてきた言葉です。
油断をしていると、せっかく思いついたアイデアもたちまち忘れてしまうのが人間の脳です。「エビングハウスの忘却曲線」というものがあります。人間は学んだことを24時間以内に復習しないと80%も忘れてしまうようにできています。1か月もすればきれいさっぱり忘れる能力があります。ですから、得られた知識や思いついたアイデアは、すぐにメモをしておく必要があります。
アメリカの元副大統領であるアル・ゴア氏は、アイデアを逃がさないようにするために、いつでも大きめのポストイットを持っていてメモを取る。オフィスの中にもあちらこちらに貼ってあるそうです。
(8)アクション(行動)によるフォローアップ(対査)なきプロジェクト(計画)はパフォーマンス(実績)を生まない
マネージメントでよく取り上げられる「PDCAサイクル」にもあるように、DO(行動)することが非常に大事です。ただ、とても時間がない私たち教員が気をつけなくてはいけないのは、DOの前の「PLAN(計画)」の段階での努力をおろそかにしないということです。たくさん教材研究をし、入念に授業計画を立て、その上で「DO(行動)」していかないと実力は伸びないです。
PLANを立てるのはいつでもできます。風呂に入っている時に「そうだ!こんな授業をしたら面白いぞ!」と立ってしまうこともありますし、バラエティ番組を見ていて「この流れは授業に使えそうだ!」と、さんまさんや所さんあたりにヒントを得る場合もあるかもしれません。
情報のアンテナをいつも立てておいて、引っかかってきたものを組み立てなおし、まずは実行してみる。その行動から返ってきたものをフォローアップしていけば良いパフォーマンスの授業に変わります。
(9)人間は単脳マシーンではない
人間の脳は一度にひとつのことしか考えられません。しかし、脳内にマルチなチャンネルを作り上げることは可能です。
小学校の授業は45分単位で教科がどんどん入れ替わっていきます。実はこれが脳に良い刺激を与えています。同じことを90分も120分もやっていると、脳は疲れて自ら機能を弱めていきます。適度な時間に適度な刺激を与えることで活性化するのが脳です。学習効果を高めるためにも、20分休みや昼休みに運動をすることも大事です。ストレスを発散するだけではなく、脳が運動という別のチャンネルを動かすことになるので、次の時間へのエネルギーになるのです。
読んでいただきありがとうございます。
できましたら応援の1クリックをお願い致します。
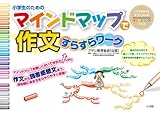 | マインドマップで作文すらすらワーク (ドラゼミ・ドラネットブックス) |
| クリエーター情報なし | |
| 小学館 |