私たちは、戦後というたった70年の時代に生まれましたので、学校に行くのが当たり前すぎて、このようなことを深く考えずに生きてきたかもしれません。しかし、人類の歴史は200万年とも300万年ともいわれるほど長い期間です。学校に通うことが当たり前になった期間は、明治時代の終わりごろからだと考えても100年間。「200万分の100」です。これをパーセントで表せば、わずか0.00005%です。
私たちは「何のために勉強しているのでしょうか?」
大人はご自分なりの答えを持っているようにしませんか。
さて、「何のため」というフレーズは、あらゆる教育活動についてくるものだと、私は自分に言い聞かせてきました。「何のためを常に問え、意味のないことを決してするな」と。
あらゆる指導に「何のため」という裏付けが必要だと思います。
「何のために漢字を練習するのか」
「何のために読書をするのか」
「何のために算数を学ぶのか」
「何のために行事があるのか」
「50m走を最後まで全力で走ることにどんな意味があるのか」
教師にはなんとなく分かっていることでしょうが、一度、文字にして考え、まとめてみることをお勧めします。
東京大学教授で「教えて考えさせる授業」の著者である市川伸一先生は、読売新聞教育ルネサンスで、こんなことを言っています。
「勉強する動機はもともと多様だ。学校教育で最も不足してきたのは『実用志向』の視点だろう。教科は学問の体系が基礎にあるため、専門の先生ほど実用的なものを軽視しがちだ。例えば数学。小学校の算数は身近でも、中学、高校とレベルが上がるほど何に役立つのか実感できず、関心が下がりやすい。必要感のない子に『数学は美しい』と言っても響かない。」
「何のため」という意義を明確に意識できている子は、少々の壁にぶつかっても、自分の力で乗り越えていけるでしょう。これこそ「生きる力」といってもいいのではないかと思います。
読んでいただきありがとうございます。
できましたら応援の1クリックをお願い致します。
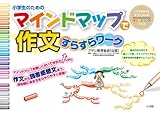 | マインドマップで作文すらすらワーク (ドラゼミ・ドラネットブックス) |
| クリエーター情報なし | |
| 小学館 |