この「教務主任通信」はOJT推進のための研修資料として提供させていただいているものです。
********************
授業はできるだけ“美しく”
大河が流れるように、ねらいの達成を目指して、教室にいる全員が粛々と取り組めたらすばらしいと思うのです。
「粛々と」を辞書で調べると、「ひっそりと静まっているさま。おごそかなさま。厳粛なさま。」と出てきます。卒業式や入学式の空気は、まさにこの「粛々と」なのですが、それは日ごろの授業から鍛えに鍛えてこそ生まれるものだと思います。
今年の校内研究は「学習交流」を生み出すためにはどうしたらよいかという切り口で取り組むことになっていますが、こどもたちが挙手もせずに勝手に話したり、授業者の言葉にあげ足を取ったりするような雰囲気を生み出しては学習のルールが崩れ、真面目に学習をしている子たちが目立たなくなり、冷めた態度になっていきます。たとえ素晴らしい意見を言っていても、勝手に発言したものは私語であるという規準を持っていることが必要でしょう。
「学習交流」を生み出すために、ひとつの授業モデルを提案してみます。
(1)ノートには毎回、「日付」「曜日」「学習ページ」を書かせる。
(2)本時のねらいを必ず板書する。(これをしないと授業はブレます。)
(3)授業を始める前に、授業者は「タイムスケジュール」を決めておく。できれば板書する。
(4)ねらい確認(場合によっては教師の教え込み)⇒個人の思考作業⇒全体の学び合い⇒まとめ⇒ふりかえり
この流れで全ての教科の授業を行う。
(5)単元を指導する前に「評価規準」を確認し、その規準に従って支援をする。
(6)長期的な見通しを立てて、学び合える児童に育てる。
本当に建設的な意見交換ができる集団になるには、新しい学級になって3カ月は必要だと感じています。
(7)「気づき」の生まれる授業を繰り返していけば、こどもたちは学び合うことを楽しむように成長していきます。
次に、児童をポジティブにする指導方法を示しておきます。
「~~してはダメ」「~~しないように気をつけましょう」「どうして~~なのか」「私語はやめなさい」という禁止言葉は人間や学級集団をネガティブにし、持っている能力を下げていきます。
「~~していこう」「~~ができるクラスにしよう」「脳に汗をかくくらい考えよう」「やってみよう」という行動イメージを促す言葉は、心の制限が自然に外れて、こどもの持てる以上の力を発揮させられるようになります。
「学び合い」もポジティブな集団であれば、男女関係なくコミュニケーションを楽しむようになるでしょう。
読んでいただきありがとうございます。
できましたら応援の1クリックをお願い致します。
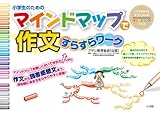 | マインドマップで作文すらすらワーク (ドラゼミ・ドラネットブックス) |
| クリエーター情報なし | |
| 小学館 |