
今日は飯田橋のとある会議室を使って、公認マインドマップフェロー第7期・11名の「養成講座」に参加しました。昨年度、学年担任を組んでいたモジャ先生と私で、教育実践報告を担当したからです。
マインドマップの活動も4年目に入り、教育現場でもかなり使われてきました。今回の養成講座を受けに全国から集まった先生方も、大学の教授をはじめ、それぞれがマインドマップがなくてもその道のスペシャリストばかり。そんな実力のある先生方が、マインドマップに可能性を見出して、3日間たっぷりの研修を受けに来ているわけです。このことだけでも十分にマインドマップのパワーを証明していると言えるでしょう。
さて、今日は16時過ぎくらいから、モジャ先生の話に始まり、6名もの実践報告者が語り継ぎました。終わったのがなんと20時。なんと4時間近くも代わる代わる話をし続けたのです。聞いていらっしゃる研修生の先生方は、それまでにも午前中からワークを続けていて疲れているのに、私たちの話を真剣に聴いてくれました。本当にありがとうございます。また、きっと今ごろ、今日の宿題で出された「ビジョンマインドマップ」に取り組んでいらっしゃることでしょう。人によっては寝られずにかいていることと思います。マインドマップフェローの研修は本当に厳しい研修ですが、やったことはすべて自分のためになりますので、受講生の先生方はフェローに公認されるまで、絶対に挫折せずに頑張って下さい。
このブログ記事は、全国のフェローの皆さんの目に触れると思いますので、その期待に応え、講義記録をしたマインドマップを載せておきました。ポイントだけ書いておきますので、気になるフェローの先生は、コメント欄で質問をして下さい。コメント欄での私とのやりとりが、また新しいアイデアを生むかもしれません。よろしくお願い致します。
ひとつだけ、私の中で大きな気づきがあったので、そのことだけ紹介しておきます。
盲学校での実践事例です。
目が見えない子どもたちを指導している盲学校ですから、マインドマップをかかせることはできません。そこで、担当の先生が生徒との対話を続けながら、生徒が話したことをマインドマップで書き取っていく。すると、不思議なことに、盲の生徒がまるでマインドマップをかいたかのような効果が顕れる。その対話の際に、「それだけ?」「それから?」という投げかけをしてあげるだけで、生徒は言葉を広げていく。すると、指導している教員がマインドマップでメモを取っているために、自然を質問内容も自然と「階層化」していく。言葉を「階層化」することによって、生徒の脳内には対話が「整理」され、強く「記憶」に残っている。つまり、論理的思考力が働き、エピソード記憶として脳内に刻みつけられていくという状況が生まれているのではないか?
目の見えない教員に協力を仰いで、いったい「文字という視覚情報」ではない方法で、言葉をどのようにイメージ化しているのかくわしく聞いてみてほしい。
これをすることによって、目の見えない方々の思考方法が明らかになり、今後の盲教育に大きな影響を与えるのではないか。そんなことを思いました。
あとのくわしい内容は・・・・・秘密!
コメント欄に質問して下さった方に返信する形で明らかにしようと思っています。
読んでいただきありがとうございます。
できましたら応援の1クリックをお願い致します。
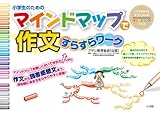 | マインドマップで作文すらすらワーク (ドラゼミ・ドラネットブックス) |
| クリエーター情報なし | |
| 小学館 |