
5月1日にNTVで放映された番組『天才じゃなくても夢をつかめる10の法則』を視聴しながらマインドマップにしてみました。この番組の内容は、私がこれまでの2年間、担任する子どもたちに対して行なってきたことがたくさん含まれていました。そのため、番組を見ながら「自分の取り組みは間違っていなかった」ということが裏付けられたという気持ちになりました。
マップを文章化しておきます。
①幼児はきちんと叱る
幼児期には、子どもが悪いことをした時に、分かりやすく、短く、ビシッと叱ることが必要である。それによって前帯状皮質が鍛えられ、社会協調性が身についていく。自分の心の痛みや他者の痛みを理解できるようになるので、思いやりのある子に育つ可能性が高くなる。注意しなくてはならないのは、ネチネチ叱ったり、過度に叱りすぎたりしないこと。叱りすぎると子どもは自信を失い、何もしない子になってしまうかもしれない。
反対に、幼児期にまったく叱らないで育てると、叱って育てた子に比べて、攻撃性が100倍増加するというデータもある。失敗を反省して次に活かす習慣がなく、自己中心的な精神構造になってしまう危険性が高い。
②夢を育む
子どもには将来の夢を持たせることが最も重要である。夢を持つということは「頭が良くなる」ことに直接つながる。夢とは「将来のビジョン」といういことであり、これは大人でも同じであるが、「ビジョン」を持っている人間は自分のするべきことが分かっている。そして、自分の脳裏に見えている夢を実現するためには、自然と「計画性」が求められてくる。このことによって、効果的な学習を自らすることができるようになる。
さらに必要なことは、自分の夢を人に語ることである。これは「アファメーション」と言って、肯定的な自己宣言である。夢を語るという「アファメーション」をかけることによって、私たちの脳は自分自身の力によって洗脳され、活性化していく。そして脳は、夢の実現に向かって、自分自身をコントロールするようにできている。
成功した多くの有名人が、小学校の卒業文集に「夢」を書き残しているのは、自分自身の将来に対して「アファメーション」をかけていることになる。
③ほめる
子どもが何か行動を起こした瞬間に、絶妙のタイミングで「ほめる」ことが大事だ。ほめられた瞬間、子どもの脳内には「ドーパミン」という報酬物質が放出され、達成感ややる気に包まれる。そして「この快感をもう一度味わいたい」という欲求が生まれる。これを「強化学習」という。
「ほめる」ということの効果は、子どもの年代によって違う。7歳までは親からほめられることが一番で、上手にほめる親の力によって子どもが伸びる。8歳からは親ではなく、他人からほめられることが必要になる。社会的な存在としての芽を伸ばしつつある時期の子どもに必要なのは、加護するようなほめ方ではなく、その子の存在を「承認」されるようなほめられ方が一番良いと井上は思う。
④10000時間の法則
どんな世界のことでも通じる法則がある。
「10000時間の法則」という。
好きなことを10000時間続けていくことができれば、どんな人でも一流になるということ。10000時間=3時間×365日×9年間。スポーツで高校を卒業する時点で一流選手になりたいと思っている子は、小学校4年生の時から毎日3時間の練習を1日も欠かさずに続けることができれば、能力に関係なく一流になれるという法則。
勉強も同じですね。たいがいの受験生は小学校4年生頃に本格的な受験体制に入ります。それを高校卒業まで続ければ、あらゆる道が開けるわけですね。
⑤おねしょする子は大器晩成型かも
おねしょをする子は、「前頭前野」の発達がゆっくりしていることが多く、統計的に見ると将来「前頭前野」が大きく育つことが考えられる。前頭前野は創造性を司る部位だけに、将来は大物に変身する可能性が大きいと考えられる。おねしょはいつかは止まるのだから、周りの大人はあまり焦ることなく、おおらかに見守ってあげることが大事である。
⑥出会いを求める
幕末の志士・坂本龍馬は、土佐藩を脱藩し、日本各地の多くの人と出会うことで、自分の目を開き、日本の進路に大きな影響を与える力を伸ばした。人との出会いは自分の視野を広げる働きがある。
小中学校時代に「オール1」という成績を取っていた宮本延春氏も、人との出会いによって劇的に人生を変えた一人である。(宮本先生に興味のある方は著書をお読みください。)
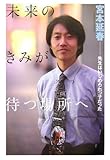 | 未来のきみが待つ場所へ 先生はいじめられっ子だった 宮本 延春 講談社 このアイテムの詳細を見る |
 | オール1の落ちこぼれ、教師になる 宮本 延春 角川書店 このアイテムの詳細を見る |
⑦正しい失敗観
エジソンは母親が失敗を叱らないで育てた。教師がさじを投げるようなエジソンの素朴な疑問に対して、真摯に答え続けた。
人間の最大の欠陥は、「あきらめること」と「やめること」である。一度や二度の失敗でめげてしまい、自分勝手に未来の失敗を予想して「あきらめて」しまう。失敗という価値観を転換する必要がある。失敗とは将来への道しるべである。今行こうとしているその道は「違うよ」と教えてくれる道標である。失敗したら別の方法でアプローチすれば良いのである。
失敗を反省し、失敗から学び、次へと活かしていくことで人類は発展してきたのだから。
⑧感情豊かに
漫画家・手塚治虫氏は、少年時代に母親から「マンガの読み聞かせ」をしてもらっていた。その読み方はマンガのセリフを感情豊かに臨場感あふれる読み方で、手塚氏の想像力を客気する効果があった。これによって手塚は、ワクワク、ドキドキする母親の読み聞かせに夢中になり、将来漫画家になる素養を育んでいった。
⑨母子関係
母子関係が密接で密度が濃いほど子どもは伸びる。これは子どもと接する時間が長いとか、短いという問題ではない。接する時間が長くても母子関係が薄い(放任主義や全面的な自主性のみ尊重など)場合は密接とは言えない。スキンシップを重んじ、短い時間であっても濃厚な親子関係を持とうとする人の子どもは脳を発達させる。
⑩親バカで良い!
母親は子どもとのふれあいを深めていく過程で、脳内に「プロラクチン」という母性促進物質が放出されていく。たとえば母乳を与えていると、約10分くらいで「プロラクチン」の法出がピークを迎えるらしい。
この「母性」によって、子どもは大きく才能の芽を育んでいく。
**************
私が把握した10の法則は、番組が意図した10の法則とはちょっと違っていたようです。
(参照『天才じゃなくても夢をつかめる10の法則』公式サイト)
しかし、それも良しとしたいのです。
要するに、正確に情報をつかむことよりも、自分に役に立つ情報を得ることができれば良いのですから。役に立たない情報を知っているよりも、実際の生活に役立つ情報を得ることが、新学習指導要領で示された「生きる力」であり、「思考力」「判断力」であると思うからです。