井上の場合、卒業式にも受け身で参加するような児童を育てたくはありません。卒業生も在校生も主体者として参加し、小学校の最後の授業を最高の授業に創り上げることを指導のゴールイメージとして持っています。
主体的に練習をしていくためには自分自身の姿をメタ認知することが必要になります。自分の練習態度や声、心の中の姿勢はどうなのかを客観的に見られるようにさせ、自分を振り返らせることで、「自分自身の卒業式」を創り上げることができる。目の前にいるその子が、「その子の卒業式」を創り上げるかどうかを見ていかなくてはなりません。
簡単なようで難しい指導です。
いったん全児童の前に立ったからには、そこにいる卒業生・在校生すべての児童の心を把握する努力はしています。表情・姿勢・目線・そぶり・口の動き・指先・足先・服装など、あらゆる角度から練習に向けての心意気を読み取る努力をしています。
毎回の練習の最後にはABCで自己評価をさせています。学習の「ふりかえり」というものです。
多くの児童は自分自身を冷静に振り返り、AかBの評価をします。そして、これを次の練習に活かせるように、意識をつないでいきます。
課題があるのはCの評価で手をあげる児童です。
なぜ課題があるのかというと、その理由が2つに分けられます。
1つは良い方の理由です。
練習の中で、自分自身に納得できずにC評価をしている児童はそれで問題ない。万が一、教師から見て「過小評価ではないのか?」と思えるような、厳しい自己評価をしているならば、「君はそんなことはないよ。すごく一生懸命練習していたよ。」「自分に厳しいんだね。すごく良いことだね。」と励ませます。
2つ目が良くない。
たま~にですが、わざとC評価に手をあげる児童がいます。
こういう児童の場合、練習に参加すること自体に「心の壁」を作っている場合が多い。ふざけて低い評価に手をあげているのが目に見えるわけです。
ここに実にネガティブな「生き方」を感じるのです。自分自身を見つめることのできない能力の低さを感じる。わざとCにあげる態度を続けていけば、確実にセルフイメージを下げてしまいます。それだけでなく、周りに人たちに嫌なイメージを持たれてしまい、知らず知らずのうちに、自分自身の人生に重大なマイナス影響を与えてしまいます。
こういう児童こそ、自分自身の過ちに「気づき」を起こさせ、向上の方向へ誘導してあげなくてはなりません。それが教師の役目です。
ただただ全体指導をして形だけ作れば良いのであれば卒業式なんて簡単にできます。しかしそんな指導をしても面白くも何ともありません。貴重な時間を使って練習するからには、一歩でも成長の方向に歩みを進めたいと思うわけです。
訳の分からない文章を書いた感じがしますが、ちょっとしたつぶやきだと思って下さいませ。
下記バナーへの皆さんのワンクリックで、教育界へのマインドマップ普及、小学生バレーボールの普及にお力添えをお願いします。
【おすすめの本】
 | できる子はノートがちがう!―親子ではじめるマインドマップ 小学館 このアイテムの詳細を見る |
 | 小説 太平洋戦争〈1〉 (山岡荘八歴史文庫) 山岡 荘八 講談社 このアイテムの詳細を見る |
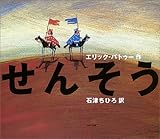 | せんそう エリック バトゥー ほるぷ出版 このアイテムの詳細を見る |
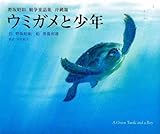 | ウミガメと少年 野坂昭如 戦争童話集 沖縄篇 野坂 昭如 徳間書店 このアイテムの詳細を見る |
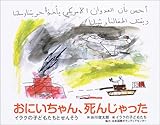 | おにいちゃん、死んじゃった 谷川 俊太郎 教育画劇 このアイテムの詳細を見る |
 | あの日を、わたしは忘れない (ヒロシマ原爆の絵日記) (ヒロシマ原爆の絵日記) 河野きよみ 勉誠出版 このアイテムの詳細を見る |
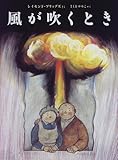 | 風が吹くとき レイモンド ブリッグズ あすなろ書房 このアイテムの詳細を見る |
 | 一つの花 (おはなし名作絵本 21) 今西 祐行 ポプラ社 このアイテムの詳細を見る |