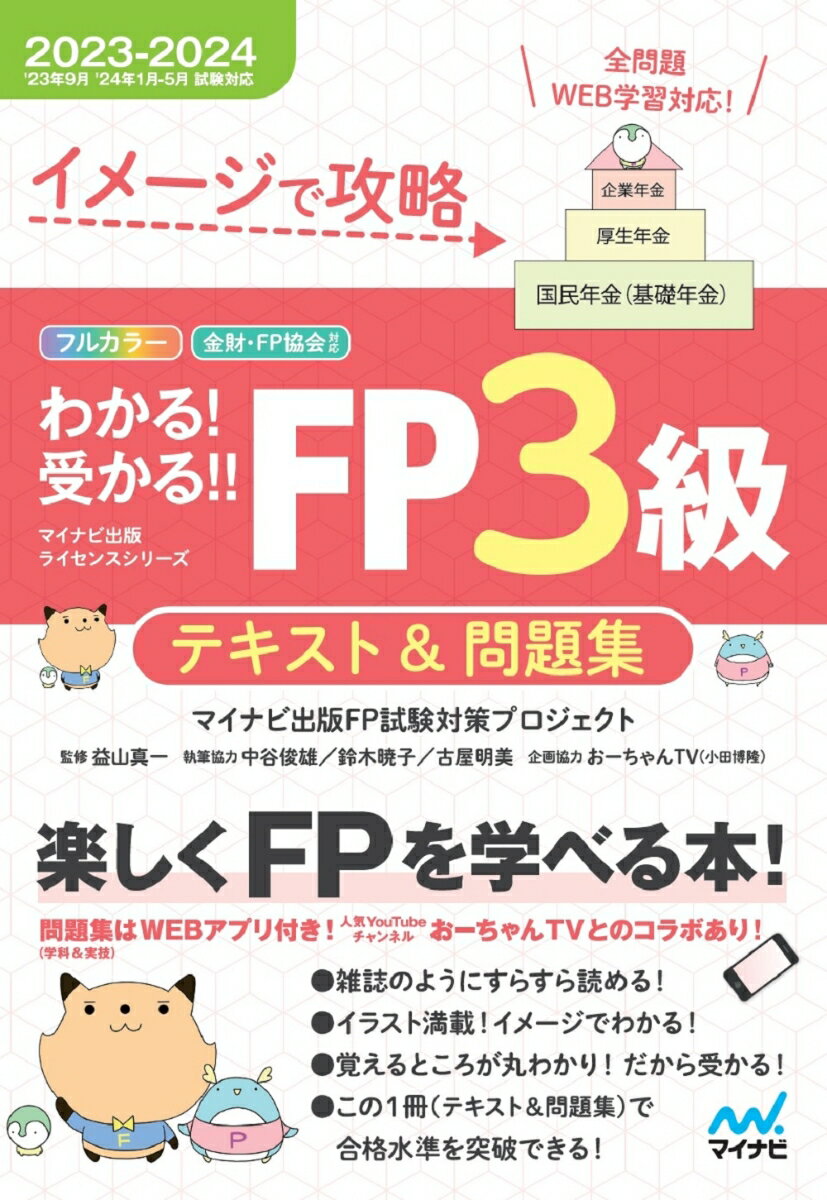ここはFPの勉強の最初の躓きポイントだと思う。私もそうだった。数年前に挑戦した時は、数字がズラ~っと並んだ表を見て「???」てなって挫折した。今回は、YouTubeを見たり何度もテキストを読んだりして何とか理解した…と思う。
これ、最初の2つの終価係数と現価係数は、複利計算ができる人なら電卓でいけるから表は不要だと思う。あれば便利というだけで。でも、他は電卓だとなかなか大変そうなので、表が必要になる。しかし、その便利な表を使いこなすためには知識が必要だから学んでおきましょう…という項目なんだと理解してる。その辺の説明がテキストやYouTubeにはなかなかないので、ド素人には難しかったりする。
テキストには5年後の例が載ってるので、以下5年後の場合で、私が理解したことを説明。
(1)終価係数…○円の元本を年利率○%で複利運用したら5年後いくらになるか?→複利計算のし方を覚えていれば表は不要。選択肢から選ぶ場合は、1より少し大きい数字を選ぶ。数%で数年運用した結果は、元本が少し増えるだけだから。
(2)現価係数…5年後に○円にしたい場合、年利率○%で運用すると、今いくらあれば良いか?→選択肢から選ぶ場合は、1より少し小さい数字を選ぶ。元本は目標金額より少し小さい額だから。
ここまではそれほど問題ないと思う。ややこしいのはここから。
(3)年金終価係数…年利率○%の複利運用で毎年○円を5年間積み立てると、5年後の合計はいくらになるか?→5より少し大きい数字を選ぶ。運用せずにただ積み立てるだけなら、5年後には単純に5倍になる。年利率数%で運用するなら、それより少し大きい数字をかけることになるから。
(4)減債基金係数…5年後に○円を貯めるために、年利率○%で複利運用するとして毎年いくら積み立てればよいか?→0.2より少し小さい数字を選ぶ。運用せずにただ積み立てるだけなら、毎年積み立てる額は目標金額の1/5、つまり0.2。運用して増やしながら積み立てるなら、0.2より少なくてすむから。
(5)資本回収係数…○円を年利率○%で運用しながら5年間で均等に取り崩した場合、毎年いくら受け取れるか?→初めて読んだ時は、そもそも「均等に取り崩す」から「ん?」てなった。要するに同額ずつ使っていくということね。そこからだからド素人は本当に大変。解き方としては、0.2より少し大きい数字を選ぶ。運用せずにただ取り崩すだけなら、毎年受け取る額は1/5、つまり0.2。運用しながらなら、それより少し増えるから。
(6)年金現価係数…年利率○%で複利運用し、毎年○円の年金を5年間受け取るためには元本がいくらあればよいか?→5より少し小さい数字を選ぶ。運用しない場合、元本は毎年受け取る額の5倍必要。運用するならそれより少なくてすむから。
こんな感じで理解した。これは5年の場合なので、年数が違う場合は(3)~(6)はこのままでは使えないけど、基本的な考え方は同じだと思う。例えば、4年後なら、(3)と(6)は4を基準に考えて、(4)と(5)は1/4、0.25を基準にするという感じ。
数字が選択肢で与えられている場合は、それぞれの係数の名前を覚えていなくても、上の方法で何とか解けると思うんだけど、係数の名前自体を選ばせる問題もあるんだよね。
(1)終価係数⇔(2)現価係数
(3)年金終価係数⇔(4)減債基金係数
(5)資本回収係数⇔(6)年金現価係数
のようにペアが3組というところまではわかると思うんだけど、「年金」と付くものがペアになってないという不親切設計。それぞれの係数の名前と意味は覚えているが、どれがどの位置なのか、どれとどれがペアなのかが曖昧…という状態と仮定して、どう覚えたらいいかを考える。
まず、(1)(3)(5)の奇数(左側)は「し」、(2)(4)(6)の偶数(右側)は「げ」が入っていることを確認。そして、(1)終価係数と(2)現価係数はさすがに覚えられると思うのでここを基本にする。さらに、(3)年金終価係数(毎年一定額積み立てたらいくらになるか)までを頑張って覚える。すると、「年金」はペアになっていないので(6)が年金現価係数であることがわかる。残った2つを「し」と「げ」で左右に分ける…みたいな感じ。この位置関係を画像として目に焼き付けてしまうのがラクではないかと思う。
自分としてはここが序盤の峠だったので、ここを超えたら少し楽になった気がする。何とか乗り越えよう。
↓使っていたテキスト↓
(追記)上記の内容をもっと分かりやすく解説してる方がいた!
(追記)
ほんださんの言うように、過去問を見ると、係数の名前を問う問題は出る確率が低い。でも!私が2級を受けた時には1問出たんだよね…。ここで落としたら悔しいと思って、一生懸命思い出した。合ってた。良かった。