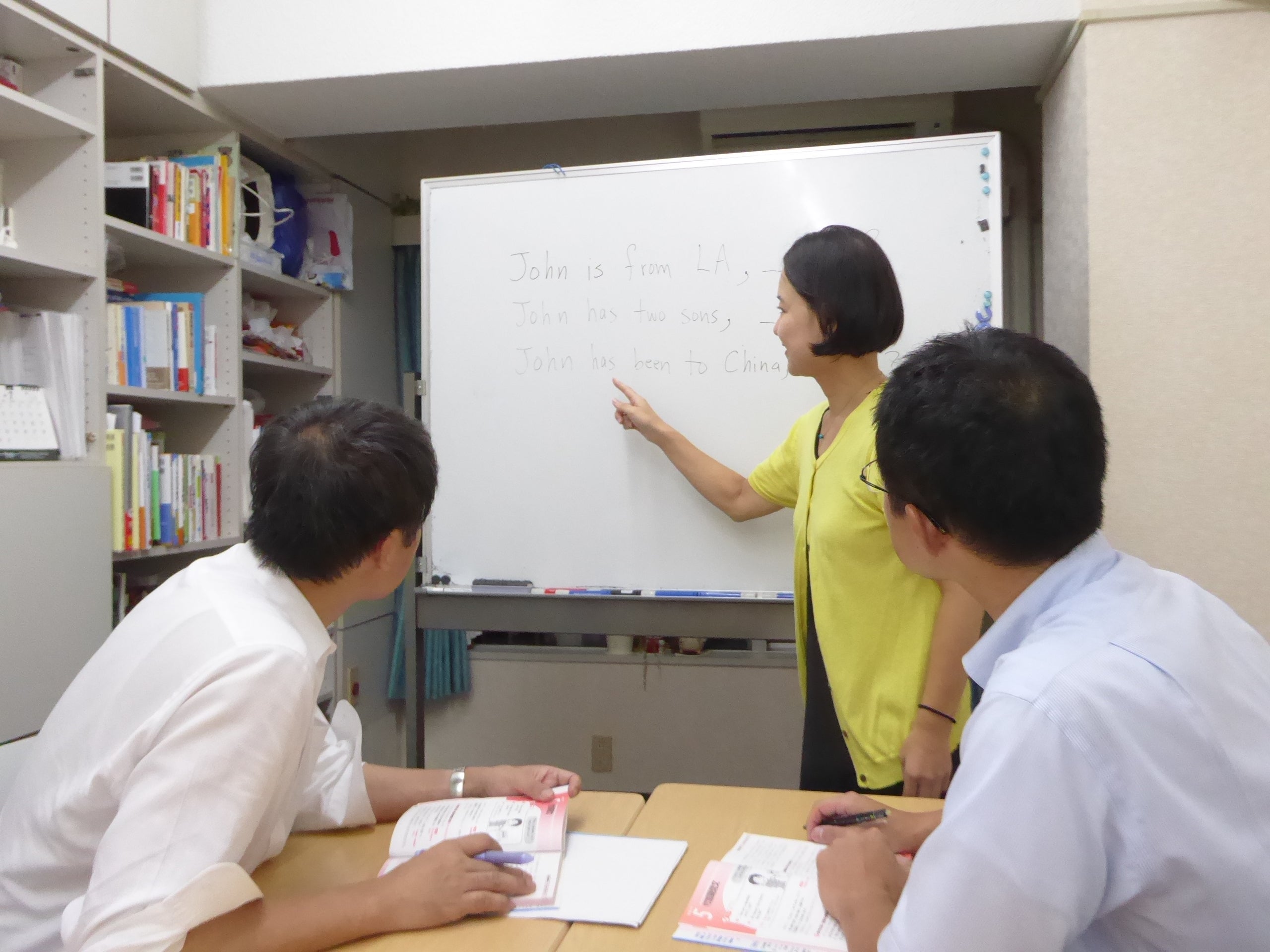Hello everyone!
ワールドカップ、盛り上がっているようですね。
時差もあり、今回は(も?)ニュースやネットで目にする程度ですが、トップ選手が全力でプレーすると奇跡的な瞬間が訪れるものですね。海外選手の超人的なプレーが毎日見られるのも醍醐味の一つです。
私の子供時代はサッカーはまだまだメジャーなスポーツではなく、通った中学校にも部活がありませんでした。地元にあるのも少年野球チームばかりで、もし学校にサッカー部があったとしても完全に野球部に追いやられていたと思います。
Jリーグ発足から30年ほどの年月を経て、W杯ともなれば野球人気をしのぐほどのメジャースポーツになりましたが、まずは先人のたゆまぬ努力に杯を捧げたいと思います。はい。
さて、その奇跡的な瞬間の一つ、「1ミリの奇跡」と呼ばれるシーンについてのCNNの記事を読んでいたら、
"typo?!"
と思った箇所がありました。
ちなみに"typo(発音はタイポゥ)"とは"typographical error"の略で「誤植;タイプミス;打ち間違え;スペルミス」の意味です。
こちらがその箇所です:
"However, after a video assistant referee (VAR) review, the goal was allowed to stand and Japan held on for an historic victory."
冠詞の"an"は母音(a,e,i,o,u)の前に置かれますが、これはスペルが母音ということではなく、発音が母音の時です。
例:
an umbrella
a university
a horse
an hour
an honest person
"h"は発音されないこともあり、その場合は"an hour"や"an heir"のようになりますが、"historic"は明らかに"h"の音を発音しています。なのに、どうして"an"と書いてあるのか不思議で、記事を目にした翌日にもう一度確認したところ、訂正はなく"an"のままでした。
そこで調べてみたところ、昔は"historic"や"historical"の前に"a"はほぼ見られず、1940年くらいまでは"an historic~"のほうが優勢だったそうです。昔教育を受けた人や、それらの人達に言語的影響を受けてきた人は、今でも時々"an"を使うことがあるようです。
フランスのブランド"HERMES"(エルメス)が良い例ですが、"h"を発音しないフランス語の影響もあったのではないかとする説もありました。フランス語だけはでなく、ラテン語から派生しているスペイン語やイタリア語も基本的に"h"を発音しないので、"h"を無音とする影響を受けていたとする説にもうなずけます。
こちらから記事全文が読めます。
とても読みやすく、教材としても使えるポイントがいくつもあります:
最後に以下の"that"が3つ登場する文ですが、それぞれの"that"が果たしている役割は何でしょうか?
答えは、、、
明日以降に発表するかもしれません![]()
“There are 80 million Germans right now going mad, waiting for a picture that shows that that ball didn’t go out of play,” said former Scotland international Graeme Souness, speaking as a pundit on ITV.
それでは今日も早く寝ます。
なぜなら、、、
↓↓↓