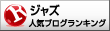参考文献 〜 「孤独を怖れない力」(工藤公康)
目次
はじめに——孤独に「自分と闘える」人の強さ
もう一歩先の自分を手に入れる
第1章 孤独を怖れないカ
1 自分を「変える」ために必要なこと
自分を成長させるプライド ダメにするプライド
変化を怖れなくなる ある一つの考え方
2 折れそうになったときの心の支え方
意外と理にかなっている「三日坊主」練習法
「工藤は終わった...」と言われてから20年も活躍できた秘密
3 一流選手ほど、この「基本」を大切にする
常勝・西武が「キャッチボール」をおろそかにしなかった理由
「頭で」理解しようとするから大事な場面でうまくいかない
4 「誰も理解してくれない...」からこそ、あえてやる
結果は「出す」ことが重要なのではない
「理解ある」ベテラン選手に存在価値はない
5 自分の「伸びしろ」は孤独の中に隠れている
「プラス思考」な選手ほど失敗を繰り返すワケ
上原投手の「問い」に表れた一流と二流の差
ここ一番で動じない
第2章 メンタルの力
1 「この人はメンタルが強い」と感じた意外な選手
迷う僕の背中を押してくれた野茂投手の言葉
球の速くない投手が「直球勝負」できる理由
2 「わがまま」で自滅する人、「マイペース」で結果を出す人
「マイペース」と「わがまま」の決定的な違い
それは「姿勢」に如実に表れる
3 相手との心理戦に勝つ、たった1つのコツ
心理の揺れはこの些細なしぐさに表れる
僕が試合前に必ず個室にこもってしていたこと
4 ここ一番! に強い人たちに共通する習慣
集中力は「上げよう」とするからうまくいかない
いざというときに120%の集中力を発揮できる人の準備力
5 ミスを引きずらない、感情スイッチの切り替え方
「ブレない心」を作る第一歩は「自分の役割」を見出すこと
100%の自分を引き出す
第3章 成長する力
1 自分を成長させる最大の武器は、この「思考」
「やる練習」がもたらした目に見える効果
自分の武器を手に入れるカギは「一年後の自分」
2 目標には「立て方」がある
チームの勝利のためには自分を抑えるべきか
チームも個人もともに成長する計画の立て方
その失敗からは真の成長はつかめない
3 「残り3%」の能力を引き出す法
成績がV字回復した2つの取り組み
自分の能力をフルに出し切る考え方
4 自分の「見せ方」をわかっている人の強さ
自分を解放させられる唯一の瞬間
自分の「見せ方」を使い分けよ
学び、備え、切り替える...
第4章 闘い抜く力
1 データを活かし切る自分の「勘」の磨き方
自分の勝ちパターンが通用しなくなったとき
最高のパフォーマンスを生む「データと勘」の活かし方
2 無駄な時間が「自己投資の時間」に変わる、頭の習慣
自分を高めるヒントはこんな意外なところに...
自己投資を習慣化させるコツ
野球にもゴルフにも共通する結果を出す頭の使い方
3 自分を「休ませ上手」にする方法
自分をもっとも高められるちょうどいい、休みの取り方
時には、とことんダラダラしたほうがいい
4 一流選手たちに共通する「学び方」
この「違い」に気づける人は強い
一流選手ほど「謙虚」な理由
結果が出ないときの
第5章 「自分」を乗り越える力
1 結果が出ないときのしのぎ方
不摂生だった自分を奮い立たせた妻のひと言
目先の結果より調子のバロメーターになるものとは?
2 「衰え」から、新たな自分の可能性を引き出す法
「自分の常識」の先に可能性を広げるヒントがある
40代になって野球を好きになれた理由
3 学ぶべき失敗、学ばなくていい失敗
ケガをしても再び活躍できる人、故障を繰り返す人。その違いは...
学ばなくてもいい失敗とは?
4 僕はこうして「苦手」を克服してきた
どうしても苦手意識を克服できない相手には...
苦手意識を必要以上に膨らませないコツ
5 他人のいいところを「盗む」とは
「マネできないもの」にこそ学びがある
「マネ」が「オリジナル」に変わる瞬間
6 どこへ行っても「結果」を出せる人の共通点
チームに馴れ合わないための思考法
「個」を成長させる
第6章 チームの力
1 負け癖がついたチームの意識をどう変えるか
「嫌われ役」が報われるとき
一流になれるかどうかは「結果」が出始めてからがカギ
2 「周囲に理解されない」と感じたときに
「今、ここにいる意味」が見えているか
周囲に理解してもらう前に必要なこととは?
3 若手を伸ばす「教え方」
若い選手たちに一番気づいてほしいこと
おわりに——孤独な闘いを支えてくれるもの
↓ぜひ応援よろしくお願いします↓