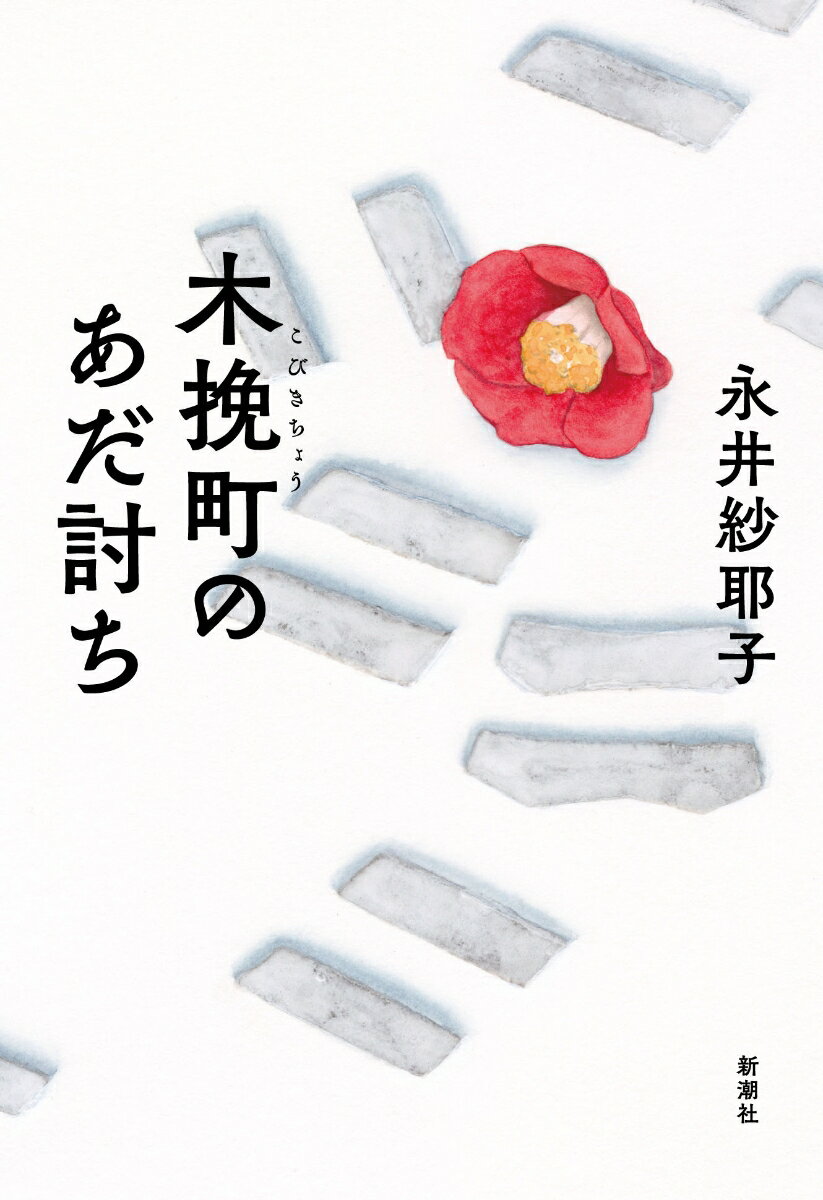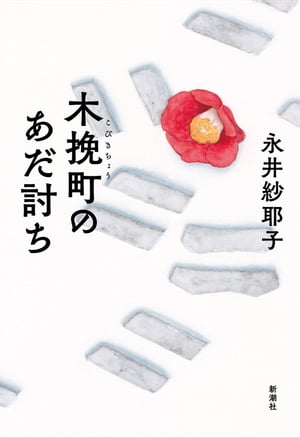ミステリ小説としても、人情噺としても面白い永井紗耶子さんの『木挽町のあだ討ち』を読了しました。
直木賞・山本周五郎賞のW受賞も当然と思える面白さでしたよ。
まだ前髪も取れていない少年 菊之助が、衆人環視の中、親の仇討ちをした「木挽町の仇討ち」。
仇討ちの舞台となったのが芝居小屋の裏だったため、芝居小屋で働く者はもちろん、通りがかりの人たちもこの仇討ちを目撃することとなった。
「曽我兄弟」など、芝居で見ることはあっても、実際の仇討ちを見るなど滅多にあるものではない。
目撃した者は皆大いに興奮し、少年の健気さに共感した。そしてこの仇討ちは瓦版にも書かれ、長く人々の口の端に登ったものだった。
それから2年。木挽町に仇討ちの詳細を知りたいと言う若者が現れた。
仇討ちまでの短い間、菊之助の世話をした芝居小屋仲間たちがその時のことを語り始める……。
(永井紗耶子さん『木挽町のあだ討ち』の概要を私なりにご紹介しました。)
子どもの頃から時代劇を見ていて、なんとなく知っていた「仇討ち赦免状」。
人を殺めることは許されることではありませんが、正式に認められて仇を討つために発行される書類です。
ただ、もう一歩踏み込んで、実際に仇討ちをすることがどれほど過酷かということを、この小説によって教えてもらいました。
まず、逃げている相手(仇)を追跡することが難しい。
江戸時代には防犯カメラの映像はありません。SNSの目撃情報もないのです。雲を掴むような話ではありませんか。
そして仇を見つけたならば、絶対に仕損じてはなりません。きちんと敵討ちを果たすまでは故郷に帰れないのが仇討ちのルールなのですって。
元服前ということは、菊之助は15歳くらいでしょうか?もしかしたら人生の大半を棒に振ることになるかもしれない仇討ちに出かけさせるのは、かなり酷な気がします。
しばらく読んでいると、この仇討ちには深い事情があることがわかってきます。
読者は、仇討ちから2年後に事情を聞きにきた若侍の立場と同化してその事情を知ることになります。
この小説は6つの章からなっており、それぞれが誰かの語りで構成されています。
目次を引用してそれぞれの語り部をご紹介しましょう。
第一幕 芝居茶屋の場
木戸芸者 一八
第二幕 稽古場の場
立師 与三郎
第三幕 衣装部屋の場
女形・衣装の繕い担当 芳澤ほたる
第四幕 長屋の場
小道具製作 久蔵の内儀 お与根
第五幕 枡席の場
戯作者 金治
終幕
まず、芝居小屋で生きる人の話だけに、通常の小説のような「章」ではなく「第一幕」「第二幕」と表記しているのがしゃれているなぁと感じました。
当時、幕府は芝居小屋を「悪所」と呼んでいました。芝居などは下賎のもののすることだと。
だからでしょうか、芝居小屋には色々な事情を抱えた人たちが集まってきていました。
食い詰めて親にも死なれ行き先のなくなった者や、侍の道を外れてしまった人たちが。
そんな苦労人たちは、親の仇を探している菊之助を放っておくことができません。
なんとか親の仇を討たせてやりたいと応援する一方、もし仇を討てず国に帰ることができなくなったら、自分たちと一緒に芝居小屋で生きていけばいいではないかとも思っています。
つまり、親身になっているのです。どっちに転んでもなんとかしてやりたいものだと。
それぞれが抱えている事情と、菊之助への思いにジーンとします。
私は特に、第四幕長屋の場のお与根さんの語りに思わず涙しました。
無口な職人である久蔵とお与根さんの間に授かった一粒種の坊をなくした事情を語るところがたまらなくて。
この辺り、仇討ちものの時代劇と、人情噺の両方の魅力があります。
そして、芝居好き、歌舞伎好きにはたまらないことに、この小説には歌舞伎役者や演目名がいっぱい登場します。
例えばお名前では、岩井半四郎さんや、坂東玉三郎さんの芸の上のお父様 守田勘弥さんに通じるであろう森田勘彌さん。
『天竺徳兵衛』『娘道成寺』『本朝廿四孝』『金閣寺』『鎌倉三代記』『菅原伝授手習鑑』など、場面や衣装が目にうかぶ演目も満載。ワクワクしてしまいます。
舞台は絵空事、だけど、演じる役者やそれを支える裏方の人たちは真剣です。
幕府が芝居小屋を「悪所」と呼んだのはきっと、幅広い人に愛される「芝居」の人気を恐れ、必要以上に悪いものである、卑しいものであると位置付けたのだと思います。
どのように呼ばれようと、芝居に生きる人たちの心意気、今でいうプロ意識には惚れ惚れします。
それは今の時代にも通じることだと思います。
ところで、この本の帯には、こんな言葉が書かれています。
このあだ討ちの「真実」を、見破れますか?
実はこの小説は一種のミステリでもあるのです。
私は、ある演目のタイトルを見た瞬間、「ああ、その手を使うんだな」と、おおまかな「真実」は見破れました。
でも、それがわかった後も最後まで面白く読むことができました。
そしてしみじみ思ったのです。
ここまで「芝居」にこだわった小説は読んだことがない、と。
同時に、梅沢富美男さんじゃないですが、木挽町の芝居小屋に生きる人たちはもちろん、誰の人生も「夢芝居」なのかもしれないと思ったのでした。
声の書評@stand.fm
アプリstand.fmでは声の書評をお送りしています。
このブログとは違う切り口でお話しするようにしています。
よろしければお聞きください。
↓
stand.fm「パーソナリティ千波留の読書ダイアリー」
ブログランキングに挑戦中
もし記事を気に入っていただけたなら、
ポチッとクリックよろしくお願いします。
↓