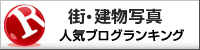昨日は天候も晴れたり曇ったりでしたので、信貴山城と水仙
の花を見に行きました。松永屋敷跡の虎口では、足場が滑り
易いため、転倒しかけました。右手で体を支えたので右腕が
まだ少し痛いです。石山本願寺攻めの際に、謀反を起こした
松永久秀の討伐で、細川藤孝も松永を攻めています。また、
後日UPします。
昨日の続きです。
細川藤孝の嫡男忠興ですが、明智光秀の娘お玉(細川ガラシ
ャ)と勝竜寺城で盛大な結婚式を挙げ、2年ほどですが、この
勝龍寺城で新婚時代を過ごしました。織田信長の許可と指示
による結婚でした。
光秀の娘玉が小畑川の道を通り輿入れした時の想像図です。
小畑川沿いの大門橋(大手門)にあるガラシャ通りです。(看板が見えます)
細川藤孝が整備した勝龍寺城です
ガラシャの解説板です。
2人の拡大図です。(これはゲームからのイラストと思います)
長岡京市は勝龍寺城公園の出来た、市民からの提案で、
平成4年度から「ガラシャ祭」というイベントをやっています。
その2011年の動画をお借りしました。
ユーチュブ動画で3分です。
ガラシャ祭です。
2年後の1580年に、父藤孝は功により丹後南半国の
領主となります。(北半国は一色満信の領国)、それで
丹後の宮津城に移りました。
その2年後1582年(信長イチゴパンツと昔覚えました)、
本能寺の変が起こります。父藤孝は剃髪して弔意をあら
わし、父子ともに明智に味方せず、ガラシャ夫人を幽閉
します。忠興はこのとき、父が剃髪隠居したので領国で
ある丹後南半国を譲られ、丹後宮津城主となります。
忠興は秀吉の家臣となり、一色満信は山崎の戦いでは
光秀側に付いていたため、秀吉の指示で忠興は北丹後
の一色満信を殺した後一色家旧臣を攻め滅ぼし、秀吉
から丹後一国の支配を許されます。北丹後攻略戦では、
同じ足利一門である一色氏を騙し討ちにした末、敗残兵
を皆殺しにするなどしたため、北丹後の一色義定に嫁い
でいた忠興の妹の伊也はそのことを恨み、戦後に兄に
斬りかかり鼻に傷跡を残しました。なので、忠興の見難い
顔について、周りの者は何も言いませんでした。
天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いに参加した
功により、天正13年には従四位下・侍従に叙任し、秀吉
から羽柴姓を与えられます。関ケ原の戦いでは大坂城内
の玉造の細川屋敷にいた、妻のお玉(ガラシャ)は西軍
の襲撃を受け、人質となることを拒んで自害を余儀なくさ
れます。護衛であったはずの稲富祐直は、包囲部隊に
弟子が多数居た為逃げるように懇願され、ガラシャを置
き去りにして逃亡しました。徳川家康から「味方につけば
但馬一国(10万石)を進ぜよう」という誘いで、徳川家康
の味方をします。但馬一国の加増は実行しなかったもの
の、慶長5年(1600年)の論功行賞で丹後12万石から、
豊前国中津39万9千石の大名となります。2年後に小倉
城を築城して移りました。大坂夏の陣にも参加し、松平姓
を与えられますが辞退して、長岡姓から細川姓に復しま
した。1632年に豊前小倉40万石から肥後熊本54万石
の領主として加増・移封されました。以上から忠興は父の
藤孝以上に、運のよい世渡りの上手な武将でした。
今日は本丸北側の土塁からです。
下図③の所です。ここから④の隅櫓に行きます。
本丸と沼田丸の想像縄張り図です。
③と④の中央に出入口があります。
この冠木門と通路は想像縄張り図にはありません。
北虎口の発見が遅れたので、ここに北門を造ったのだと思います。
勝竜寺城の縄張り図です。(下が北)
本丸北側の土塁をさらに歩くと
④の隅櫓が見えます。
瓦の家紋が細川氏の九曜紋と、本家足利氏の二つ引両紋です。
細川氏は、清和源氏足利氏の分れで室町幕府の管領を務めた細川氏
の一族です。もともと細川氏は足利陸奥判官 義康の四代目の孫にあた
る義季が、鎌倉時代の中ごろ三河国額田郡細川郷(現在の愛知県岡崎
市北方)に住んで 、細川氏を名乗ったことに始まります。南北両朝対立
の動乱期において、細川氏一族は足利尊氏に属して活躍、 室町幕府の
成立に尽力します。一連の戦功によって、一族は讃岐・阿波・河内・和泉
諸国の守護職に任じられます。 やがて、将軍義詮の遺命を受けた細川
頼之が管領となって、三代将軍義満を補佐して、室町幕府体制の確立し
ました。応仁の乱では、管領細川勝元が東軍の立役者となって西軍の
総帥山名宗全と対立します。その子政元は10代将軍義材(よしき)を 、
クーデタで倒して幕政を牛耳ったが、みずからが招いた細川家跡目をめ
ぐる家中争いによって横死します。以後、細川氏宗家は 泥沼の同族争
いを起こして歴史の荒波に呑まれて没落します。
近世大名として生き残った細川氏は頼之の弟で 和泉半国守護職に任
じられた頼有の裔で、細川藤孝(幽斎)・忠興父子の子孫です。江戸時
代は肥後五十四万石の大大名に出世しています。つまり細川氏として
は庶流でした。近年では当主が総理大臣にもなる大出世です。
肥後細川氏の「九曜紋」は、伝によれば、信長使用の小柄に付いてい
た九曜紋を見た忠興が自分の衣服に使用したいと 信長に願い出たと
ころ、しからば定紋にせよとの言葉をそえて与えられたのだといいます。
当時の忠興は長岡を称しており、 細川家代々の家紋に代わる新たな
紋として、主君信長の小柄の九曜を望んだと考えられます。
これが④の隅櫓です。中は休憩所になっています。
ここから南の方に行きます。
④から南の方を見たところです。
南枡形門と資料館が見えます。
次に休憩所兼資料館に行きました。
1階が休憩所で2階が資料館(無料)です。
山茶花の花が咲いていました。
休憩所兼資料館の間取り図です。
1階の休憩所です。いろいろな関連本資料とか
明智光秀をNHK大河になどのポスターがあります。
本丸内が見渡せます。
勝龍寺城のジオラマです。
神社の模型
勝龍寺城と山崎の合戦武将配置図です。光秀は勝龍寺城の
近くに陣を置きました。
2階に上る階段です。
2階は資料館ですが、残念ながら撮影禁止でした。
発掘の史料などが中心でした。説明版と重なる所も多々ありました。
外に出て本丸内の景色です。
今日はここまでにします。明日は沼田丸・神足屋敷など紹介です。
読者募集中ですので、読者登録お願いします。
希望があれば、相互登録します。相互アメンバーも募集中です。
どちらもチェックを外して「読者とわかるように」に設定して登録してください。
見てくれた人にはブログ村・ブログランキングを出来るだけ押しに行きます。
お手数ですが、お願いです。![]()
![]() ぽちっと
ぽちっと![]()
![]() 押すだけ
押すだけ