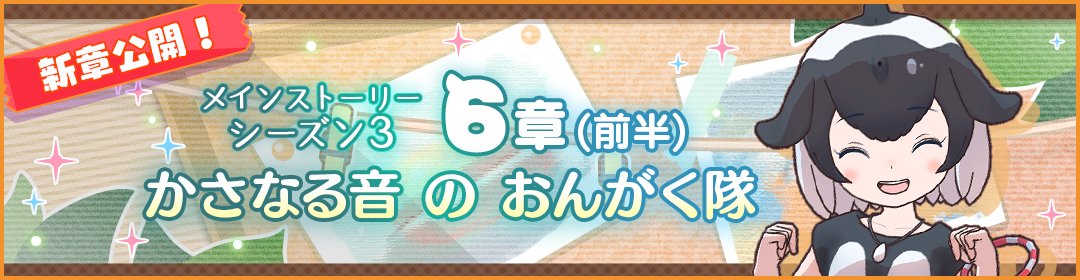お知らせ
〇<図形分類表>を追加しました!
各記事の<分類>の項目に<図形分類表>を追加しました。
この分類表は、各分類階層ごとに図形で表し、その階層に含まれるものを更に線でつないで大まかに表したものです。
この表で表しているのは、各動物園、水族館、自然科学博物館及び〈けものフレンズ図鑑>で採用されている<リンネ式分類階層>を元に作成しており、目は赤、科は緑、種は青、亜が付くものは橙で示しています。
一般的に表記されている分類は通常、綱、目、科、属、種という5階層で示していますが、そのうちの綱、上、下を含めると表が非常に複雑になり見にくくなる都合上、含めていません。
最近の記事を含め、過去の記事にも随時、完成でき次第入れていきますので、よろしくお願い致します。
〇現在、ともにジャパリパークを盛り上げる隊長仲間(フォロワー)を募集中です!
※条件
相互フォローとなっている方で、<けものフレンズ3>での隊長の名前と<申請しました!>という旨を、X<とりはね>のいずれかのポストのコメ欄、またはDMにて送信してください。
けものフレンズ
〇<けものフレンズ 10th ANNIVERSARY SHOP SPECIAL>が開催されます!
/
— マルイノアニメ (@marui_anime) August 8, 2025
けものフレンズ 10th ANNIVERSARY SHOP SPECIAL
新宿マルイメン開催決定✨
\
🗓️新宿マルイメン
📍2025年9月5日(金)~9月15日(月祝)
⚠️一部日時は事前予約入場となります⚠️
詳細▶https://t.co/YUowtegW0a pic.twitter.com/2YLoHHMtqH
〇メインストーリー シーズン3 6章 <かさなる音のおんがく隊>が公開されました!
〇新フレンズ<ライチョウ>が登場!
キジ目
<キジ(雉)>
キジ目の鳥たちは主に食用肉として得られるカモ類と同じ、<狩猟鳥(しゅりょうちょう)>として世界中の人々の食文化に深くかかわっていた歴史があり、色鮮やかな羽などの見た目の美しさから装飾品としてや芸術として使われたり、国鳥として指定されることもあります。
例として<シチメンチョウ>が産業動物として、現在も食肉として多く飼育されています。」
キジ目は<古口蓋類(ここうがいるい)【ダチョウ、レア、エミューなど】>のグループから分岐した<新口蓋類(しんこうがいるい)>にあたるグループの一つで、
この目には日本の国鳥である<雉(キジ)>や<ウズラ>、<ライチョウ>、<ホロホロチョウ>、<ツカツクリ>、<クジャク>、<ニワトリ>など多くの種類が属しています。
基本的にオスのほうが羽の見た目が派手で、メスは茶褐色など地味な色が多いのが特徴的です。
キジ目の中では特に<ライチョウ>の絶滅が危惧されており、現在環境省、自治体、大学、動物園が共同で保護活動にあたっています。
分類(なんのなかま?)
キジ(雉)
ライチョウ
ヤブツカツクリ
ホロホロチョウ
インドクジャク
ニワトリ(セキショクヤケイ)
キジ目(図形分類表)
キジ目には大まかに<キジ科>、<ツカツクリ科>、<ホウカンチョウ科>、<ホロホロチョウ科>、<ナンベイウズラ科>に分けることができます。
キジ目は鳥綱に含まれるグループの一つで、<新口蓋類(しんこうがいるい)>のキジカモ類に含められており、カモ目と姉妹群を構成しています。
この目ではさらに<キジ科>、<ホウカンチョウ科>、<ホロホロチョウ科>、<ナンベイウズラ科>、<ツカツクリ科>に分類されます。
キジ科には<キジ>、<クジャク>、<ホロホロチョウ>、<ライチョウ>、<コジュケイ>、<ウズラ>など、ツカツクリ科には<ヤブツカツクリ>、<クサムラツカツクリ>など、ホロホロチョウ科には<ホロホロチョウ>、ナンベイウズラ科には<ギアナウズラ>などの種が属しており、キジ科の種類が圧倒的に多いです。
しかし、この目ですが、どこまでをキジ科に含めるのかが、依然としてあいまいになっていて、ツカツクリ科とホウカンチョウ科以外を全てキジ科に含めるようにするべきか、シチメンチョウ科とライチョウ科を独立させるべきかが議論されています。
〇キジ科
キジ、ライチョウ、クジャク、ウズラ、コジュケイ、ヤマドリ、ムナグロシャコ、セイランなど
〇ホロホロチョウ科
ホロホロチョウ
〇ツカツクリ科
ヤブツカツクリ、セレベスツカツクリ、クサムラツカツクリなど。
〇ナンベイウズラ科
ギアナウズラなど。
生息地(どこにすんでいるの?)
キジ目は世界中に分布しています。
日本を含んだアジア、ユーラシア大陸、南北アメリカ、東南アジア、ヨーロッパ、アフリカに分布していますが、一つの種と言っても生息地がはっきりとしています。
例えば、ライチョウは日本を含んだ北半球にしか生息しませんが、ツカツクリ、ホウカンチョウなどは南半球にしか生息していません。
日本には固有種である<キジ>、<ヤマドリ>が存在し、他コジュケイ、コウライキジと呼ばれる種がいますが、放されたのが野生化したもので、元々は中国に分布しています。
ウズラは日本に生息するキジの中ではゆういつの渡り鳥で、夏に北部で繁殖し、冬に日本に南下し越冬する<冬鳥(ふゆどり)>ですが、野生個体を見られるのはごく稀です。
〇東アジア(日本、中国、台湾、朝鮮半島)
キジ(雉)、ヤマドリ、コウライキジ、コジュケイ、ウズラ
〇東南アジア(インドネシア)
セイラン、セレベスツカツクリなど。
〇南アジア(インド)
インドクジャク
〇北アメリカ
シチメンチョウ
〇中南アメリカ
ホウカンチョウなど
〇オーストラリア
ヤブツカツクリ、クサムラツカツクリなど。
〇アフリカ
シャコ類、ホロホロチョウなど。
形態(どんな見た目?)
オスは色鮮やかで派手な見た目をしていますが、メスは茶色で地味な色をしています。
地上凄で高く飛ぶのはあまり得意ではありません。
〇体系と羽毛
鳥類の中では丸くずんぐりしたような体型をしています。
短い嘴は地面の植物の種子や小型の昆虫などを草むらなどの間から器用につまめるように都合が良い形をしています。
翼が小さい為、あまり飛翔能力はなく、短距離を低空飛行するか、やや高台を登ったり時に使われます。
地上での活動が多いせいか、足はどちらかというと発達しているほうで、穴を掘ることに使われたりします。
オスとメスのクジャク
オスとメスのキジ
〇性的二形
キジ目の一部の種は基本的にオスのほうが羽が色鮮やかで綺麗な飾り羽をしており、メスは茶褐色で少々地味な色をしています。
これを<性的二形(せいてきにけい)>といい、その理由の一つとして繁殖行動(性淘汰)に関連していると言われています。
例えば<クジャク>は飾り羽が長く派手な色ほど、より目立ちメスにアピールすることができ、より良いオスを産むことができます。
夏のライチョウ(上)、冬のライチョウ(下)
種によって季節によって羽の色が変わる種が存在し、その風景に紛れるカモフラージュになります。
特にライチョウは夏は白黒色をしていますが、冬になると真っ白になります。
生態(たべもの、せいかつ、はんしょく)
雑食で開けた環境を好み、山岳、地面が柔らかい場所を好む種がいます。
繁殖は独特でオス1羽にメス複数羽、子育てを全くしない種がいます。
〇食性
食性は雑食性で植物の種子、昆虫、果実を採食します。
〇環境
主にキジ目の多くは平地、草原、森林、河川敷など開けた様々な環境を好みます。
ライチョウは北アメリカやユーラシア大陸の北極圏周辺、山岳地帯の寒い環境を好み、ツカツクリ科の多くは地面に卵を産めて温める為、地面が落ち葉で覆われているか柔らかい地面などを好みます。
人慣れした個体も確認され、私有地にも近づくことがあります。
〇繁殖
基本多くの鳥類は1夫1妻制で協力して子育てをしますが、キジ目の繁殖は少し独特な形態が多いです。
例えば<キジ>のようにオスが複数のメスと交尾する一夫多妻制で繁殖を行い、メスが抱卵と子育てをします。
これを<つがい外受精>と呼ばれる繁殖方法で、つがい以外のオスとできるだけ多く交尾することで、優秀な遺伝子を引き継いだ雛を誕生させやすくするメリットがあります。
<ヤブツカツクリ>の場合は、落ち葉や土を積み上げた微生物による発酵熱によって卵を孵化させる繁殖方法で、オスは巣作りと孵化の温度管理を入念に行いますが、オスメスどちらも子育ては一切しない特徴があります。
保護評価(ちきゅうにどれくらいいる?)
ライチョウ
全体の生息数は安定していますが、ライチョウに関しては数が大幅に減少し、絶滅危惧種に指定されています。
ライチョウ全体のIUCN保護評価はLC:軽度懸念となっていますが、亜種である<ニホンライチョウ>は個体数が少ない傾向にあり、環境省のレッドリストではEN:絶滅危惧IB類に指定されており、<特別天然記念物>に指定されています。
要因として地球温暖化による気候変動、キツネ、カラス、サルなどの捕食者の分布拡大、高山植物の食害など多くの要因が考えられています。
現在は環境省、自治体、大学、動物園(那須どうぶつ王国)などが連携し保護政策を行っており、最近では一部地域での生息数回復の兆候が見られており、保護評価の見直しが検討されています。
他にキジ目では<セイラン>はVU:絶滅危惧Ⅱ類に指定され、ワシントン条約付属書Ⅱ類に登録されています。
家禽化したキジ<ニワトリ>
セキショクヤケイ
ニワトリ
ニワトリを家禽化した歴史は古く、紀元前4千年前~2千年前とされ、インドとマレー半島に生息していた原種を家禽化したのが始まりとされており、日本へは弥生時代に中国から渡来したとされています。
私たちがよくみる<ニワトリ>の多くは、野生種である<セキショクヤケイ>という野生のニワトリを肉や卵を大量生産できるように品種改良をしたもので、その数は約500品種以上が作出されており、世界中で様々な名称がつけられています。
日本の場合、食肉用の<プロイラー>、卵用の<レグホーン>と呼ばれる種が多く飼育されており、さらに地域ごとの特徴のある<地鶏(ぢどり)>と呼ばれるものが多く作られるようになりました。
例えば、愛知県では<名古屋コーチン>、鹿児島県の<薩摩地鶏>などが有名です。
省スペース、低コストで大量の飼育と繁殖が可能なことから、現在も世界で高い需要を誇り、ウシ、ブタに次ぐ産業動物として、スーパーやファーストフード店などで私たちの食生活に深く浸透するようになりました。
オスとメスで見た目が全く違う<性的二形>
<性的二形(せいてきにけい)>とは、オスとメスの見た目や体系が大きく違うようになる現象の事いいます。
今回の記事で紹介した<キジ>と呼ばれる鳥類ですが、オスでは派手で色鮮やかな見た目をしていますが、メスでは茶褐色の様な地味な色をしており違いがはっきりしています。
他の動物種に例えると、哺乳類ではヒトでは被毛の濃さや体系の違い、ライオンではたてがみがあるかどうか、昆虫ではカブトムシ、クワガタでは頭に角やハサミがあるかどうかなどがそれにあたります。
住みかを追われるライチョウ
<那須どうぶつ王国>の展示エリア<保全の森>のニホンライチョウ
ライチョウは<鳥綱キジ目キジ科ライチョウ属>に分類されるキジの1種です。
元々ライチョウは北アメリカやユーラシア大陸の北半球を中心に生息していますが、2万年前は地球全体の気温が低く、分布域が広かったのですが、地球温暖化の影響もあり気温が以前よりも高く、北半球よりも寒冷な地域へ移動するか、日本の寒冷な地域にとどまるか2択を迫られました。
その日本の寒冷な地域、日本アルプスなどの山岳にとどまることを選んだのがその<ニホンライチョウ>になります。
ライチョウ全体では数万羽が生息しているとされており、保護評価は絶滅の可能性が低い<LC:軽度懸念>となっていますが、<ニホンライチョウ>はニホンサル、アカギツネ、テンなどの捕食やニホンジカによる餌の過剰食害、温暖化による気温上昇や積雪の低下により数を大幅に減らしています。
現在は環境省、自治体、大学、動物園などの関係機関が連携し研究と調査を行いながら、野生復帰と繁殖を行っており、回復傾向にあります。
隊長さんのご意見
【例】
<サーバル>の分類が間違っている場合パターンです。
【〇誤っている内容
哺乳綱クジラ偶蹄目イヌ科レプタイルルス属
〇正しい内容
哺乳綱食肉目ネコ科サーバル属
〇理由
サーバルという種はクジラ偶蹄目ではなく、食肉目に属する肉食動物のグループの1種で、ネコ科の動物です。
以前はレプタイルルス属でしたが、現在はサーバル属に分類が変更されています。】
リンク
〇X【とりはね】
けものフレンズ、動物関連などのつぶやきや動物園などの写真を投稿。
編集履歴
〇20250901
・項目、【家禽化されたキジ<ニワトリ>】、【オスとメスで姿が全く違う<性的二形>】、【住みかを追われるライチョウ】
の記事と画像を新たに追加しました。
・文章の誤字、脱字を修正しました。
〇20250907
・<お知らせ>の項目において、【<図形分類表>を追加しました!】を追加しました。
・<分類>において画像<セキショクヤケイ>、<キジ目の図形分類表>追加しました。