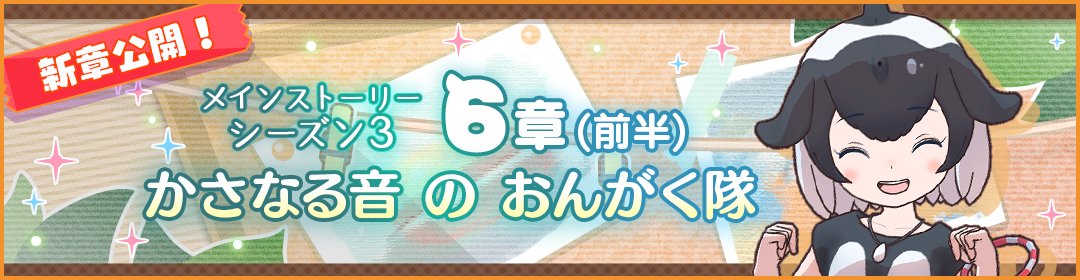お知らせ
〇こちらのブログでは会員の方以外でもコメントができるようになりました。
SNS、動画、フォロワーさんの意見などを元に様々な情報を元にしながら、作成していますが、誤っている情報、何かトリビア的なものがあれば、内容にはよりますが追記、訂正をさせて頂きます。
また、基本的にサイト、SNSなどをソースにして記事を作成していますが、実際に施設へ赴いた方への意見や画像などの取り入れたいです。
X<とりはね>へのDMかアメーバのコメント欄にて受け付けております。
よろしくお願い致します。
〇現在、ともにジャパリパークを盛り上げる隊長仲間(フォロワー)を募集中です!
※条件
相互フォローとなっている方で、<けものフレンズ3>での隊長の名前と<申請しました!>という旨を、X<とりはね>のいずれかのポストのコメ欄、またはDMにて、送信してください。
是非、よろしくお願い致します。
けものフレンズ
〇<けものフレンズ 10th ANNIVERSARY SHOP SPECIAL>が開催されます!
/
— マルイノアニメ (@marui_anime) August 8, 2025
けものフレンズ 10th ANNIVERSARY SHOP SPECIAL
新宿マルイメン開催決定✨
\
🗓️新宿マルイメン
📍2025年9月5日(金)~9月15日(月祝)
⚠️一部日時は事前予約入場となります⚠️
詳細▶https://t.co/YUowtegW0a pic.twitter.com/2YLoHHMtqH
〇メインストーリー シーズン3 6章<かさなる音のおんがくたい>
〇新フレンズ<イロワケウイルカ>、<マッコウクジラ>が登場!
鳥の大移動とは?
繁殖の成功率をあげることや、餌が捕れにくい厳しい冬を乗り越えるために、渡り先で一定期間を過ごすということです(越冬)。
鳥類の野生化での繁殖には、気温や気象条件、昼の長さ、天敵から近づにくさ、餌をとりやすさ、生理条件などが関連しています。
その為、鳥類の多くは餌が捕りやすく、営巣がしやすい環境を求めて長距離を移動し、その渡り先で一定期間を過ごします。
したがって、夏に昆虫などの生物が大量に発生しやすい季節では、繁殖の時間に費やし、寒さが厳しい季節では餌も取れにくくなるため、比較的過ごしやすい地域へ移動し、その渡り先で季節を乗り越えます。
鳥の越冬と繁殖
一般的に春~夏に観察できる鳥を<夏鳥(なつどり)>、秋~冬に観察できる鳥を<冬鳥(ふゆどり)>と呼んでいます。
日本列島は世界中の渡り鳥の飛行ルートの一部となっている為、様々な鳥類が高速道路のサービスエリアとして活用したりしますが、これらの鳥を<旅鳥(たびどり)>いいます。
また、悪天候などで迷い込んだ<迷鳥(めいちょう)>、国内で季節ごとに標高の高いところと平地で渡る鳥を<標鳥(ひょうちょう)>、渡りを行わず、1年中観察できる鳥を<留鳥(りゅうちょう)>と呼んでいます。
日本に限らず、世界中の鳥類が渡りを行っていますが、進化的背景には複雑な要素が絡み合うため、現在も研究調査が行われています。
夏鳥(なつどり)
ツバメ
ダイサギ
カッコウ
アオハズク
ハチクマ
夏の期間は国内で繁殖を行い、秋ごろになると南方の地域へ越冬を行います。
夏鳥は主に4月~7月の春から、夏の終わりごろまで繁殖のため、南部から日本へ北上し、繁殖活動を本格化していきますが、早い種は冬の終わりからすでに移動し始めている個体も見られるようになります。
主な鳥類として、<ツバメ>、<シジュウカラ>、<カッコウ>、<オオルリ>、<キビタキ>、<ホトトギス>、<アオハズク>、<ハチクマ>、<ダイサギ(田植えの時期など)>、<チュウサギ>などが見られます。
この時期は多く鳥類が交尾、子育ての為、活発に飛び回り、水温の上昇とともに河川や水田などに集まるプランクトン、両生類、昆虫などを求めて集まる為、観察がしやすいです。
しかし、夏の季節は木々や葉がおい茂る為、木に止まっている姿での観察難易度が高くなります。
冬鳥(ふゆどり)
エナガ
キビタキ
モズ
ハクチョウ
オナガガモ
夏の期間は北方の地域で繁殖を行い、冬の期間は国内の湖、河川、水田、森林などで越冬します。
冬鳥は主に9月~3月の秋の初めから冬の終わりごろまで、越冬のため北部から日本へ徐々に飛来していきます。
主な鳥類として、<エナガ>、<ヤマガラ>、<ジョウビタキ>、<メジロ>、<キビタキ>、<ルリビタキ>、<モズ>、<カケス>、<シロハラ>、<アカハラ>、<ハクチョウ>、<オナガガモ>、<マガモ>、<カモメ>、<ホシハジロ>などをみることができます。
秋に入り始めると、徐々に一部の冬鳥が飛来していき、一部の夏鳥が活動している為、混合群を作ることがあります。
毛虫、コオロギ、トンボ、バッタなどの昆虫類が多く発生する時期の為、それを求めて木の枝や枯草などに集まるようになり、
12月の本格的な冬に入ると、近くの河川、池、湖、田んぼに多くのハクチョウなどのカモ類が集まり、シロハラ、アカハラ、ツグミなどがみられ、地上の枯れ葉の裏にいる昆虫や木の実を探って食べる姿が確認できます。
冬の季節は木のほとんどの葉が枯れて落ち、木の枝の上に止まっている様子がとても分かりやすく観察がしやすい時期でもです。
旅鳥(たびどり)
オオソリハシシギ
トウネン
繁殖や越冬を目的に飛来するのではなく、一時的な羽休めや餌を食べるために立ち寄る鳥の事をいいます。
日本に飛来する主な鳥類として<オオソリハシシギ>、<オグロオシギ>、<チュウシャクシギ>、<トウネン>など、シギ・チドリ類が中心です。
基本的にこれらの鳥類は、北半球から南半球にかけて非常に長い距離を渡ることで知られており、特に<オオソリハシシギ>はアラスカからニュージーランド、オーストラリアまで、1万2千km以上を10日ほどかけて渡りますが中継地点として、日本に一時的に飛来していることが確認されています。
標鳥(ひょうちょう)
ウグイス
ホオジロ
国内を季節によって山地と平地を短距離で移動する鳥の事をいいます。
主な鳥類として、<ウグイス>、<ヒヨドリ>、<ホオジロ>などが有名です。
例えば、日本全国で見られるウグイスは、夏と冬に比較的暖かい場所を目指して、平地や山地を移動することが知られています(留鳥として同じ場所で過ごすこともある)。
迷鳥(めいちょう)
悪天候など様々な要因により、渡りのルート、生息域から外れて偶然、飛来してきた鳥のことをいいます。
過去に飛来した鳥類では<アネハヅル>、<アメリカホシハジロ>、<インドガン>、<ヒマハジロ>、<ワライカモメ>などが観察されています。
これらは、石川県舳倉島、長崎県対馬、山口県見島などの日本海の離島でよく観察されています。
毎年100種以上が迷鳥として飛来してきますが、毎回同じ鳥種とは限らないことや、日本の鳥類にはない特徴がある為、バードウォッチャーの間では珍しい鳥として定評があります。
鳥が長距離を渡れるひみつ
長距離を渡れるのは、多くの脂肪を蓄え、太陽、星座の位置、磁気により方向を感じ取っているからだと言われています。
長距離を渡る鳥は、まず渡る前に大量に餌を食べて、体脂肪率を増加させ、体重の25∼30%まで増やします。
これは、一度も採餌を行わず長距離をほぼ不休で飛行する為といわれています。
鳥の目の網膜には太陽の青色光を受けると化学反応を起こす、特殊なたんぱく質を含んでいる為、昼間は太陽の位置や磁気を頼りに方向を決めていると言われ、これを<太陽コンパス>と呼ばれています。
また他に夜間では星座の位置、光の偏光、嗅覚など様々な情報を把握していると考えられており、メカニズムに関しては現在も研究が行われています。
隊長さんのご意見
※現在募集中です。
この情報が間違っている、トリビアなど。
リンク
〇X【とりはね】
けものフレンズ、動物関連などのつぶやきや動物園などの写真を投稿。
編集履歴
〇20250829
・<鳥の大移動>の項目において、イラスト<鳥の越冬と繁殖>を追加しました。
・文章の一部のフォントサイズを変更しました。
・文章の誤字、脱字、消去を行いました。
・段落を調整しました。