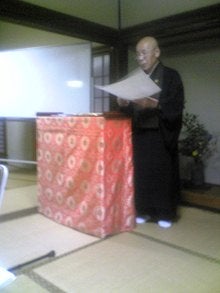ご存知、江戸本所松坂町、吉良上野介 の屋敷へ、赤穂浪士 の討ち入りは、昨日14日。
きょう万慶寺で、「忠臣蔵と万慶寺」の演題で、川中 清司先生 と万慶寺久我住職のお話をお聞きしました。
その万慶寺に、寺宝として、討ち入りの仔細を書き綴った「義士夜討高名噺」が保存されています。
お話は、元禄時代、赤穂浪士の処遇をめぐっての、一禅僧の話題であります。
その禅僧が、万慶寺の開山となった、承天和尚。
元禄15年(1703年)12月15日の朝。
赤穂浪士の一行が、亡君の墓前に参り首をそなえ焼香したいと、泉岳寺に参上。
夜討ち殺生を犯した罪人集団の処遇に、泉岳寺 の住職は狼狽。
碁を打ちにきていた、泉岳寺隣の副寺広岳院住職、承天和尚が、「お咎めがあれば拙僧がお引き受け申す」の一言で浪士を受け入れたそうです。
首尾よく大望を遂げられ、その忠義・名誉のさまを、後世に伝えざることは残念千万なことと、条理を尽くして大石内蔵助を説得、ようやく納得したという。
承天和尚は、一言なりとも聞き漏らしてはと、自ら筆を走らせ討ち入りの仔細を書き綴ったのが、寺宝の「義士夜討高名噺」として今に伝えらているものです。
私も講演の前のあいさつで、以前にも、私のブログ(http://ameblo.jp/hyakuo/day-20061215.html・ http://ameblo.jp/hyakuo/day-20070206.html )でも触れさせていただきました、「近松門左衛門 と赤穂藩」について、ご紹介させていただきました。
一昨年11月8日 と今年の2月6日、近松門左衛門から9代目にあたる子孫の、近松洋男さん(京都外国語大学名誉教授・元天理大学教授)にお会いした時の話題。
近松は、2歳から12歳まで、吉江藩 に父杉森信義と住んでいました。
その後、赤穂藩の筆頭藩医である、近松伊看 の養子となり、京都の三条家に仕え、御所勤め。
上司の一条恵観公 (御水尾天皇の弟君)が他界して、辞職しております。
その後、19歳から10年間赤穂藩に仕官。
赤穂塩の販売を手がけたそうです。
浄瑠璃の作者として名前が記録される、31歳ごろまでの空白の10年間は、赤穂藩御用に徹した謎の10年だったようです。
この間、大石内蔵助とも濃密に繋がり、赤穂塩のネットワークを完成させ、藩財政の確立に活躍しております。
また、 赤穂浪士四十七士の、近松勘六 と奥田貞右衛門 (勘六の異母弟で奥田孫太夫の婿養子)の2人は、近松の養父近松伊看の孫、門左衛門からは、義甥にあたります。
門左衛門は近松勘六の討ち入りにあたって、勘六の子供に累が及ぶのを避けるため、2人の子供を養子(遺児1人は、京都近松の初代となる文四郎)にしております。
また、門左衛門は、西回り航路で敦賀で下船、吉江藩 にもたびたび訪れ米・塩の取引のほか、輪島で習得した蒔絵技術を、春慶寺で伝授していたそうです。
越前蒔絵の起源は、この地かも・・。![]()
![]()
当時、塩貿易ルート開発構想まであったようで、航海には、寺坂吉右衛門
(四十七士で身分は足軽、唯一人生き残られた浪士)も門左衛門と同道し、通訳にあたったようです。
近松洋男さんは、近松家には赤穂討ち入りに関係する身内がいたことで、それが幕府にばれたら危険だからと2000年の今まで、文書ではない口伝で伝えてきたと言われました。
近松本人の意思もあり、公界(士農工商のどの身分にも属さない天皇を中心とした自由社会の事で、職業的には、今で言うインテリ層で、医者、学者、著作業、宗教人、芸術家、芸能人、回船業者等)の義もあって、世に秘してきたそうです。
それを、門左衛門生誕350年を迎えたのを機に、代々、近松家に伝わってきた口伝を、禁を破って公表することに。
近松洋男さんは、「口伝解禁 近松門左衛門の真実」 という著書を発刊。
関連ブログ・南川泰三の「近松門左衛門と赤穂浪士 」もあわせてご覧ください。
http://taizonikki.exblog.jp/2324617/
「先祖代々の口伝の根拠は、何か古文書か、証拠となるような資料は?」とお聞きしても、「絶対に外に漏らすなと言われた口伝、証拠となるようなものは一切残しませんでした」とのことでした。
「何の裏付けもない口伝など学問の対象にならない」という方もおられますが、連綿脈々と繋がる口伝の重さ、大事にしたいものです。
近松門左衛門の出生についても、つい最近の、平成15年大阪府箕面市の瀧安寺 で見つかった、近松直筆の写経の中に書いてあった戒名と、杉森家家系図に残されていたものとが、ピッタリ一致したことによるものです。
近松が浄瑠璃作家として名を成したのが31歳、それから、出生地が越前鯖江に落ち着くまで320年もかかっています。。
江戸時代には諸説紛々、多い時には、11箇所もの生誕地説があったそうです。
なぜかといえば、近松が自分の出自や経歴をまったく書き残していないからです。
近松洋男先生の口伝が奇想天外というより、地元としては、これが事実と信じたいものです。
・ 赤穂浪士助命の策をめぐらしていた、当時、甲府中納言綱豊(5代将軍綱吉の弟君、後の6代将軍家宣)の側用人であった、鯖江藩藩祖の間部
詮房
。
・ 赤穂浪士を義士として温かく受け入れられ、後に、間部家の菩提寺万慶寺を開山(藩祖詮房との縁といわれている)した、承天和尚。
・ 赤穂藩御殿医近松伊看の養子となり、大石内蔵助 との濃密な繋がりや身内に2人の赤穂浪士がいた、近松門左衛門。
忠臣蔵との、あまりにも関係の深いまちに、あらためてビックリです。![]()
![]()
![]()
絶対に何か![]()
![]() 、いい物語ができそうです。
、いい物語ができそうです。![]()
![]()
今後の研究での、驚愕的歴史の実証を期待しています。![]()
![]()
![]()
![]()
![]()