朝から青空の原村です。
東京から帰ってきた今朝はぜんぜん違う朝です。何しろコタツに足を突っ込んでた私ですから(笑)窓を開けたまま寝てしまったら、朝方は寒くて目が覚めました。爽やかな朝です。やっぱり原村がイイわあ〜って思う朝です。せっかくですから原村の大きな青空を見に行こうかと思いまして…
青い空の下柱が4本!ここは「中原遺跡」正確には「なかっぱらいせき」
こんなにキレイな空を見ながらエコーラインをビーナスライン方面へ走ります。
茅野市のビーナスライン沿いにある「中原遺跡」からの景色です。
もちろん八ヶ岳も見えます。
ここは、国宝「仮面の女神」が出土した縄文時代の遺跡です。中原遺跡(なかっぱらいせき)公園
4本の柱の隣の建物が「仮面の女神」が出土した場所で、その瞬間を再現してあります。
ここからは、ほかにも何点かの土器や翡翠や琥珀なども出てきたそうです。
公園の真ん中には竪穴式住居の柱の跡も残してあるのです。
不思議なのはこちらの大きい4本の柱と小さい4本の柱の計8本の柱
発掘調査で発見された「柱穴列」柱を立てていたと思われる穴が見つかり、再現して、こんな風に柱が建てられていただろう!という事です。これが、諏訪地域の御柱祭の始まりかも知れない!とも言われています。
御柱祭は江戸時代に現在に近い形で行われていた事がわかっているそうですが、更にむかしの大昔!縄文時代の頃に高い柱を立てて、少しでも神に近づこうとしていたのではないか…とか
古代史ミステリーは、「NHKの古代史のドラマミステリー御柱祭」 と紹介されました。考古学的にも不思議な柱の存在のようです。うまく説明ができませんが、たぶん大ざっぱですがこんな感じの意味かな?
諏訪大社御柱祭も山から何十キロも引かれて行く巨木の柱を、木落としで山から里に落とし、川越しで柱を清め、建て御柱で神になる。その儀式が縄文時代からあったとしたら、その時代にどうやって巨木を立てたのだろうか?柱は高ければ高いほど神に近づけた〜のだろうか?
ふっと思ったのですが、縄文時代では長い柱を立てるには限界があって、その余った部分を前に立てたのでは?あくまでも私が思った事ですが(^.^)
諏訪地区は古代史のミステリーの多いい場所のようです。むかしむかしの大昔、長野は自然豊かな場所で、生活はけっこう裕福に暮らせる土地だったとか、山から流れ落ちる清らかな水と、狩りができる動物と木と木の実などなどと食料は豊富に手に入っていたようで、そのため日本列島の中でも米作りは一番遅かったらしいです。
粘土で土偶作りも体験できる「尖石縄文考古館」
ここに国宝に指定された「仮面の女神」「縄文のビーナス」が展示されています。
エコーラインを茅野市方面に走り「尖石縄文考古館」の信号を入ればすぐです。三井の森別荘区につながる、緑豊かで美しい道にあります。今日はちょっと古代史が面白いかも?って思った一日でした。
ご訪問ありがとうございましたm(_ _)m
そろそろ曜日が変わる時間になってしまいました。さあ〜てと!明日の仕込みが終わってないので、これで失礼いたします。今日も、応援のひと押しをいただければありがたいです。よろしくお願い致します。
↓↓↓
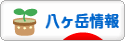
にほんブログ村
東京から帰ってきた今朝はぜんぜん違う朝です。何しろコタツに足を突っ込んでた私ですから(笑)窓を開けたまま寝てしまったら、朝方は寒くて目が覚めました。爽やかな朝です。やっぱり原村がイイわあ〜って思う朝です。せっかくですから原村の大きな青空を見に行こうかと思いまして…
青い空の下柱が4本!ここは「中原遺跡」正確には「なかっぱらいせき」
こんなにキレイな空を見ながらエコーラインをビーナスライン方面へ走ります。
茅野市のビーナスライン沿いにある「中原遺跡」からの景色です。
もちろん八ヶ岳も見えます。
ここは、国宝「仮面の女神」が出土した縄文時代の遺跡です。中原遺跡(なかっぱらいせき)公園
4本の柱の隣の建物が「仮面の女神」が出土した場所で、その瞬間を再現してあります。
ここからは、ほかにも何点かの土器や翡翠や琥珀なども出てきたそうです。
公園の真ん中には竪穴式住居の柱の跡も残してあるのです。
不思議なのはこちらの大きい4本の柱と小さい4本の柱の計8本の柱
発掘調査で発見された「柱穴列」柱を立てていたと思われる穴が見つかり、再現して、こんな風に柱が建てられていただろう!という事です。これが、諏訪地域の御柱祭の始まりかも知れない!とも言われています。
御柱祭は江戸時代に現在に近い形で行われていた事がわかっているそうですが、更にむかしの大昔!縄文時代の頃に高い柱を立てて、少しでも神に近づこうとしていたのではないか…とか
古代史ミステリーは、「NHKの古代史のドラマミステリー御柱祭」 と紹介されました。考古学的にも不思議な柱の存在のようです。うまく説明ができませんが、たぶん大ざっぱですがこんな感じの意味かな?
諏訪大社御柱祭も山から何十キロも引かれて行く巨木の柱を、木落としで山から里に落とし、川越しで柱を清め、建て御柱で神になる。その儀式が縄文時代からあったとしたら、その時代にどうやって巨木を立てたのだろうか?柱は高ければ高いほど神に近づけた〜のだろうか?
ふっと思ったのですが、縄文時代では長い柱を立てるには限界があって、その余った部分を前に立てたのでは?あくまでも私が思った事ですが(^.^)
諏訪地区は古代史のミステリーの多いい場所のようです。むかしむかしの大昔、長野は自然豊かな場所で、生活はけっこう裕福に暮らせる土地だったとか、山から流れ落ちる清らかな水と、狩りができる動物と木と木の実などなどと食料は豊富に手に入っていたようで、そのため日本列島の中でも米作りは一番遅かったらしいです。
粘土で土偶作りも体験できる「尖石縄文考古館」
ここに国宝に指定された「仮面の女神」「縄文のビーナス」が展示されています。
エコーラインを茅野市方面に走り「尖石縄文考古館」の信号を入ればすぐです。三井の森別荘区につながる、緑豊かで美しい道にあります。今日はちょっと古代史が面白いかも?って思った一日でした。
ご訪問ありがとうございましたm(_ _)m
そろそろ曜日が変わる時間になってしまいました。さあ〜てと!明日の仕込みが終わってないので、これで失礼いたします。今日も、応援のひと押しをいただければありがたいです。よろしくお願い致します。
↓↓↓
にほんブログ村










