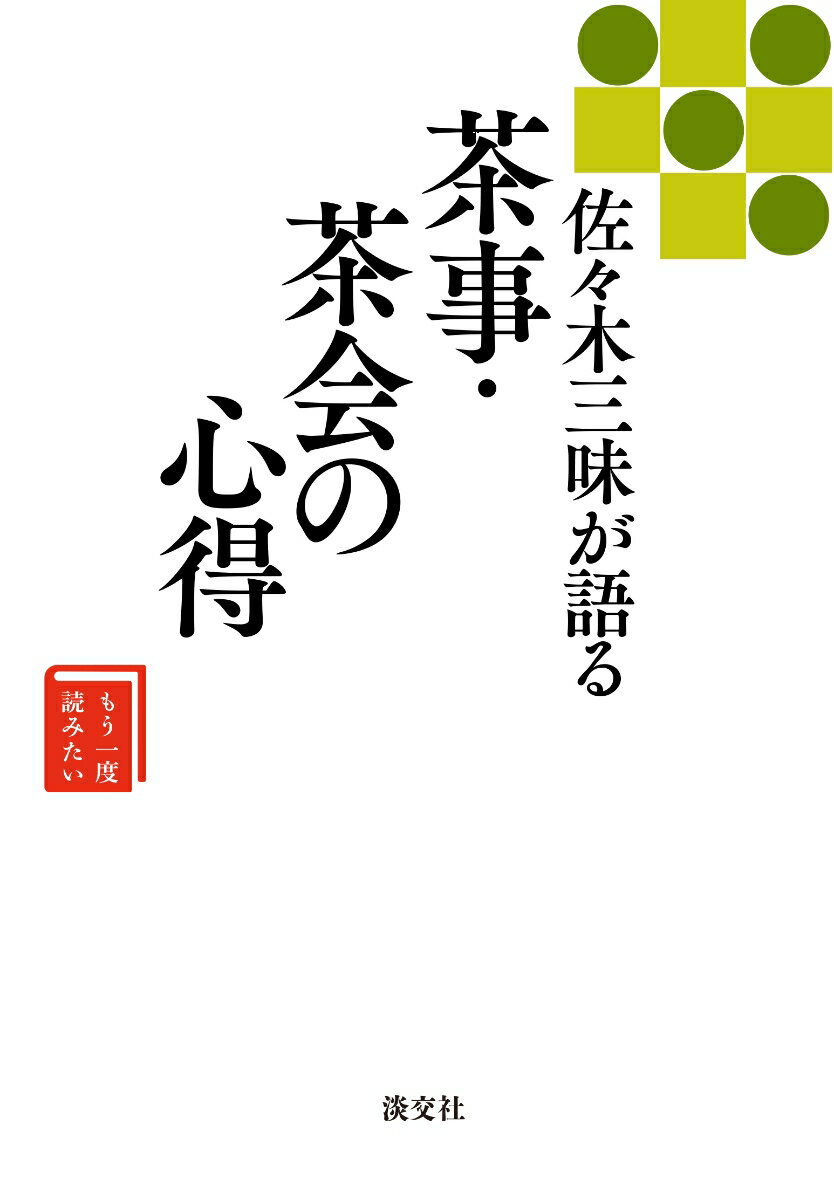茶事・茶会の心得 佐々木三味著
茶杓の銘
春 山吹 郭公
夏 卯の花
晩秋 紅葉
初冬 散り紅葉
茶器の銘
①物の優秀
②景色
③来歴
④所持者
道具が主、亭主が従のお茶から、亭主の人格の表現・芸術的な創作の茶へシフトする
懐石料理 一汁三菜を限度とし、牛飲馬食しては物の味は分からなくなる。乏しい位がしみじみと味わいつくせるのである。
茶の醍醐味
乏しさ、つつましさ、幽かなるもの、そこに美しさを求めて、その中から高い情操的なものを味わう
茶を点てる事ができれば、亭主になり、生きた茶をしていく事が大切
その為に亭主は心の用意をし、客と慈しみながら茶を楽しむ
無理をしない
分相応の茶
利休曰く「釜一つあれば茶の湯はなるものを
数多の道具持つぞ愚かな」
懐石の方が主になり、茶が疎かになるのは、頂けない。
利休曰く「草庵を書院のごとく、取り捌き、
基本意を尋ねるに及ばず、大食大酒の人は
草庵にでも酒盛りの興をなし、その心々に叶はざれば侘数寄いやに思ふ成」