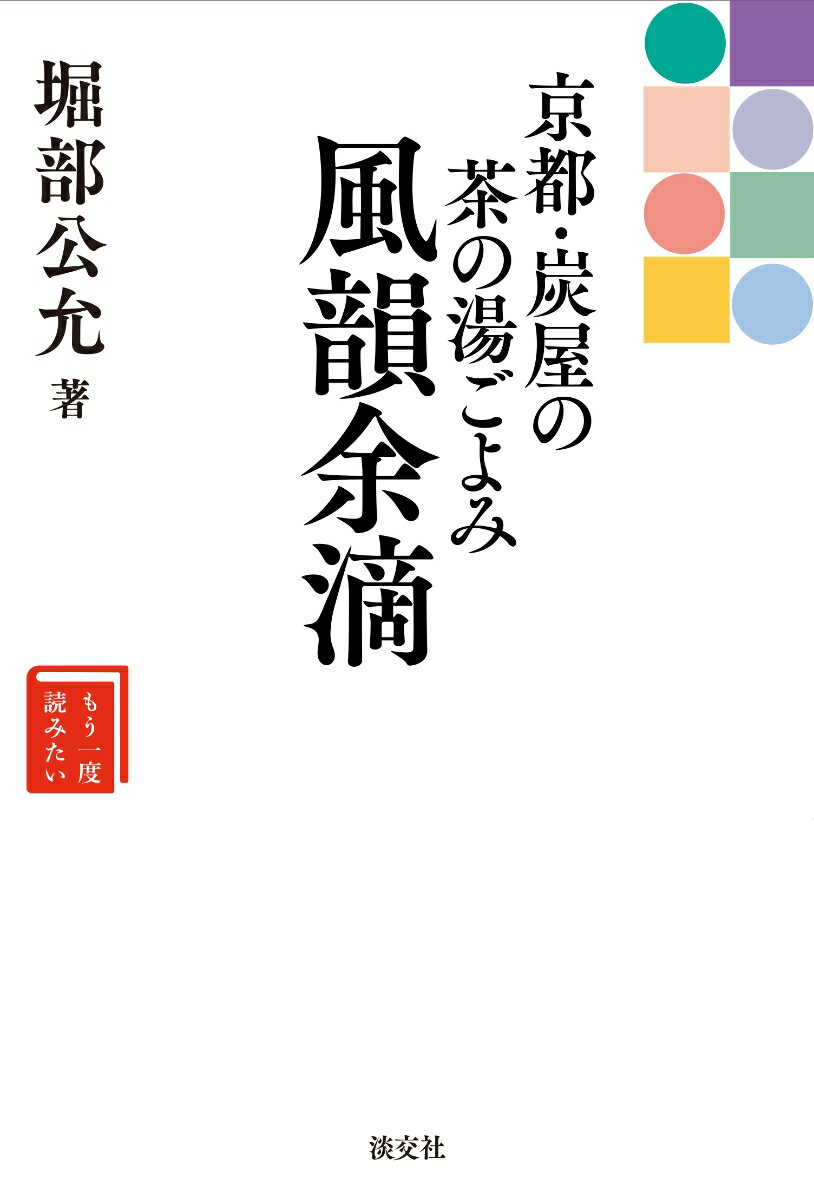炭屋の茶の湯ごよみ
睦月
睦月を迎える準備
炉壇 片田儀斎
除夜の鐘 余韻がゆっくりと松風に融け込んでいく 沈黙の刻
にしん蕎麦
おけら詣り
門松 事始め(12月13日)に迎入れ
28日、朝に立てる
蓬莱飾り 三宝に奉書紙をひき洗い米、胴炭
昆布、神馬草、熨斗鮑、串柿、橙
伊勢海老、海・山の幸(土器)
床の間 結び柳、日陰蔓
望月釜
正月の茶席
香合 老松形
主茶碗 赤楽梅暦
棗 寒雲棗
如月
鰯の頭を柊と門に飾る
立春のお参りは、吉田神社やみぶ寺
茶杓 初午
長月
洗月の間
床框 北山丸太の面皮が一部残った床面を水面に見立てる
軸 玉室宗珀 明月上孤峰
水指 仁阿弥道八 竹の絵
茶杓 銘 羽衣 玄々斎
棗 利休形 尻張棗
主茶碗 富士の絵 慶入
神無月
名残
一如庵
軸 掬保萬歳齢 玄々斎筆
香合 貝合わせ 菊の絵 玄々斎好
釜 真形桐地紋釜 初代寒雉
風炉 道安面取雲華
水指 曲物 菊の置上 駒澤利斎
主茶碗 志満台
茶杓 銘 福寿海
趣のあるしたたり 風韻余滴