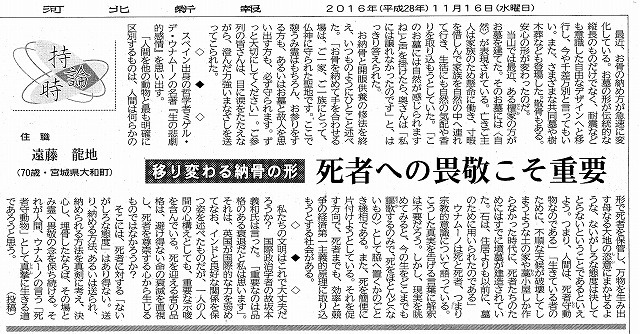
11月半ば、新聞やテレビなどのマスコミは、人工知能(AI)「東ロボくん」が東大合格を断念したと報じた。
理由は、問題文などの意味を理解する能力に限界があるからだという。
複数の文章を組み合わせると、一つ一つの短い文章は分析できても、それぞれの文章の意図や関係、あるいは全体の文脈を理解できない。
プロジェクトリーダーの新井紀子・国立情報学研究所教授は明かした。
「東ロボくんは、そもそも意味を理解して問題を解いているわけではない。
そこに限界がある。」
ここに重要な問題がある。
ロボットは、問題文から答を導き出しても、それは問題文を〈理解〉した上で、問題文の意味する内容に〈ふさわしい〉答を見つけているのではない。
単語あるいは組み合わせられた単語とつながる確立の高い単語を自動的に選び、自動的に組み合わせるだけなのだろう。
たとえば、「秋が来た」「セーターが欲しい」という二つの文章がある場合、秋らしいセーターを持っていないからなのか、それとも寒いからなのか、といった心中の動きについては、前後の文章を分析しても解を見つけられないのだろう。
生きた人間同士の会話なら、こうなろうか。
男が言う。
「秋になったね」
女が言う。
「セーターが欲しいわ」
男にはさまざまな考えが起こりうる。
〝彼女は私とのデートで着る秋用のセーターもないほど貧しいのか〟
〝もしかして、この女は、モノカネが目当てで俺とつきあっているのではなかろうか〟
〝この娘はやっと、僕に甘える気持になってくれたらしい〟
〝セーターが欲しいほど寒いと言う先には、肉体関係を許してもよいという気持があるのかも知れない〟
こうした判断を誤らなければ、二人の関係は妥当な結末へと進むだろう。
もしも、女の言葉が男の反応を考えない不用意なものだったり、男の判断がトンチンカンだったりすれば、残念な結果が待っているだろう。
情緒を含んだ理解と判断ができないロボットは、人間と心を通い合わせ、人間に代わってつき合うことはできない。
もしも人間がロボットに愛着を感じるならば、それは人間の側からの一方的な気持でしかない。
ロボットは、具体的な要求への対応としていつも変わらぬ反応を示し、決して裏切らないだろうが、それは変わらぬ思いやりを示しているわけではない。
ロボットの読解力を研究する過程で、恐ろしい事実も判明した。
新井教授らが中学生の読解力を調べたところ、約5割が教科書の内容を読み取れないだけでなく、約2割に至っては基礎的・表層的な読解すらできていないという。
この指摘は恐ろしい。
「中学生の多くは単にキーワードを拾って読んでいる。」
これではロボットと同じではないか。
もしも〈それだけの人間〉になったなら、ロボットに敵わない。
それは、情緒や、他者の思いに対する感応力が鈍り、心が深まらず、ひいては人間性が貧しくなる道に違いない。
人間が人間であるためには、読書が必要であると思う。
それも、キーワードをつなぐノウハウものではない読書である。
他者の多様な思考や感情に触れ、自分の思考や感情を豊かに養えば、人間はケダモノでなく、ロボットでなく、人間として生きられる。
多様な自然と生きものの世界、多様な人間社会にあって、多様性に感応できる柔軟な姿勢を育て、人間らしい人間として向上しつつ生きられる。
中学生諸君には、まっとうな本を読んで欲しいと願ってやまない。
小学生から英語を教え、そろばん勘定の体験をさせる前に、やらねばならぬ重大なことがあると思う。
読書の習慣づけである。
原発事故の早期終息のため、復興へのご加護のため、般若心経の祈りを続けましょう。
般若心経の音声はこちらからどうぞ。(祈願の太鼓が入っています)
お聴きいただくには 音楽再生ソフトが必要です。お持ちでない方は無料でWindows Media Player がダウンロードできます。こちらからどうぞ。
「のうぼう あきゃしゃきゃらばや おん ありきゃ まり ぼり そわか」※今日の守本尊虚空蔵菩薩様の真言です。
どなたさまにとっても、佳き一日となりますよう。
https://www.youtube.com/watch?v=IY7mdsDVBk8

