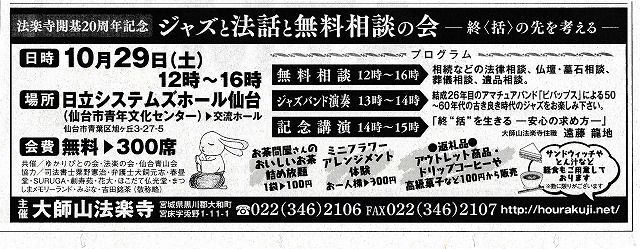
私たちが生きる上での問題はまず、安定した衣食住の確保、次に、生きがいの獲得ではないでしょうか?
1 無財の七施
一番目については、自分の努力と社会のありようとが決めます。
怠け者ではどうにもなりませんが、いくら労働意欲があっても社会が混乱したり、戦火の雲に覆われていたりすれば、どうにもなりません。
自分の業(ゴウ)と社会の共業(グウゴウ)をよく考えてみましょう。
社会のおかげなくしては一瞬も生きられず、良きにつけ、悪しきにつけ、社会と無関係は人は一人もいません。
だから誰一人、社会の傍観者ではいられず、傍観者であってはならないと言えましょう。
二番目については、ほぼ、自分次第、自分の生き方次第です。
医療関係者や福祉関係者などの人生相談を受けていると、生きがいはどこにでもあると実感します。
たとえば、ある女性の介護士さんが難しいことばかり言うお爺さんに手を焼いていましたが、ある日、昔話を聴いていたところ、どうしたことか「自分は子供の頃からへそ曲がりだった」と涙ながらに詫びられました。
彼女は手を取って一緒に泣き、誠意を尽くしてきて本当によかったと喜び、初めて仕事を誇りに思えました。
おじいさんは、その日から別人のようになりました。
まごころの交流が、お爺さんの捻れをなおし、看護師さんにやりがい、生きがいをもたらしました。
生きがいは、手応え、達成感の蓄積によって得られます。
連続する確かな達成感が、喜びと力になってその人を輝かせます。
この達成感は、どこにでも見つけられます。
その典型が「無財の七施」、財物によらない施しです。
○眼施(ガンセ)
思いやりのある優しいまなざしで相手を見ることです。
眼は口ほどにものを言うのです。
○和顔悦色施(ワゲンエツジキセ)
和やかさと笑みを含んだ相貌で相手と接することです。
医師の穏やかな顔と接するだけで気持が落ち着いたり、孫の笑顔を見るだけで励まされたりします。
○言辞施(ゴンジセ)
思いやりを含んだ言葉を相手へ届けることです。
「ありがとう」や「おかげさま」や「おたがいさま」が心を和ませ、勇気づけ、励まし、いのちの力を引き出すことは驚異的なほどです。
○身施(シンセ)
身体を使って相手へ何かをさせてもらうことです。
東日本大震災などで、みかえりを求めない珠玉の汗がどれだけ流されたことでしょうか。
○心施(シンセ)
相手を思いやり、心配りをすることです。
相手の立場や気持を思いやって心を配り、気を配るところから布施行は始まります。
○床座施(ショウザセ)
相手へ座る所を提供することです。
乗り物の席を譲る光景は例外なく美しいものです。
○房舎施(ボウシャセ)
まず、来訪者を温かく迎えることが大切です。
モノを渡さなくても、貸すことによって相手へ雨風をしのぐ場が提供できます。
もしも、ベッドに横たわっていてすら、誰かへ穏やかな顔で和やかな言葉をかけられれば、それはまぎれもなく尊い布施行であり、一つの達成です。
日々、「無財の七施」を心がけてみませんか。
2 「比丘の四法」
付録として、せっかくの善行を台無しにしかねない〈人間関係の破壊〉から免れる方法を書いておきます。
それは「比丘(ビク…男性の出家修行者)の四法」です。
○相手を非難しても、二度とは非難しない
○相手を怒っても、二度とは怒らない
○相手へ暴力的にふるまっても、二度とは暴力的にふるまわない
○相手の過失を暴いても、二度とは暴かない
いずれも、そうしなければならない時、あるいは、そうしないではいられない時の心構えです。
自他のために、誰かの過失を暴き、厳しく非難せねばならないならば、勇気をもってやらねばなりません。
怒り、暴力的にふるまう必要性に迫られる場面からも逃げられません。
自分と相手を救うだけでなく、悪行の害毒が広がるのを防ぐためです。
もしも、自分に起こった感情を引きずり、繰り返すことによって相手へダメージを与えるところまで行けば、ことのスタート時には理があっても、最後は悪行(アクギョウ)に転じてしまいます。
それは、人間関係を壊す行為になり、出家修行者の間で厳しく戒められていたことが理解できます。
この戒めは、普通の社会人にとっても、必要な心がけであると思われます。
3 二の矢
最後に、貪り・怒り・愚かさの三毒に陥らないための心構えである「二の矢の教え」について少々書いておきます。
ある時、お釈迦様が弟子たちへ問いました。
確かにそうです。
お釈迦様は、いかに徳が高く、慈悲と智慧に満ち、法力に勝れていてもきっと、超然としてはいなかったことでしょう。
周囲の人々が心の温かさを実感できたに違いなく、表情も豊かだったことでしょう。
何しろ、観音様とお不動様が同居しておられたのです。
ならば、喜怒哀楽が私たちとどう違うのか?
弟子たちは誰も答が見つけられず、お釈迦様は、おもむろに説かれました。
「二つ目の矢を受けるか否かが違うのである」
私たちは、外的刺激に対して、どうしても貪り、怒り、愚癡にたどりつきやすいのです。
喜べば「もっと、もっと」とさらに欲しくなり、気に入らなければ「このやろう」と怒って排除したくなり、自分に利をもたらさなければ「知ったこっちゃない」と無視します。
しかし、仏弟子は、快感に溺れず、不快感に左右されず、自己中心でなく周囲を観るので、因縁の糸を見失いません。
こうありたいものです。
原発事故の早期終息のため、復興へのご加護のため、般若心経の祈りを続けましょう。
般若心経の音声はこちらからどうぞ。(祈願の太鼓が入っています)
お聴きいただくには 音楽再生ソフトが必要です。お持ちでない方は無料でWindows Media Player がダウンロードできます。こちらからどうぞ。
「のうぼう あきゃしゃきゃらばや おん ありきゃ まり ぼり そわか」※今日の守本尊虚空蔵菩薩様の真言です。
どなたさまにとっても、佳き一日となりますよう。
https://www.youtube.com/watch?v=IY7mdsDVBk8
