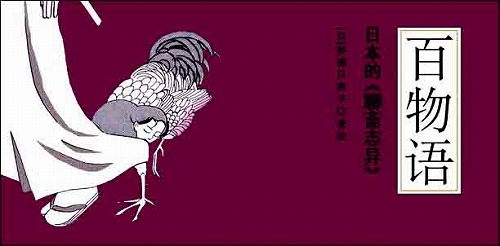
ご葬儀の際、最後の法話までが導師の法務と心得、法話が終わり会場を後にしてから、喪主様のご挨拶となる流れが多かった。
しかし、ある時、喪主のご挨拶後に導師の席を立つよう要請され、久方ぶりに座ったまま、お話を聴いた。
内容には圧倒された。
「母はあの世へ旅立ちましたが、これで家族がなくなったわけではありません。
母は私たちより一歩先にこの世から離れただけのことです。
やがて私たちも次々に行くので、また絆を結び、あの世で楽しく暮らしたいと思います。
その日のために、この世で導いてもらったとおり、あの世から見ている母に恥ずかしくない生き方をしようと思っています。」
この方が仏教徒かどうかは知らないが、ご一家はキリスト教徒でなく、生前の故人共々、当山の法務に納得して墓地を求め、仏教によるお別れをされた。
これまで幾度か、お会いした印象からすれば、喪主様の言葉は特殊なドグマなどを信じてのお話ではなく、自然な感覚をそのまま口にされたのであろうと思う。
要は、人は死んでも無にならず何かが残り、この世で家族となった縁は、家族の死によって消えないと感じておられるのだ。
だからこそ、お墓を造り、お参りをする。
親の導きや戒めは、親が亡くなれば消えるのではない。
新たに与えられることはなくなるので、子供としてはいっそう、大切にして行かねばならないものとなる。
人倫とはこのことの謂いではなかろうか。
白川静著『字通』によれば、「侖は相次第して、全体が一の秩序をなす状態のもの」である。
また、「輩(トモガラ)」であり、「道」でもある。
だから「倫」は一字だけで人倫を意味する。
とすれば、人倫の根本には〈連なりの意識〉がなければならない。
さて、9月14日付の産経新聞は「特権階級が社会を牛耳る」と題して、中国の農村部で根付く読書無用論について書いた。
「『勉強する必要はない』という『読書無用論』は、農村部を中心に今も大きな支持を得ている。
中国青年報が2014年、四川省の雲郷雍村で行った調査では、村の262世帯の約4割に当たる106世帯が子供を学校に行かせる必要はないと考えていた。
『字を知らなくても金は稼げる』『教育費が高すぎる』などの理由からだという。」
この風潮は悪名高い毛沢東の文化大革命から広まった。
「最高指導者の毛沢東自身が読書家であるにもかかわらず知識人を嫌い、68年には小中学校を含めて『授業を中止して全身全霊で革命に尽くせ』と呼びかけた。」
人々から、ものごとを鵜呑みにせず自分で考える力を奪い、一つの思想で染めて統治しやすくした。
「文革期の読書無用論は、党中央が推進する政策や、党幹部の特権などに異論を差し挟む知識人を打倒し、物事を考える力を奪う『愚民政策』の一環だったと指摘される。
現代の農村部とは事情が異なるように思えるが、『本質は全く同じだ』との指摘もある。
『文革期、中国を動かしたのは優秀な人材ではなく、特権を持った人々だった』。
北京のある文化人はそう前置きした上で、次のように語った。
『最近は、元高官の二世などの特権階級に社会が再び牛耳られるようになった。
庶民は努力しても報われることが極端に少なくなった。
特に農村部の保護者たちは、子供に勉強させること自体がバカらしくなっている』。」
このとおりだとすれば、中国の指導部は、国民を二分しようとしていることになる。
特権階級と、それ以外の人々だ。
文化大革命では分断策により、家族関係や師弟関係などを問わず凄まじい密告・暴力・虐待・殺人などが起こっただけでなく、暴風がおさまった後も、被害者の自殺、加害者の罪悪感、生き残った人々のPTSD(心的外傷後ストレス障害)など、広汎な人間性の破壊が行われた。
明らかに、〈連なりの意識〉が家庭からも、社会からも奪われたのだ。
ひるがえって日本を眺めてみればどうか?
確かに「絆」が叫ばれてはいる。
しかし、それは主として空間的に、言わば〈横に広がるもの〉として、とらえられているように思われる。
手をつなぐ意識である。
無論、それはそれで結構だ。
しかし、私たちの文化はそもそも時間的に、言わば〈縦に連なるもの〉として紡がれてきたのではなかったか?
お祭りなどの行事であれ、学問であれ、技術であれ、各種の芸能であれ、もちろん宗教であれ。
そして、神棚も仏壇もお墓も、特に言挙(コトア)げするまでもなく、切れるはずのない絆を象徴するものだった。
江戸時代までは、こうした空間的な絆と時間的な絆のバランスがよかったのではなかろうか?
そこを見抜いたからこそ、故杉浦日向子はこう言ったのではなかったか?
「江戸時代は、自分と他者の境界線がものすごく曖昧で、融通し合っていた。
その辺から、パワーなり、エネルギーなりが生まれていた。」
「250年続いた泰平の世は、言うならば、低生産、低消費、低成長の長期安定社会。」
時間的に縦に連なるものに懸ける者同士として、空間的に横に連なるのは当然であり、そこに文化の創造性があると説いたのが故三島由紀夫だった。
彼はたった一人で東大へ出かけ、約千人の学生を相手に2時間、討論した。
議論の中心は時間と空間の問題だったように思われる。
個人主義が膨れ上がり、極端な消費社会になり、緊張と不安と競争に明け暮れる私たちは、〈連なりの意識〉を忘れつつあるのではなかろうか?
横に絆を求める一方で、家族や先祖などとの自ずから与えられている縦の絆を、あまりにも脇へ追いやってきたのではなかろうか?
冒頭に挙げた喪主様の言葉には、風潮に流されない人、自然に絆を育ててきた人の明晰で強靱な自覚がある。
救われている方に救われる思いだった。
そうそう、今後はなるべく喪主様のご挨拶をお聴きしてから退場しようと思う。合掌
原発事故の早期終息のため、復興へのご加護のため、般若心経の祈りを続けましょう。
般若心経の音声はこちらからどうぞ。(祈願の太鼓が入っています)
お聴きいただくには 音楽再生ソフトが必要です。お持ちでない方は無料でWindows Media Player がダウンロードできます。こちらからどうぞ。
「おん ばざら たらま きりく」※今日の守本尊千手観音様の真言です。
どなたさまにとっても、佳き一日となりますよう。
https://www.youtube.com/watch?v=IvMea3W6ZP0
