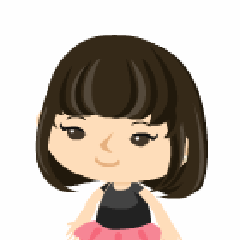「ご都合主義」、「ハプニング頼り」、「細かいことは、気にすんな?それワカチコワカチコ♪」といえば〰?
それは、わたくし、ぽてとのことでございます( ̄^ ̄)エッヘン←←←
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「社さんに聞いた。キョーコちゃんが、CMの共演者の人に『京子』ではなく『最上キョーコ』として晩御飯に誘われたって。」
蓮は自宅に戻るなり、出迎えたキョーコにただいまと軽く言うと、すぐに本題を切り出した。
「………あ、はい!えと、でも」
「なんでもなかったって。」
「あ、の、」
「なんでもなかったって聞いてる。だから、俺は気にしないことにした。だから、キョーコちゃんも『仕事のための情報提供をしただけ』って認識していてほしい。」
「……はい。」
「それに、今回みたいに会うことはもう無いんでしょ?次は、収録の時かな。」
「あ、はい。『これで曲は書ける』とおっしゃっていましたから。」
「……うん。というわけで、この話はおしまい。」
「あ、はい!」
男性と食事に行ったことを少なからず気に病んでいたキョーコは、蓮の方からこの話題を完結してくれたのでホッとした。
「ふふ、うん、いいお返事です。さて、この匂いは………鰹のお出汁……?」
「わ、ピンポーンです!今日の晩御飯は、『茶カツ』なんですよ!」
「………『チャカツ』…………って、なんだ?」
「それは、見てのお楽しみで〰っす。」
わだかまりが無くなった二人の声は、今から始まるおうちデートへの期待に満ちて、楽しく弾んだ。
カチャカチャじゃぶじゃぶと音がする中、今夜も二人は仲良くキッチンで後片付けをしていた。
蓮は時々、キョーコの髪や頬にちゅっと軽いキスを落とす。キョーコは、ふにゃふにゃとしながら、そのキスを受け止めていた。
でも、キョーコは先ほどから、実はかなりいたたまれなくなってきていた。とても軽くふわりと触れていただけの蓮の唇が、ちゅくぷっと音を立てて、首すじに押し付けられたり、後頭部の髪の生え際に鼻を押し付けて匂いを嗅がれたりと、蓮のスキンシップが、キョーコが明るく笑いながら受け止められる範疇を越えだしたからだ。
そんな恋人達の甘い空気を薙ぎ払ったのは、キョーコの携帯への着信だった。
「…………あ、でっ電話…………、……………………。」
急いで手を拭いて携帯電話を手に取ったキョーコは、しかし、液晶画面を見て思案顔になった。
「?、出ないの?」
「………知らない電話番号でして。」
「……出てみたら?意外と知り合いかも。仕事関係とか。変な電話なら、俺が対応するから。」
キョーコはそこまで蓮に甘えるつもりはないが、とりあえず電話には出てみることにした。
「…………もしもし?」
『夜分にすみません。最上キョーコさんの携帯電話でよろしいでしょうか?わたくし、小池真也と申します。』
「し、真也さんっ?」
『あ………その声はやっぱりキョーコさんですね。……よかった。』
「え、と。でも、あれ?番号………」
と、キョーコは言いかけて、そういえばと、先日の夜の別れ際のことを思い出した。曲作りのことでもしかしたら連絡を取らせてもらうかもしれないと、真也から携帯電話の番号を聞かれて、伝えたのだった。
『いきなりごめんなさい。この時間なら……キョーコさんの仕事も終わってるかなと思って。』
「あ、あ。はい、はい、終わってます、が」
『もう、おうち……ですか?』
「…ぇ、と…………………家ではない…………です。」
『そうですか………………。あの、ほんとうに突然電話したりしてすみません。』
「い、いえ、曲作りで……何か?」
『……ええ、まあ。……確かに曲を作っていたはいたんですけど…………。…………そしたら…………どうしても………どうしても、キョーコさんの…声を聞きたくなってしまって。』
「…へっ。」
『…………………………………………。』
「…………ぁ、の、」
『〰〰っ〰〰あ〰〰〰!!!なんかほんとすみません!こんなこといきなり!!』
真也の、テンパッたような大きな声が携帯から飛び出す。
「い、いえ、」
『キョーコさんのことを思い浮かべていたら、もう我慢ができなくて。なんかもう勢いだけで、』
「……………………。」
『ふぅ。あ〰カッコ悪いッスね、俺。』
「そ、んな」
そんなことはないです、と言おうとした。でも、キョーコの喉は、声が張り付いてしまったようで言葉が出てこない。キョーコの思考は、グルグルと激しく渦巻いていた。カッコ悪いとか、いいとか、そんな、今をときめく売れっ子バンド『Hope』のギターさん相手に、当たり前のことだ、カッコいいに決まっている。いや、でも、そうでなくて。彼は今、そんなことを言っているのではなくて。だからと言って、でも、それを考えてしまうことは、彼の言わんとすることを勝手に解釈してしまうことになって、でもなんて図図しい…………………と考える傍ら、自分が背を向けている蓮のことが気になって仕方ない。…………そういえば、食器の音も何もしない。無音だ。
『キョーコさん。』
「……あ、は、は、はいっ?」
『声…………聞けて嬉しかった、です。すごく。』
「……………………ぁ、ぇと、」
『また、…………また、連絡します!おやすみなさい!』
「っぁ、」
キョーコは、自分が何を言おうとしたのかわからなかった。ただ、なんだか慌てたままで、言葉にならない小さい音を発して。でも、通話は既に切れていた。
気づけば、携帯電話を強い力で握りこんでいた。どんな顔で後ろを振り返ればいいのかわからない。
蓮には、真也の声は聞こえていなかったはずだ。ただ、会話中のキョーコの言葉はとにもかくにも不自然過ぎただろう。どうしようどうしようどうしたら?、というのが、キョーコの今の間違いのない心境だった。
「お疲れ。」
「ふぇっ?」
蓮の柔らかな声に、キョーコは驚いて振り返る。
「通話の邪魔になるかなと思って静かにしてたんだ。さ、片付けの続きをしよ?」
「あ…………あ、そうか、そうでした……!私が廊下に行っておけば、「ダメだよ。」」
「っへ?」
「それはダメ。」
ふと、蓮の目に、翳りのある光が灯る。
「…………っ。」
キョーコは、その光に怯んだ。
「『どうして?』ってなるよ?『なんでわざわざ俺の視界から消えて、俺が聞こえない所に行くの?』、って。」
「…………っえ!、違っ、私、違っ、」
「…………なら、いいじゃないか。…………今度からも、それで。」
「……………………つるがさん、」
「俺の前で堂々と話したらいい。………キョーコちゃんにやましいところが無いのなら。」
「あ、ない、です。私、ないです。だ、から、だからっ、怒らないで………嫌いにならな「やめよう!」」
「…………ぇ?」
「この話はもうやめよう。せっかくキョーコちゃんと二人の時間を過ごしているんだ。俺はこんな話がしたいわけじゃない。」
少し苦しそうに眉をひそめる蓮に、キョーコも、コクコクッと頷く。ぎこちない空気のままではあったが、二人は片付けを再開した。各々目の前の作業をこなし、片付けはすぐさまゴールを迎えるかに見えた。ただし、精神状態はとても常のようにはいっていなかった。お互いにモヤモヤとしたものを抱え込んで、作業に集中などできていなかったのだ。だから、常ならばキョーコは手が届かないと蓮の力を借りる高所へのアプローチを自分でしてしまった。この空気はなんだか声がかけづらい、と思ったキョーコ。背伸びをして、無理矢理にサランラップのストックの箱を取ろうとしたのがいけなかった。キョーコが力の限りに伸ばしたその指先は、サランラップの箱を下から掬い上げたものの確実に捉えきれない。その箱はそのまま真下にあった、調味料を加えて冷ましていた出汁が入ったボールのど真ん中に落下した。その後の惨状は言わずもがな。出汁まみれのキョーコは、ただひたすらに蓮に謝って、オシャレなシステムキッチンが醤油のシミで染まりませんようにと祈りながら清拭に勤しんだ。
「シャワー、浴びておいで。」
キッチンを拭き上げたあと、蓮は、落ち込むキョーコに、明るい口調でシャワーへ行くように提案した。恐縮しっぱなしのキョーコは気づかなかった。シャワーに誘導してくれた蓮の目が、獣のそれになっていることに。
キョーコは、重苦しい反省の念から思考の小部屋に入っていた。そのため、この状況はどうしたことだと気づいたのは、あの夜のように、またしてもシャワーが終わったあとだった。焦るキョーコに拍車をかけたのは、蓮が音も立てずに脱衣所に用意しておいてくれた、例の柔らかなトレーナーの存在だった。
インナーを含め、キョーコが先程脱いだ衣類は前例の如く無くなっており、そこにあるのはトレーナーのみ。
キョーコはそのトレーナーを身に纏うことを、今度は前回と違う意味で躊躇した。敦賀′sトレーナー&ノーブラ&ノーPANという出立ちで脱衣所を出ていくことを。それすなわち、キョーコが未知の世界へ踏み込むことを意味する。
蓮と付き合いはじめて4ヶ月近くがたった。その間に、全く何も無かったわけではない。それらしいお誘いを蓮から匂わされたこともあった。しかし、キョーコの体に月のものが来ていたり、二人の仕事の都合が合わなかったりと、実際は行為に至ることはなかったのだ。
これを着て出ていけば、蓮からのお誘いに「諾」で、応えることになる。
蓮を。あの大きな身体の重みを、あの熱い掌を、あの柔らかな唇を、この全身で受け止める。それはきっと…、すごく恥ずかしくて、きっと…すごくすごく痛いこと…………らしい。
でも、でも、それよりも……………………きっと、きっと。
キョーコは、キュッと唇を結んで、そのトレーナーをゆっくりと手に取った。
「今夜は、その中…………見たいな………。」
トレーナー一枚で廊下に出たキョーコは、低く甘い声にハッと振り返る。そこには、あの夜と同じ、シャワーから出たばかりの蓮が立っていた。
「…………っ!」
キョーコは、体が強張っていくのを自覚する。蓮の圧倒的な、獰猛過ぎる雰囲気にのまれたのだ。
「…………だめ…………?」
「……………………っぇと…………。」
「嫌…………?」
「い、や、じゃ、な…………ぃ……です……け、ど…………。」
「触り、たい。」
「…………っ。」
「それ……以外にも……色々したい。」
蓮の、ごくり、と唾液を嚥下する音が、静かな廊下に異様な程に響いた。
「んやああぁぁっっ!」
キョーコの両肩を掴んだ蓮が、キョーコの耳朶にかぶりつき舌を捩じ込んだ。キョーコは、その激しい感触に、悲鳴に近い声を上げる。
「はあっ、キョーコ…………キョーコ…………。」
荒い息のまま、全身でキョーコに絡み付く蓮。
「ひゃっ!?、つ、めたっ」
その蓮の、濡れた髪がキョーコに触れて、キョーコは、驚きの声を上げた。
「あ、あ。そう、だった、ごめん。キョーコに優しくしたいから、少し落ち着きたくて、仕上げに冷水浴びてきたんだった。冷たかったね、ごめん。」
申し訳なさそうに、蓮はそっとキョーコから離れる。
「………ぇっ、かっ風邪、ひき、ませんっか?」
「俺は大丈夫…………。でも…………ほんと、ごめん………。色々…………ごめん。」
蓮は、キョーコを怖がらせないように自らを押さえようと努めてはいる。でも、キョーコが欲しくてたまらないという雄の本能がどうしても大き過すぎた。
キョーコは、不安げに蓮を見上げたままだ。
「キョーコちゃんを好きだって部分の本能は……もう押さえるつもりなんてないんだけど…………こっちの方までってのは、俺の身勝手だよね。…………本能剥き出しで…………君に、怖い想いをさせた……。」
ふーっと長く息を吐いて視線をずらす蓮に、キョーコは、目を瞬かせると、それはそれは赤くなって、ポツポツと小さい声で話した。
「違っ、違います、よ…………。」
「…………ぇ…………?」
「大好きな人を、求める本能が、あるのは…………本能が強い、のは…………男の人、だけじゃないです…………。」
キョーコは、そろり、と蓮の胸元に手を置いた。
それを合図にしたかのように、蓮は、キョーコの唇に深く己の唇を被せる。
キョーコは、蓮から与えられる濃厚なキスに呼吸がうまくできない。朦朧としてその場に崩れ落ちかけたが、そのまま蓮に抱えられる。
「できるだけ、優しくするから。」
掠れた声でそう呟いた蓮は、キョーコを抱いたまま寝室に消えていった。