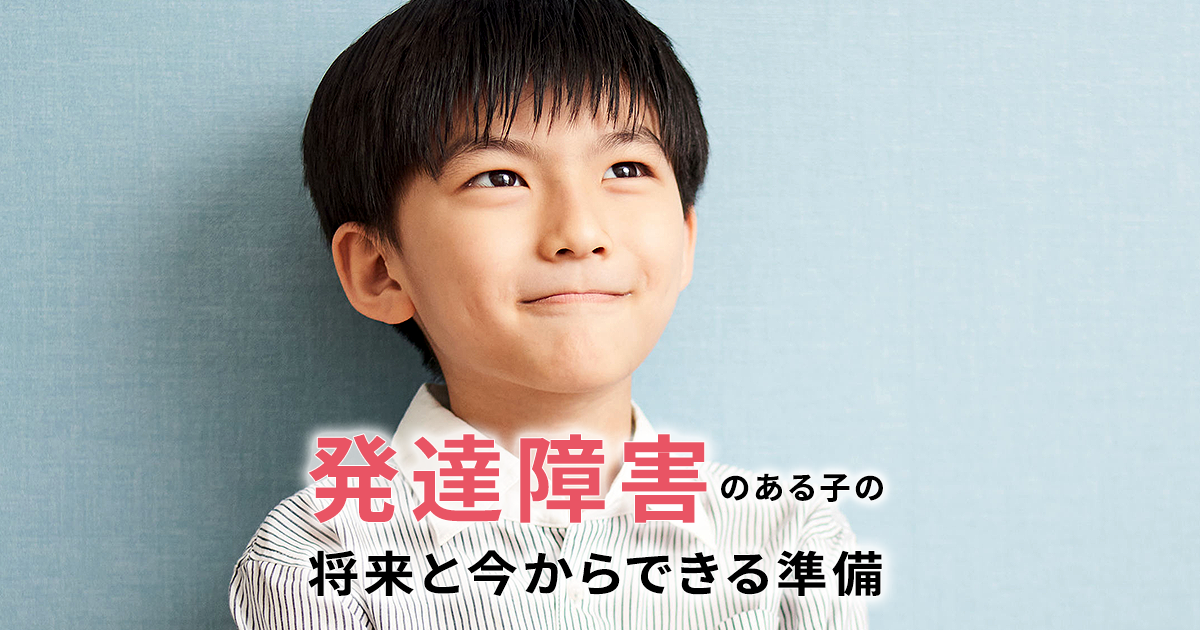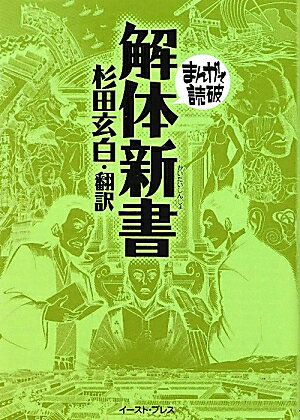こんにちは、凸凹君のママです。
最近、(発達)障害児育児をされている方のブログで「うちの子は小さい頃こんな感じでした!」という記事をいくつか見かけたので、私も少し昔話をしてみようかなと思います。
※素人の私が実際に感じたこと、見聞きした範囲の話です。


と、その前に。
「発達障害もどき」とか「発達障害と間違われる」といった表現のある記事を、最近よく見かけます。
「もどき」というと自主的にそう振舞っているように聞こえてしまいますが、「間違われる」と同じで本当は発達障害ではないという意味ですよね。
実際に発達障害の人と関わったことがあると、定型との違いは(嫌でも)肌で感じると思いますが・・・![]()
ある意味、発達障害という言葉の認知度が上がった結果でしょうか。
言葉だけ、ね。
こういった記事は、誰に向けて書かれているのかな?と思うことがあります。
子どもの発達障害を疑われたけれど、それを否定したい層なのかな?なんて思ったり。
認知度が上がり気にする人が増えたのか、兆候や傾向を示したセルフチェックリストのようなものが、本でもネットでもたくさん出回っています。
あれを見て、当てはまっていると落胆したり、違うところを数えて安心したりするのでしょうか。
こういうやつね
とか言って、もちろん私も試してみたことがありますよ!
ウチの場合、パパは大人のASDのセルフチェックに結構当てはまります(笑)
ところが、小さい頃の凸凹君はチェックリストにはほとんど該当せず、外では特に困りごともないと判断され健診でも一切指摘されませんでした。
たしかに特性がある子の多くに共通する傾向というのは、あるのだろうと思います。
でも、当てはまったからといって、必ずしも発達障害と診断されるとは限りません。
そして、当てはまらないからといって、発達障害じゃない! ・・・ではないんですよね。
特に乳幼児期は判断し難いところもあります。
チェックリストは、代表的な傾向が見られる場合は有効でしょう。
可能性に気付き、受診につながるケースもあると思います。ただ「発達障害」とまとめてしまっていると、当てはまらない項目も多くなり変な否定材料になりかねないなと思ってしまいます。
一方で、チェックリストに全然該当しないような、気付かれにくいタイプの子も確実にいます。
傾向を判断するには、複合・併発の影響も考慮する必要があると思うのですが、そういったパターンを網羅するようなチェックにはなっていないからというのもあるでしょうね。
チェックリストに引っかからない子は、周囲からの指摘もされない(遅れる)可能性が高いと思います。
なぜなら、指摘する側(園や学校の先生等)もそういうチェックリストに代表されるような傾向の有無で判断している部分が大きいと思われるからです。
凸凹君の場合がそうでした。
幼稚園では「この子が発達障害なんてありえないですよ、ママさん!」と完全否定されるくらいでした。
沢山の子どもを見てきている先生はそれなりにプロの目を持っていると、素人である保護者側は思っています。
そのプロから否定されると、それで安心を得る人もいるでしょう。
でも。
その子が本当に発達障害だった時、責任を取ってくれるわけではありません。
対応が遅れ、大きな問題が起きてから慌てて医療につながろうとするも初診は半年待ち、その間に状況悪化、本人の自己肯定感もダダ下がり・・・なんてケースもあるようです。
発達障害でない人が発達障害と誤診されるのも、発達障害の人が発達障害と診断してもらえないのも、どちらも本人の為にはならないと思います。
チェックリストも必要かもしれませんが、それ以上に本人や周囲に困りごとがないかに気を配って見ることが大事かなと、今振り返って思っています。
ということで、もしかしたら誰かの参考になるかもしれないしならないかもしれないけど、チェックリストによくある傾向とこれまでの凸凹君の成長を比較してみようと思います。
前置き長いね(笑)
(つづく)
発達障害児の傾向 次の記事
凸凹君が夏休みに読んだ本 41