このコーナーの文章を転用する場合は、
「邦楽ジャーナルHPより転載(執筆=○○)」とご記載ください.
写真の無断転載はご遠慮ください。
邦楽ジャーナルのHPは http://www.hogaku.com/ からどうぞ!
「邦楽ジャーナル」は下記を手掛けています。
1.日本の古典音楽、民俗芸能、和楽器を使ったジャズ、ポップス、
ロックなどを扱った月刊情報誌 「邦楽ジャーナル」の発行
2.楽譜・単行本などの発行
3.CDや関連書籍などの通信販売「純邦楽CDショップHOW」の運営
4.ワークショップやイベントの企画・制作
「邦楽ジャーナルHPより転載(執筆=○○)」とご記載ください.
写真の無断転載はご遠慮ください。
邦楽ジャーナルのHPは http://www.hogaku.com/ からどうぞ!
「邦楽ジャーナル」は下記を手掛けています。
1.日本の古典音楽、民俗芸能、和楽器を使ったジャズ、ポップス、
ロックなどを扱った月刊情報誌 「邦楽ジャーナル」の発行
2.楽譜・単行本などの発行
3.CDや関連書籍などの通信販売「純邦楽CDショップHOW」の運営
4.ワークショップやイベントの企画・制作
こんなCD、いかがですか?
ここでご紹介するCD・DVDを聴いてみたいと思われた方は、「純邦楽CDショップHOW」でご注文を。邦楽ジャーナルのCDショップでは1500タイトルのCD・DVDを扱っています。お電話・ファックスならCDタイトルあるいは[HOW取扱No]を おっしゃってください。お時間がおありの方は邦楽ジャーナルにお越しいただき、視聴コーナーをご利用ください。
これならわかる! 邦楽のいろいろ
「邦楽を知りたい、と思っても、どこにいって何を聞けばいいのか迷う。CDもたくさんあってわけが分からない。三味線と言ったって、津軽三味線だけではなく長唄三味線とか新内三味線などあるらしい」そんな方にはまず、邦楽にはどういうジャンルがあるのかを知っていただきましょう。

「日本音楽まるかじり」は2枚組で雅楽、声明、箏、琵琶、沖縄音楽、アイヌ音楽、現代音楽などの名曲のおいしいところを名人の演奏で2、3分ずつ収録しています。全60曲。解説書も充実しています。あなたに合ったジャンルをみつけて、そこから出発してみては? 3,000円!
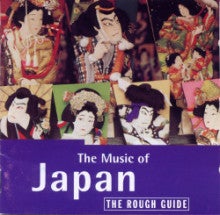
「伝統音楽じゃなくて、もっと楽しい今の邦楽が聞きたい」そんな方にお薦めするのが
「THE ROUGH GUIDE TO THE MUSIC OF JAPAN」日本の音楽のラフガイドです。外国人が「これこそ今のエネルギーある日本の音楽」と選んだ奏者は民謡の伊藤多喜雄、浪曲の国本武春、河内音頭の河内屋菊水丸等々全部で19人(組)。現代音楽も入るという、自由なセンスが魅力です。日本語の解説、ついてます。2,300円!
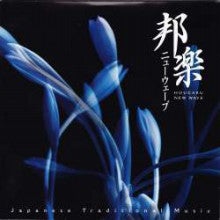
「邦楽ニューウェーブ」も今の邦楽を聞いてもらうCDです。「THE ROUGH GUIDE」と比べると、もうちょっといろんな楽器の音色が聞けます。吉田兄弟の津軽三味線もあれば、琵琶と尺八で祇園精舎、箏で現代邦楽やオリジナルポップス、雅楽の響きも聞ければ、能管とベースのセッション、太鼓とドラムの共演等々11曲。解説は邦J編集長ほか。2,5250円!
これならわかる! 邦楽のいろいろ
「邦楽を知りたい、と思っても、どこにいって何を聞けばいいのか迷う。CDもたくさんあってわけが分からない。三味線と言ったって、津軽三味線だけではなく長唄三味線とか新内三味線などあるらしい」そんな方にはまず、邦楽にはどういうジャンルがあるのかを知っていただきましょう。

「日本音楽まるかじり」は2枚組で雅楽、声明、箏、琵琶、沖縄音楽、アイヌ音楽、現代音楽などの名曲のおいしいところを名人の演奏で2、3分ずつ収録しています。全60曲。解説書も充実しています。あなたに合ったジャンルをみつけて、そこから出発してみては? 3,000円!
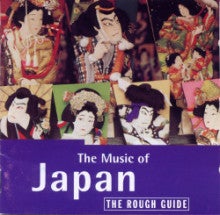
「伝統音楽じゃなくて、もっと楽しい今の邦楽が聞きたい」そんな方にお薦めするのが
「THE ROUGH GUIDE TO THE MUSIC OF JAPAN」日本の音楽のラフガイドです。外国人が「これこそ今のエネルギーある日本の音楽」と選んだ奏者は民謡の伊藤多喜雄、浪曲の国本武春、河内音頭の河内屋菊水丸等々全部で19人(組)。現代音楽も入るという、自由なセンスが魅力です。日本語の解説、ついてます。2,300円!
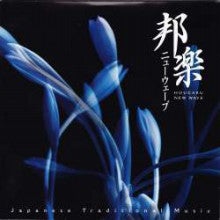
「邦楽ニューウェーブ」も今の邦楽を聞いてもらうCDです。「THE ROUGH GUIDE」と比べると、もうちょっといろんな楽器の音色が聞けます。吉田兄弟の津軽三味線もあれば、琵琶と尺八で祇園精舎、箏で現代邦楽やオリジナルポップス、雅楽の響きも聞ければ、能管とベースのセッション、太鼓とドラムの共演等々11曲。解説は邦J編集長ほか。2,5250円!
邦楽器ってどんな楽器?
邦楽とひとくちに言っても雅楽から歌謡曲まで幅広いものです。あるアンケートで「邦楽」で想像する音楽を聞いたものがありました。結果は「J-POP」が50%以上。以前、「邦楽専門のライブハウス!」といううたい文句で「和音」という店を開業していたことがあるのですが、店長募集の広告を出すと、「J-POP」指向の人が応募して来ました。お門違いではあったわけですが、店長になってもらうと、その人はこちらの「邦楽」に興味を示し始めました。「こんな世界があったんだ!」。そう、こちらの「邦楽」はあまりに知られていないんですね! 楽器もそのすぐれた性能が知られていない。なんてもったいないことだろうと思います。
ここでは邦楽器にスポットをあてて、楽器の構造や奏法解説というより、邦楽器の魅力や楽しさ、こぼれ話をお届けしたいと思います。
邦楽ジャーナル編集長・田中隆文
ここでは邦楽器にスポットをあてて、楽器の構造や奏法解説というより、邦楽器の魅力や楽しさ、こぼれ話をお届けしたいと思います。
邦楽ジャーナル編集長・田中隆文
第4話 太鼓

太鼓
これも日本の伝統ある楽器です。特に世界に類を見ない大太鼓は、その重低音大音量で私達を魅了します。一打入魂の世界は日本の伝統的精神性を感じさせます。また、太鼓集団が大きな身振りで大小様々な太鼓を打ち鳴らす様は見ていて壮観です。でも、こんなスタイルが広まったのは、まだ半世紀前のことなのです。
他の楽器の伴奏というのではなく、太鼓自体が主役となるこのスタイルは、1950年代に長野で小口大八が御諏訪太鼓を復活する際に考え出したといわれています。71年には佐渡で田耕(でんたがやす)率いる鬼太鼓座(おんでこざ)が誕生しました。民俗芸能だけでなく、現代音楽とも結びつき、76年にボストン交響楽団と初演した石井眞木作曲『日本太鼓とオーケストラのためのモノプリズム』(小澤征爾指揮)は音楽界に大きな衝撃を与え、また、太鼓が世界に知られるきっかけともなりました。
創作和太鼓のプロ集団は次々に生まれ、また、鬼太鼓座や分裂した鼓童から独立した奏者がまた新しいスタイルを作り出しています。近年では、太鼓はあらゆる音楽のジャンルに登場し、様々な楽器や歌と自由に共演しています。プロではなく、アマチュアの組太鼓チームも、全国の市町村にないところはないというくらい普及しており、その数、1万とも3万とも言われています。町おこしにもってこいの素材だったようで、竹下総理の「ふるさと創生」でも、1億円を太鼓に使ったところが多かったと聞いています。
太鼓の歴史をひもとけば縄文時代にさかのぼります。情報伝達の重要な道具だったようです。それから雅楽や民俗芸能、歌舞伎の下座音楽、能や神楽の囃子など様々に使われてきたことは周知の事実です。種類は長胴太鼓、桶胴太鼓、締太鼓といろいろですが、現代の組太鼓の音楽は、そんな伝統に根ざしていることは間違いありません。古くて新しい音楽、それが太鼓なのです。
ちなみに、創作太鼓の打ち手の格好が半纏・股引が多いのはどうしてか、ご存じですか? 映画「無法松の一生」の影響ということです。祭で見事なバチさばきをみせた松五郎は車夫だったのです。(写真・文=田中隆文)
第3話 琵琶

琵琶
琵琶と聞いてなにを想像しますか? 耳なし芳一? 平家物語? 古い物語をソロで弾き語るイメージがおありでしょう。そうです。箏や尺八と違って(基本的に)合奏をしません。ですが、鶴田錦史が登場し、1967年、武満徹作曲『ノヴェンバー・ステップス』を尺八の横山勝也とともにニューヨークフィル(小沢征爾指揮)と共演して以来、器楽としての琵琶にも注目が集まりました。あのサワリ(ビビリ音)のついた音、バチで思い切り板面を叩く音、絃をこする音など、洋の東西を問わずあまり聞けるものではありません。
しかし、琵琶の起源をたどれば、遠く中東に行き着きます。イラクやトルコの楽器ウードの前身が西に渡ってリュートやギターとなり、東に渡って中国でピパとなり、日本には中国から7、8世紀にもたらされたと言われています。当時の美しい琵琶が2009年秋、奈良国立博物館で紫檀木画槽琵琶(したんもくがそうのびわ)、東京国立博物館で螺鈿紫檀阮咸(らでんしたんのげんかん)(円形の胴)で展示されました。ともに正倉院宝物で、来場者の一番人気の展示となっていました。優雅な琵琶を見ながら古人(いにしえびと)に思いを馳せてみるのもいいものです。
琵琶には雅楽の琵琶、盲僧琵琶、平家琵琶、薩摩琵琶、筑前琵琶などがありますが、現在一般に使われているのは男性的な薩摩琵琶と女性的な筑前琵琶です。構え方や絃の数、フレットの数が4つあるいは5つとそれぞれで違っていて、どれが正しいというものではありません。鶴田錦史は薩摩琵琶を大胆に改良しています。琵琶の表面には分からないように孔が3つあいています。機会があれば見つけてみてください。
日本を代表する楽器は三味線ですが、実は琵琶法師が16世紀に大阪の堺に入って来た三線(さんしん)を改良したものと言われています。だから、三味線はバチで弾き、サワリという、音をビリつかせる工夫も施されました。
戦前にはまだ、特に西日本では一般家庭に浸透していた琵琶ですが、軍記物のレパートリーが合わなかったせいか戦後は急速にすたれていきました。琵琶専門店は全国に1軒しかありません。それでもどんどん新しい弾き手が生まれてきて、その幽玄の音色を聞かせてくれます。一度琵琶を構えて、バシッっと音を出してみてください。その振動が身体に伝わり、なんとも心地よいものですよ。(写真・文=田中隆文)
第2話 箏(こと)
 (写真=肥田木智子)
(写真=肥田木智子)箏(こと)
巷では「琴」という字を多く見かけますが、本来は「箏」です。戦後、常用漢字というものを制定してそこに「箏」が入らなかったが故に「琴」で代用したんですね。昔は「こと」とは絃楽器の総称であって「琴(きん)のこと」「箏(そう)のこと」「琵琶のこと」などと言っていたようです。だから、琴と箏は違う楽器で、桐の胴体に13本の絃を張って柱の移動で音階を定める長さ180cmの楽器は、「箏」の方なのです。今では小中学校でも「箏」の字を使っていますが、「そう」と読ませています。今度は「こと」という読みがないんですね。混乱甚だしいのが現状です。
箏はお正月の『春の海』で有名です。ご存じ宮城道雄が昭和4年に作曲しました。宮城はベース箏「十七絃箏」を開発し、洋楽の手法を取り入れた作品を次々に発表して、箏を座敷から、洋楽のようにステージ上げました。そして一世を風靡しました。戦後、洋楽系作曲家もアイデンティティの確立とばかり、邦楽器を用いた作品を書くようになりますが、多用されたのが箏でした。オーケストラとも共演する宮城の実績もあったし、愛好人口も伝統邦楽のなかでは一番多い(つまり人気の楽器)。なにより調弦が自由(ドレミにも並べられる)で、音色も現代にとけ込みやすかったからでしょう。1960年代に花開いた現代邦楽の立役者で、絃の数が21本そして25本と増えた箏も現れました(30絃もある)。それによる和音の構成や音の響きも新しいものになっています。
普通の13絃の箏も昔と比べるとずいぶん変化しています。なにより絃が絹からテトロンに変わり、それを強く張ることで、音量の増大とアップテンポの曲に対応出来るようになりました。それでも、古典が基本としてすべての箏曲家に受け継がれています。
箏は奈良時代に中国から伝わったものですが、今聞かれる箏曲(そうきょく)は江戸時代の八橋検校からはじまります。調子(音階)を工夫し、歌の伴奏だけではなく例えば『六段の調』といった各段の拍数を合わせた純粋器楽曲も作っています。八橋が亡くなった1685年にバッハが生まれているわけで、その当時すでに高度な音楽が存在していたことがお分かりいただけると思います。箏はやがて三味線や胡弓と結びつき、地歌と呼ばれる三味線歌曲をレパートリーにしていきます。地歌は曲の途中で調子を変えることも多く、箏は柱を動かしてそれに対応します。そういう行為を伴う音楽は世界にそうあるものではありません。箏は尺八とも合奏するようになり、明治を迎え、発展していきました。
2010年3月(予定)、宇宙飛行士・山崎直子さんがスペースシャトルに搭乗しますが、彼女の趣味はお箏。ということで、宇宙用の箏を持って行くかもしれません。宇宙から箏の音色…昔の人だったら驚くことでしょう。(田中隆文)
