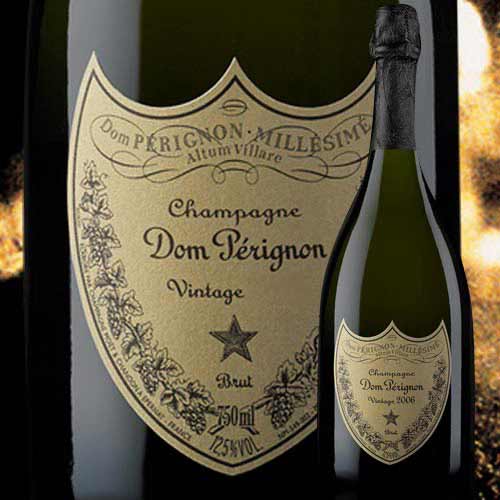シャンパンといえば、第一に浮かんでくるのはシャンパン「ドンペリ」でしょう。
有名な人物ドン・ピエール・ペリニョンに敬意を評して造られたシャンパンです。
第9回はそのドン・ ピエール・ペリニヨン(その1)についてです。
チャレンジしてみて下さい。
ℚ1.ドン・ ピエール・ペリニヨンの「ドン」とはどういう意味でしょうか?
① ファーストネーム(姓名の名)
② カトリック修道士の尊称
③ カトリック・ベネティクト会の「親」
④ 独身
ℚ2.ドン・ ピエール・ペリニヨンとは、どんな人物だったでしょうか?誤っているものを選んで下さい。
① 幼いころからブドウ畑での収獲やワイン作りに親しんで育った。
② シャンパーニュ地方に生まれ、兄弟が多く17歳にして修道院に入った。
③ カトリックの厳格な戒律が嫌いで、ワイン造りの担当者となった。
④ 30歳にして醸造責任者となり47年間良いワイン造りに勤しんだ。
ℚ3.ドン・ ピエール・ペリニヨンのワインに関する歩みのうち、誤っているものを選んで下さい。
① 早春に剪定する、涼しい朝のうちにブドウを摘むなど、ブドウ栽培で革新的な考えを実践した。
② 黒葡萄から白ワインを造る圧搾方法を生み出した。
③ 鋭い感覚の持ち主でアッサンブラージュを行い、バランスのとれたワインを造り出した。
④ 生涯、発泡性ワインを探求し、人工的な発泡性ワインが造ることに成功した。
ℚ4.ドンペリの時代の様子について、誤っているものを選んで下さい。
① シャンパーニュのワインは自然に泡のたつワインだった。
② ミサや民衆の間でも好んで飲まれていたのは赤ワインでなく泡立つワインだった。
③ ドンペリは白ブドウでなく黒ブドウを使ってワイン造りをしていた。
④ ドンペリはシャンパーニュ地方で初めてコルク栓を使用した。
如何でしょうか?
答えは、
ℚ1:② カトリック修道士の尊称
ℚ2:③ カトリックの厳格な戒律が嫌いで、ワイン造りの担当者となった。
ℚ3:④ 生涯、発泡性ワインを探求し、人工的な発泡性ワインが造ることに成功した。
ℚ4:② ミサや民衆の間でも好んで飲まれていたのは赤ワインでなく泡立つワインだった。
【解説】
ドン・ ピエール・ペリニヨンは1639年にシャンパーニュ地方サント・メニュールドに生まれ、子供の頃からブドウ畑で収穫を手伝うなど、ワイン作りに親しんで育ちました。7人も兄弟がいた彼は17歳で修道院に入り、オーヴィレール修道院には19歳の時に移り、30歳にして彼醸造責任者として修道院の再建に乗り出しました。
その柱はブドウ畑の復興で、47年にわたり大変な労力を要しました。
彼がブドウ栽培で成し遂げた「ワイン造りの黄金律」は、次のような当時としては革新的な考えでした。
・最良のブドウだけを使う。
・実の付き過ぎるのを防ぐため早春に剪定する。
・涼しい朝のうちにブドウを摘む。
・皮の破れたものは捨てる
また、ワイン製造について、彼は、ブドウは優しく圧搾し、黒葡萄から白ワインを造る圧搾方法を生み出しました。また、絞った果汁は各圧搾ごとに別々に保管し、鋭い感覚でアッサンブラージュを行い完璧な調和とバランスのとれたワインを造り出していました。
ドンペリの時代、シャンパーニュのワインは自然に泡のたつワイン、意図せず泡立つワインでした。この泡立つワインはミサ用には受け入れられなく、民衆にも歓迎されていませんでした。
そして、彼はシャンパーニュ地方で初めてコルク栓を使用しました。それまでは油をしみこませた麻の繊維でくるんだ木の栓を使用していましたが、コルクを使用することで、良いワイン、良い発泡性ワインの製造、貯蔵、運搬に大きく貢献しました。
ご興味のある方は、「ドン・ ピエール・ペリニヨンはシャンパンの先駆者?・・・シャンパンのそうだったのか!⑨」⇒こちらをご覧ください。
詳しく解説しています。