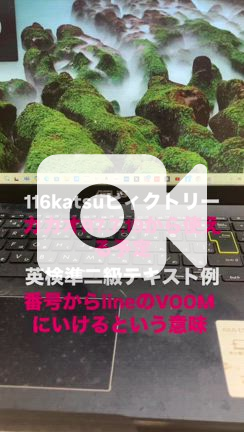16katsuビィクトリーのホンマです。
前回、「デジハラ(デジタルハラスメント)」は“通知やチャットを使った圧力”のことだと書いた。
今回はもう少しリアルな話をしていく。
まず職場だと、いちばん多いのは勤務時間外のチャット・メール。
「すぐ返さなくていいよ」と言いつつ、既読スルーだと翌朝に「昨日見た?」って聞かれる。
こういうの、軽く見られがちだけど、立派なデジハラ。
会社がリモートやオンライン化を進めるほど、増えていく傾向がある。
次に多いのがSNS絡みのハラスメント。
上司が部下をフォローして、投稿に口を出したり、逆に「フォローして」と強要したり。
これも明らかにプライベートの領域に踏み込んでる。
学生なら「先生が生徒のアカウントを見て注意する」とか、家庭でも「恋人や親がLINEを監視する」なんて話もよく聞く
どれも“つながること”が前提の時代だからこそ、断りにくいのが厄介だ。
じゃあ、どうすれば防げるか。
俺が思うに、まず大事なのは自分の中で線を引くこと。
仕事用とプライベート用でアカウントを分けるとか、通知を切る時間を決める。
たとえば「夜10時以降は業務チャットを見ない」とか、スマホ設定で“集中モード”を使うのもあり。
習慣にすれば、周りも自然と理解してくれる。
それでも止まらない場合は、証拠を残す。
チャット履歴やスクリーンショットは、そのまま行為の記録になる。
会社ならハラスメント窓口に、学校なら先生や保護者に相談。
身近に頼れる人がいないときは、労働相談センターや自治体の窓口もある。
「たかがLINE」じゃなく、「これもハラスメントの一形態」として扱われる時代になってきている。
そしてもう一つ。
自分が“やる側”になっていないかも気をつけたい。
無意識に「返事まだ?」「なんで既読なのに?」なんて言葉を使っていないか。
それが相手のストレスになっていることもある。
デジハラは、悪意よりも“無意識”から始まることが多い。
だからこそ、意識してブレーキをかけることが大事だ。
デジタルの距離感が保てる人ほど、信頼される時代。
次に誰かにメッセージを送るとき、ちょっとだけ立ち止まって考えてみよう。