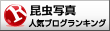楽しかったアゲハの幼虫の飼育ですが
もうこの時期ですので、羽化は来春ですね
今4匹ほどアオスジアゲハの幼虫が残っていますが
先日アゲハの幼虫がすべて蛹になりました。
砲シリーズで蛹の様子をご覧になっていると思います
綺麗に割り箸に蛹がついていると思いますが
これは、
私が幼虫の飼育中にしっかり躾をしてるわけでもなく
そうなるように、上手く幼虫を誘導しているわけでもなく
幼虫は自由に好きなところで蛹になっております
蛹化後、私が取り外して割り箸に貼り付けているのですね
今回はその手順をお見せしようと思います
まず、このように
プラスチックの飼育箱の側面で蛹になっていますね
この場合だとアゲハチョウはプラスチックの壁は登れないので
羽化した時に登って翅を広げることができず
落下してしまったり、羽化不全になってしまいますので
ちゃんと登って翅を広げれるように手を加えてあげる必要があります
方法としては
蛹の上部と側面にキッチンペーパーなどを貼ってあげて足場を作ってあげる方法
と
蛹を取り外して、割り箸などの棒に付け直す方法
があります。
蛹を取り外した場合のその蛹をどうするかの方法としては
紙で円錐状のポケットを作ってあげて、そこに蛹を入れて割り箸などの棒に貼り付ける方法
蛹を直接割り箸などの棒に貼り付ける方法があります。
それを応用した色々方法があったりもするのですが
今回は私が採用しておりますその一例である。
蛹を直接割り箸の貼り付ける方法を解説したいと思います
まず、
蛹の取り外し方
取り外すのは蛹になってすぐではなく、2、3日経って蛹がしっかり固まってから作業します
では、まず
このように、蛹の下から5mm程度の所にセロテープを貼ります
それを、そっと、ゆっくり剥がします
元気の良い蛹だと、お尻をキュンキュンさせて嫌々しますので
蛹に負担を掛けないように、途中で止めたりして落ち着かせたりしながら、ゆっくりそっとそっと剥がします
幼虫は蛹を作る前に、しっかり周りに下地を作っているので
結構、すんなり綺麗に剥がれます
剥がれたら接着です。
接着する部分は1点
赤丸の部分
蛹の下から5mm弱くらいかな。
割り箸に
木工用ボンドを付けて
このように貼り付けます
接着剤は木工用のボンドが良いようですね
アロンアルファやセメダインのような石油系のまわりを溶かして接着するものは
駄目なようです。木工用ボンドなら確実です
ボンドが乾いて蛹が固定されたら
このように
前の部分を爪楊枝の先で支えている糸などを整え
爪楊枝の先にボンドを付け
要所を接着しながら、可能な限り元の姿に修復して
完成です。
前の部分の修復は、支える糸が破損したりする時もありますが
アゲハ、キアゲハの蛹だったら、小さいので下の接着した部分だけで大丈夫です
クロアゲハ、ナガサキアゲハ、オナガアゲハなど大きい蛹は
前の部分が上手く修復できなく、立ててみて、だらーんとして安定しなかったら
紙をテープ状に切ってお腹の部分に一巻きして補助してあげれば良いと思います
こういった作業の前提として、羽化の時、どのように出てくるか
知っておく必要がありますね
このように出てきます
作業してみて大丈夫かのチェックポイントは
以上のように出てこれるようになっているかですね
このように出てこられて、ちゃんと翅を伸ばす場所があるように
以上のような環境
(飼育箱の側面にキッチンペーパーを貼り足場を作り、そこに接するように蛹を立てる)
で蛹を保管すれば
健康な個体であれば、綺麗に正常に羽化して
綺麗な完璧な姿を見せてくれると思います。
せっかく幼虫を大事に育てて
健康上の理由でなく、事故で羽化不全させてしまうと
中々悲しいものがあります
しっかり羽化のプロセスや成虫の身体的な能力を知って
上手く環境を作っていくのが大切ですね
また、このプロセスや性質を調べたり、観察によって知ったりして
環境を作るのが飼育の楽しさだったりもするのですよね
蛹を剥がすのちょっと怖いと感じらる方もいると思いますが
やってみると簡単です
蛹は春から秋に賭けては約2週間
秋以降は翌春となりますので、そのままだとその間飼育箱を洗ったり使ったり出来なくなるのと
複数幼虫を飼育していると結構
なんだこりゃ?
(お前のもうじきそうなるんだよ!)
って、触ったり、突っついたり、またいだりします
読者様のブログで拝見してて、こんなこともあるのだ
と見ていたら、写真を撮り忘れたのですが、この間、
蛹の上に蛹になるというのをはじめて経験しました。
上手く分離させましたけど
蛹になったら、順次取り外していかないと、中々面倒くさいことになったりしますね
こうしておくと、蛹をまとめたり整理もできますしね
試されて頂ければと存じます
色々な蝶の幼虫を飼育して
モンシロチョウ、キタキチョウ、ヤマトシジミは
プラスチックの壁は登れるので蛹になっても
よほど変な体制だったり、場所だったりしなければそのままで大丈夫です
タテハチョウ科はぶら下がりなので、ちょっとまた対処の仕方が違いますね
チョウによって色々身体能力が違うのですね。