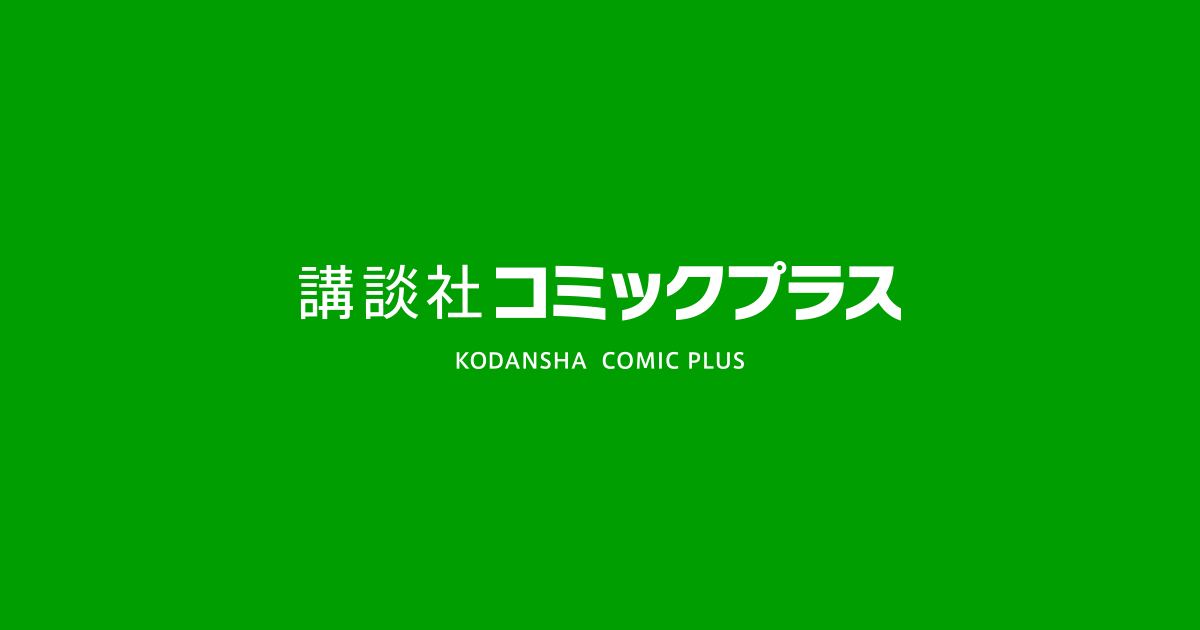昨今、二言目にはソレを言う人が多い。多いけれども、その割に、実際、目の前の人を、一人の人として認め、理解しようとしているかというと、ソコは、必ずしもそうではないなという・・・
6月は「プライド月間(Pride Month)」だそうで。
●「プライド」
「アタシを見て」「アタシを認めて」という叫びではあるのでしょう。「これこそがありのままのアタシ」とばかりに、それこそ「多様な姿」で闊歩する。
さらに、「“性”と“生”の多様性」を祝福する、なんて謳いながら、彼等・彼女等・どちらでもない彼の人等とともに、「いい人」気分で街を練り歩く。
正直、違和感しかない。
「そのままのアナタを受け入れますよ」と言うのは簡単。
言えば、それで全て解決したかのように錯覚もする。
本来複雑な人と人との関係をリアルに考えることなく、ラクして横着して、むしろ単純で平板な「みんな同じ」枠に押し込めようとしているだけ、のようにも思う。
現実に、生活の中で「共に在る」のは簡単じゃない。
何故って、それこそ「みんな違う」から。
●「LGBT(QIA+……)」
例えばLGBT。
多様性を認めようと言いながら、その実「LGBT」という枠で括っている。
LBGTに「Q」や「IA+」を加えようが、その他のアルファベットや記号をどこまでもどこまでも続けようが、つまり「塊」として扱っていることに変わりはない。
やいのやいのと騒いでいる人の多くが、本当に苦しんでいる人、生き辛さを感じている人と共にあるのかと凝視すれば、そんなわけないだろうと気付く。
真に共感しているのは極わずかで。
多くの人にとっては「私達」ではなく、「そういう人達と私」だ。
まして、運動とか活動とかの中心にいる人にとっては、ただ、利用しているだけ。
政治ビジネスだったり、医療ビジネスだったり。
であるからこそ、多様性についての「多様な意見」を認めようとしない。
人の繋がりを利用して圧力をかけ、無関係の人を巻き込んで脅迫もする。
●「トランスジェンダー」
そこら辺、せっかくなんで、例の本を再度紹介。
ヘイトではありません
ジェンダー思想と性自認による現実です
思春期に突然「性別違和」を訴える少女が西欧諸国で急増しているのはなぜか。
約200人、50家族を取材した著者が少女たちの流行の実態を明らかにする。米国ベストセラー『Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters』の邦訳版
「それまで違和感を覚えたことはなかったのに、学校やインターネットで過激なジェンダー思想に触れて傾倒した十代の少女たちがもてはやされている。そうした少女たちの後押しをしているのは、同世代の仲間たちのみならず、セラピスト、教師、インターネット上の著名人たちだ。だが、そんな若さゆえの暴走の代償はピアスの穴やタトゥーではない。肉体のおよそ四五〇グラムもの切除だ。(中略)いわばフォロワーになっただけの思春期の少女たちに、そのような高い代償を払わせるわけにはいかない」(「はじめに」より)
本書への賛辞
はじめに 伝染
1 少女たち
2 謎
3 インフルエンサー
4 学校
5 ママとパパ
6 精神科医
7 反対派
8 格上げされたもの、格下げされたもの
9 身体の改造
10 後悔
11 あと戻り
おわりに その後
謝辞
解説 岩波明
原注・参考文献
という目次なのですが、「11 あと戻り」から、バック・エンジェルというトランス男性57歳の言葉を引きます。
ちなみに、〈バックは、ロサンゼルスで最初に女性から男性へ医療措置で性別移行したトランスセクシャルのひとりだ。1991年にテストステロンの投与を受けはじめた。最終的に、トップ手術と陰核陰茎形成術を受け、すべての処置に心から満足している〉とのことです。
同じ章から、著者自身の考えも。
過激な人々⎯⎯トランスジェンダーの場合も、そうでない場合も多いが⎯⎯が、ほんとうに苦しんでいる人々の戦いに乗じて、絶望しかけている若者たちが突発的な熱狂に巻きこまれているとの指摘を避難し、攻撃し、くつがえして封じこめようとしている。わたしが話を聞いた多くの大人のトランスジェンダーたちは、彼らのためにという名目で活動家たちが主張していることについて謝罪していた。そうした活動家たちが極端な急進派であることを忘れてはならない。(P.310)
どうでも良い話だけれども、この本、いつも利用している書店になかったので、オンライン書店【ホンヤクラブ】を利用して注文購入。したら、その後2冊ほど入荷したようで、入口近くに面陳されてます。どなたか、買ってあげて。
●「マイノリティ」という名前の人はいない
例えば、1万人に一人であれば「マイノリティ」に違いない。
けれど、それでさえ、日本全国1億人で考えれば1万人いるわけで。
その中で、たまたま聞こえてきた、あるいは、聞かされた「当事者の声」で、一体、何が分かると言うのか。
男も女もない小学生のうちから「性の多様性」を教えて何になると言うのか。
男も女もない⎯⎯正確には「分からない」と言うべきかも。だからこそ言葉でうまく説明できない「違和」は誰でも感じることがある。そういう子供達の「ちょっと変」に共感するのと、そしたら「あなたはトランスジェンダーなのよ」と結論を急ぐのとでは、大人としての姿勢に大きな違いがある。
残念なことに、世の中には、不安や恐怖、あるいは善意や良心に付け込む人、しかも、それをビジネスにして恥じない人が大勢いるのです。
会ったこともない抽象的な誰かのこと、ではなく、目の前に、名前を持った具体的な人が現れた時、自分が望み、相手も望む中で、目一杯悩めばそれで良いと思う。
おしまい。
ホント、一般論じゃ何も語れないなあと思う今日このごろです。
例えば「性同一性障害(GID: Gender Identity Disorder)」と「性別違和(Gender Dysphoria)」・「性別不合(Gender Incongruence)」。
場面や人の考え方によって、どれを使うのが「適切」なのか、そこさえ「多様な意見」があります。
こちら、けっこう前に出版されたものですが、ついうっかり購入してしまいました。
身体的にも法律的にも女性になるために、主人公・平沢ゆうなは性別適合手術(SRS)を受けにタイへと旅立つ。しかし、女性への道のりは想像していた以上に“痛かった”!! 性同一性障害(GID)当事者の作者が男性から女性になる過程を詳細に描いた実録エッセイ!
「あとがき」からの引用です。
〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜
さて、この『ぼくわた』ですが、不安だらけの連載準備でした。『ぼくわた』は私の体験談とはいえ、とてもデリケートなテーマです。このテーマの闇の深さを私は嫌というほど知っているのに、私なんかが描いていいのか、この言葉は適切なのか、この表現は誰かを傷つけやしないか・・・何もかもが手探りでした。
そうした逡巡と推敲を繰り返すうちに、私はこの漫画を、何を伝えるために描くのかを強く考えるようになっていきました。そして私は一つの考えにたどり着いたのです。
「私からは何も伝えないようにしよう」
性同一性障害に限らず、世間から風当たりの強い立場の人達は「私達を認めて!」と主張すればするほど、「認めてくれない人を認めない」という自己矛盾を回避できません。だから私は、「差別をやめよう!」「社会的にこうして欲しい!」という要求部分は終始、排除することにしたのです。辛い体験をしたとしても、それについて「かわいそう」と思うか「当たり前だろう」と思うかは自由に読めるように描いたつもりです(力不足だったところもあるかもしれませんが・・・)。
ただ、ひとつ、7話の最後に投げかけた問題提起・・・それだけがこの漫画のすべてです。
〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜
確かに、何か、こうしてほしい、そうなればいい、みたいなことはほとんど描かれていません。
それだけに、そこを声高に叫んでいる人達との立ち位置の違いが鮮明になるという。
ちなみに「7話の最後」には、こんな独白が綴られてました。
「性同一性障害(GID)なんだから仕方ないじゃない」
そう思う人もいるかもしれません
でも・・・・・・
私は最近思うんです
「障害(disorder)」って
何だろう・・・・・・?
「性別」って
何だろう?
「普通」って
何だろう?
この世界は
「普通」なのかな・・・
この世界は・・・・・・
「変」じゃないのかな・・・?
そう、実は「みんなちょっとずつ変」と。
これは、新海誠さん『言の葉の庭』に、よく似たセリフがありました。
また会うかもね。もしかしたら。雨が降ったら。
雨の朝、高校生の孝雄と、謎めいた年上の女性・雪野は出会った。雨と緑に彩られた一夏を描く青春小説。劇場アニメーション『言の葉の庭』を、監督自ら小説化。アニメにはなかった人物やエピソードを多数織り込んだ。