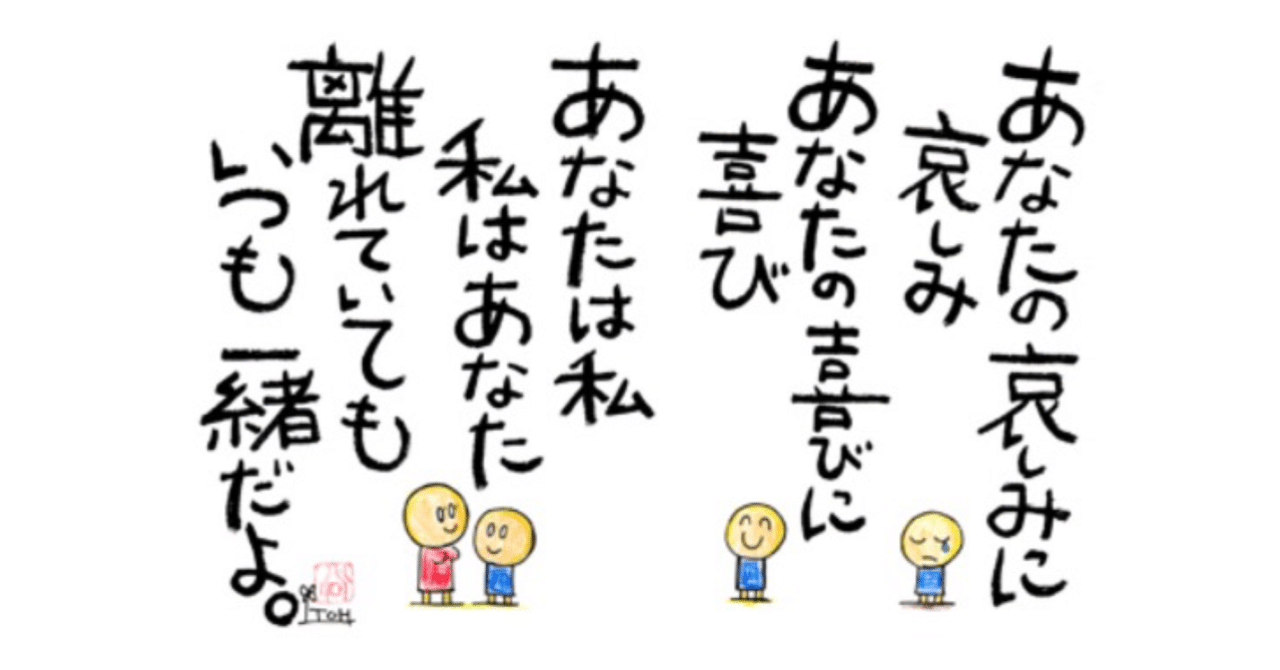撤回に至った原因は「説明不足」? いやいや、違うでしょう。「子供の安全」とか「虐待の禁止」とか、それ自体、絶対反対できないキーワードの裏に隠されたものを、多くの県民(国民)が本能的に嗅ぎ取ったから(だと思いたい)です。
埼玉県虐待禁止条例改正案、埼玉県内のみならず、全国的に批判の声が大きくなり、本会議での採決を前に、無事(?)撤回となったそうで。
埼玉県議会に提出されていた、子どもを自宅などに放置することを虐待と定める条例改正案について、同県議会の自民党県議団は10日、記者会見し、案を取り下げると表明した。13日の本会議で撤回の手続きを取る方針。改正案を巡っては「対応できない家庭が多い」など反対も多く、波紋を広げていた。
しかしながら、もう済んだ話、では済まないようです。
●間違いを認めていない?
当の自民党県議団は、改正案の内容それ自体に瑕疵はなく、説明不足で反対の声が広がっただけ、という認識でいる、と言う他なく。
こちらの「田村琢実県議団長との主な一問一答」を読む限り、いやいやお客さん、って感じですかね。
既に施行されている条例全体の中で冷静に判断してもらいたかった、のだそうです。
じゃあ、実際、その条例の全体像はどうなのかと言いますと、その「あらまし」がこちらです。
https://www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/bn/H29_07/0711_t2916/item/6772/t2916_20170711i6772.pdf
なるほど〜。
趣旨
児童、高齢者及び障害者(以下「児童等」という。)に対する虐待の禁止並びに虐待の予防及び早期発見その他の虐待の防止等(以下「虐待の防止等」という。)に関し、基本理念を定め、県及び養護者の責務並びに関係団体及び県民の役割を明らかにするとともに、虐待の防止等に関する施策についての基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって児童等の権利利益の擁護に資するもの
ですか・・・
「まあ、そうですね」という程度の「理念条例」なのですね。
ただ(だからこそ?)、全体として、先の国会でゴリ押し制定されたLGBT何とかと似たような建付けになってまして。
基本的に反対できない「理念」を掲げておいて、で、その理念を広く一般に「啓蒙」していくために、アレやれコレやれという種々の責務役割を挙げ、のみならず、あーだよこーだよという諸々の刊行物作成・研修開催等に予算を回してちょうだいね、みたいな・・・
いや、むしろ、自民党埼玉県議団(の一部)こそが「そういう遣り口」の先鞭をつけ、自民党国会議員(の一部)がその成功体験を参考にして色々蠢いている、なんてハナシもあったりなかったり。
だからどうだ、ということでもありませんが、自民党埼玉県議団≒稲田朋美埼玉後援会だったりしますし💧
あ、でも、考えてもみれば、そこら辺はいっそ、今は昔の男女共同参画云々の頃から見え隠れするようになった常套手段と言うべきかもしれません。
●「理念」も解釈次第で
条例の「あらまし」に戻ると、こんなことも書かれてます。
(二)基本理念
ア 虐待は、児童等の人権を著しく侵害するものであって、いかなる理由があっても禁止されるものであることを深く認識し、その防止等に取り組まなければならないこと
イ 虐待の防止等は、社会全体の問題として、地域の多様な主体が相互に連携しながら取り組まなければならないこと
ウ 虐待の防止等に関する施策の実施に当たっては、児童等の生命を守ることを最優先とすること
エ 養護者への支援は、切れ目なく行われなければならないこと
つまり此度は「児童等の生命を守ることを最優先とする」の部分が暴走した(を暴走させた)ということになりますかね。
ちなみに、国の「児童虐待の防止等に関する法律」には、こんな定義がありまして。
(児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
「三」に「長時間の放置」とありますね。
でもって、そこを意図してかどうかは分からないけれども、埼玉県議団の説明では「長時間の」が脱落。時間(と、ついでに状況も)関係なく「放置=虐待」と単純化していたわけで。
「放置」が「児童等の生命」を危険に晒す、と言われれば、それはまあ、そうです。
けれども、だから「全ての放置は虐待」というのは極端であって。
まして「放置を見たら通報」というのは極論であって。
何か、このテの論理の飛躍って、コロナ騒動時のマスクもそうだったな、って思わずにいられません。
マスクの着用に(時と場合によってほんのちょっぴり)感染予防効果があるとして、そこからは、おどろくほど短時間で「何時でも何処でも誰でも」というところまでマスク着用の薦めが拡大、マスク警察の跋扈にまで至ったわけで。
そういう危険を(おそらく、ひとまず「撤回」したものの「諦めた」わけではない)今回の改正案は孕んでいた(いる)ように思うんです。
●庶民をバ◯にしているような・・・
だいたい、留守番も、買い物も、ある日突然できるようになるものじゃないでしょう。
短い時間から長い時間へ、近いところから遠いところへ、親の判断で(!)少しずつハードルを上げていくもの。
それを、小学校3年まではとか、6年まではとか、個人個人、各家庭の違いを認めず、一律に定めようとしたことも間違いで。
世の中、これをやっておけば絶対安全なんてあり得ません。
猛烈個人的見解を言えば、生命とか安全とかが最優先とも思いません。
安全対策が、時に効率とか、何なら自由とかを減ずることがあって。
どの程度危険を織り込んで生きるか、そこは個人や家庭が、それぞれの価値観、人生観に基づいて判断することではないですか。
人には、傷つく自由、後悔する自由があって良いのです。
それが無かったら、生きているとは言えないと考える人だっているのです。
虐待とか貧困とか、あるいは性同一障害とか、小説やドラマになるような、真に救われるべき事例があることは否定しません。
でも、そういった人々がやたらと多くいるような印象操作をもとに理念法・条例をつくり、普遍的なものとして広く一般になにがしかの行動を促す(そしてお金を使う)というのは、どうなんでしょう。
(あえて言えば)少数の人々を救うことと、その他(一応言っておけば)多くの人々の日々の暮らしを守っていくこととは、本来別の話だと思います。
●無かったことにはさせません
最後に、実際の条文も見ておきましょうか。青字は施行済み、赤字部分が撤回された「改正案」です。
(養護者の安全配慮義務)
第六条 養護者(施設等養護者及び使用者である養護者を除く。)は、その養護する児童等の生命、身体等が危険な状況に置かれないよう、その安全の確保について配慮しなければならない。
2 養護者(施設等養護者及び使用者である養護者に限る。)は、その養護する児童等の生命、身体等が危険な状況に置かれないよう、その安全の確保について専門的な配慮をしなければならない。
3 児童を現に養護する者は、その養護する児童の安全を確保するため、深夜(午後十一時から翌日の午前四時までの間をいう。)に児童を外出させないよう努めなければならない。
(児童の放置の禁止等)
第六条の二 児童(九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはならない。
2 児童(九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童であって、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置(虐待に該当するものを除く。)をしないように努めなければならない。
3 県は、市町村と連携し、待機児童(保育所における保育を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをいう。)に関する問題を解消するための施策その他の児童の放置の防止に資する施策を講ずるものとする。
(県民の役割)
第八条 県民は、基本理念についての理解を深め、県民と児童等及びその養護者との交流が虐待の防止等において重要な役割を果たすことを認識し、虐待のない地域づくりのために積極的な役割を果たすよう努めるとともに、県及び市町村が実施する虐待の防止等に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 県民は、虐待を受けた児童等(虐待を受けたと思われる児童等を含む。第十三条及び第十五条において同じ。)を発見した場合は、速やかに通告又は通報をしなければならない。
青字部分はこちらから。
赤字部分については、「撤回」される前、下のサイトに原文PDFが出てたんですが、今はなくなってて、こんな文言のみになってます(こういうとこ、嫌らしいなあと思う)。
令和5年10月4日提出分
議第25号議案「埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例」については撤回承認されました。
ご存知の方も多いと思いますが「子育て4訓」というものがあります。
「乳児はしっかり肌を離すな」
「幼児は肌を離せ手を離すな」
「少年は手を離せ目を離すな」
「青年は目を離せ心を離すな」
ほほう、ですね。
とは言え、だったら、いつ肌を、手を、そして目を離すか、は、実際に子供を抱きしめ、手を繋ぎ、見守っている人にしか分からないことで。
そういう極めて個人的で家庭内のことにまで議会(他人)が首を突っ込もうとした(している)ことが、根本的に間違っていると思うのでございますよ。
今日日の政治は、要らんことまで遣り過ぎ。
「小さな親切大きなお世話」です。
子育て4訓の出処は諸説あるっぽい。ご参考まで。