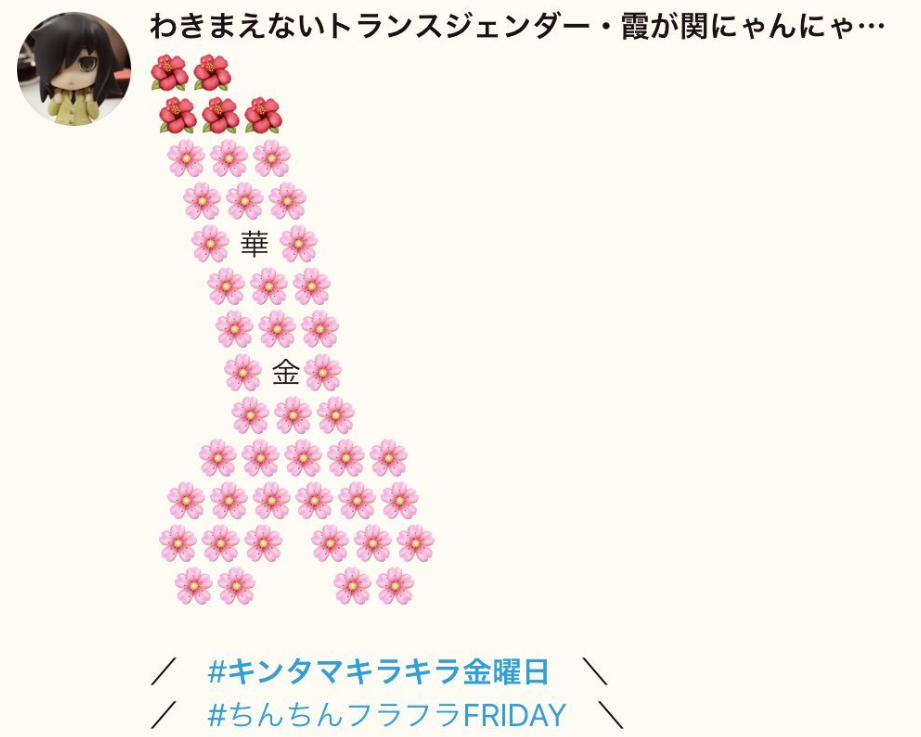「体の性」と「心の性」とが一致しない、ゆえに生きるのが困難だという。そういう人は、そりゃいるのでしょう。けれど、人の心は測れない。その辛さ、苦しさは、人には分からない。何なら、本人にだって分からない・・・こともある。
これが、時代の流れというヤツでしょうか。
●世の中は、見出しで動く(?)
やはり、1面トップでした。
トイレ制限 最高裁「違法」 性同一性障害巡り初判断
(中日新聞7/12-1面)
続くリードは、こうです。
戸籍上は男性で、女性として東京都で暮らす性同一性障害の五十代の経済産業省職員が、省内で女性用トイレの使用を不当に制限されたとして、国に処遇改善を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(今崎幸彦裁判長)は十一日、制限を認めないとの判断を示した。経産省の対応を是認した二〇一五年の人事院判定を違法と判断し、職員側の勝訴が確定した。
ほとんどの人は、自分には関わりのないこととして「ふ〜ん」くらいにしか思わないかもしれません。
あるいは、ここまで読んで満足し「へ〜」と納得してしまう可能性もあります。
●魂は細部に宿る(!)
しかしながら、すこしでも引っかかりを覚えるのであれば、踏ん張って、本文も読まなきゃいけません(赤字強調は引用者)。
経産省職員が逆転勝訴
自認する性別が出生時と異なるトランスジェンダーなど性的少数者の職場環境の在り方を巡る最高裁の初判断で、裁判官五人の全員一致による結論。小法廷では異例となる全員の個別意見が付いた。今崎裁判長の補足意見は判決について、不特定多数が利用する公共施設のトイレなどを想定した判断ではないと強調し、そうした問題は改めて議論されるべきだと説明した。同様に人間関係が限られる企業や学校などでは性的少数者のトイレ使用の対応に影響する可能性がある。
う〜ん微妙に「あれかし報道」。
さり気なくアリバイ工作をしつつ、しかし言外に「そうあってほしい、そうなれ」という願望(「個人の感想」)含みの書き方になってきました。
本文の続きは以下のとおりです。
判決によると、職員は入省後に性同一性障害との診断を受けた。健康上の理由から性別適合手術は受けていない。長年、女性ホルモンの投与を受け、一〇年から許可を得て女性の身なりで勤務を始めたが、女性用トイレについては勤務先のフロアから上下二階以上離れた場所での使用しか認められなかった。職員は制限を不服として人事院に行政措置要求を申し立て、一五年に退けられていた。
第三小法廷はまず、これらの個別事情や職場でのトラブルもなかった状況などを考慮し「職員は自認する性と異なる男性用か、離れたフロアの女性用トイレしか使えず、日常的に不利益を受けている」と指摘した。
さらに職員が性同一性障害について周囲に説明会を開いて以降、人事院判定が出るまでの約四年十カ月の間、経産省側が処遇見直しなどの検討をしなかった点を重視。不利益を受け入れなければならないような事情もないとして、人事院判定は「職員の具体的事情を踏まえることなく、同僚らへの配慮を過度に重視しており、著しく妥当性を欠く」と結論付けた。
一、二審では自認する性別に即した社会生活を送ることをいずれも「重要な法的利益」と位置付けたが、結論は分かれた。一九年の東京地裁判決が使用制限は正当化できず違法とした一方、二一年の東京高裁判決は「他の職員の性的な不安などを考慮した」などとして適法と判断していた。
判決≒判断については、一般市民として「はあ、そうなんですね」と呟く以外ないですね。
けれど、「事情」とか「配慮」とかいったものは、その属性がマイノリティか多数派かは関係ありません。双方に等しく認められ求められるものではないのですか、とは思います。
つまり、
マイノリティなんだから我慢せよ、と言うのが間違いなら、
マジョリティゆえに配慮しろ、と言うのも横暴ではないか、
というものでして。
●「想像力が欠如」しているのは、どっち?
記事には、お約束のように、専門家(?)の解説が付いてます。
経産省の想像力が欠如
大阪公立大の東優子教授(ジェンダー研究)の話 判決は今回の経済産業省の対応について、組織の中でマイノリティーが声を上げることがどれだけ大変かという想像力が欠如していたことを示しており、民間や教育現場にも影響を与えうる判断だ。誰もが安全・安心にトイレを使うためには多目的トイレを増やすなど選択肢を増やすことが重要なのに、トランスジェンダーの使用を制限するという解決策が取られてきた。困っている人に問題解決を押しつけない社会にしていかなければならない。
え〜と、アナタこそ、今日、この「空気」の中で、マイノリティに対して物申すことがどれだけ大変かという想像力が欠如しているのでは?
マイノリティ=困っている人、とは限らないでしょう。困っている人=多数派ということも有り得ます。
マジョリティ側に「問題解決を押し付ける」社会だって、やはり間違ってるような気がしますけどね。
●判決「全文」に当たりましょう
いずれにしても、この「判決」を一般化したい人と、個別事例にとどめたい人とがいて・・・
前者は、見出しだけを繰り返し、後者は、懸命に言葉を尽くすという、ま、これまた、よくあるパターンになっております。
そろそろ面倒くさくなってきたかもしれませんが、この際なんで、判決それ自体も(これでも極一部なんですが)見てみましょう。
「原審の適法に確定した事実関係等の概要」から。
なお、男女共用の多目的トイレは、上記執務室がある階(以下「本件執務階」という。)には設置されていないが、●●●複数の階に設置されている。
⎯⎯え、(執務している階でないにしても)多目的トイレあるの? 新聞記事(や、その他、多くの報道)は触れてないですけど、ソコ、重要なんじゃないの?
「裁判官宇賀克也の補足意見」から。
さらに、上告人が戸籍上は男性であることを認識している同僚の女性職員が上告人と同じ女性トイレを使用することに対して抱く可能性があり得る違和感・羞恥心等は、トランスジェンダーに対する理解が必ずしも十分でないことによるところが少なくないと思われるので、研修により、相当程度払拭できると考えられる。上告人からカミングアウトがあり、平成21年10月に女性トイレの使用を認める要望があった以上、本件説明会の後、当面の措置として上告人の女性トイレの使用に一定の制限を設けたことはやむを得なかったとしても、経済産業省は、早期に研修を実施し、トランスジェンダーに対する理解の増進を図りつつ、かかる制限を見直すことも可能であったと思われるにもかかわらず、かかる取組をしないまま、上告人に性別適合手術を受けるよう督促することを反復するのみで、約5年が経過している。この点については、多様性を尊重する共生社会の実現に向けて職場環境を改善する取組が十分になされてきたとはいえないように思われる。
⎯⎯いやいや、違和感・羞恥心は、どこまで行ってもその人個人のものであってですね。それを「トランスジェンダーに対する理解が必ずしも十分でないことによる」とか言われましても・・・
「裁判官渡邉惠理子の補足意見」から。
また、原審の認定事実によっても、本件説明会において女性職員らが異議を述べなかったことの理由は明らかではない。上告人が男性であると認識していたために、上告人が女性トイレの利用を希望することを知って戸惑う女性職員が存在することそれ自体は自然な流れであるとしても、本件説明会において女性職員らが異議を述べなかった理由は一義的ではなく複数あり得るものである。すなわち、女性職員らが、上告人にその自認する性別のトイレ利用を認めるべきであるとの認識の下で異議を述べなかったことも考えられる(一件記録によれば、このような女性職員の存在もうかがわれる)。また、女性職員らが、異議ある旨の意見を多数の前で述べることに気後れした可能性がないとは言い切れないものの、戸惑いながらも上告人の立場を配慮するとやむを得ないと考えた場合や反対することは適切ではないのではないかと考えた場合(一件記録によれば、このように考えた女性職員らの存在もうかがわれる)などの理由による場合も十分にあり得ると考えられる。
⎯⎯そう、そういうことですよ。でも、せっかっくのその「想像力」が、全体の判断≒判決には活かされていないという・・・
「裁判官今崎幸彦の補足意見」から。
なお、本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである。
⎯⎯これ、超重要。けど、新聞記事では本文まで読まないと出てこないわけで。「女性トイレ使用制限は違法」を一般化したい人々は、極力、触れずにいる様子ですし、これからも捨て置くつもりなのでしょう。
判決全文、引用はこちらからです(赤字は引用者)。
といことで、結論。
というか、むしろ、素朴な疑問。
●人の心は測れない
性同一障害で「普通に」生きるのも難しい人がいる、のは、そうだろうと思います。
けれど、「体は男性だけど心は女性」とか言うとき、体はともかくとして、心は、何をもって「女性」と言っているのでしょう。
LGBT界隈では「男性らしさ」「女性らしさ」を認めないんですよね。
したら「心は女性」という時の、その「女性」って一体何を指しているのでしょう。
女性トイレを使いたい人、ですか?
だったら、体が男性の人には女性トイレを使ってほしくない、少なくとも、アタシが使うトイレを使ってほしくない、と思う人の心は女性ではないのですか。
そういった「感覚(信条・価値観)」は「研修(学習?)」でもって、改めなければならないものなんでしょうか。
女性の気持ちに寄り添わず、推し測ることもせずに、「心は女性」なんて言われても・・・
です。
考えてもみれば、ジェンダーフリー界隈で女性管理職の少なさをいちいち問題にするのもオカシナ話で。
なぜって、世の中、男性も女性もないんでしょ。
てか、男性と女性だけじゃないんでしょ。
●これは・・・これも、デマ、フェイク、陰謀論?
さて、この裁判・判決に関してあちこち探検していたら、こんなのを見つけてしまいました。
何でも、件の経産省職員さん自身、かなり「特殊」な人ではないか、というハナシでして。
ひょっとして、同僚職員さんにしてみれば、「(一般論として)性同一障害の人と同じトイレを・・・」ではなく「(個別具体的に)正直、この人と・・・」という違和感(嫌悪感?)があったりなかったり、な、ちょっとヤバい事例なのかもしれないという・・・
具体的に紹介するのも憚られる内容なので、興味ある方はリンク先を覗いてみてください。
これは全国の公衆トイレに波及する問題ではないので、当初の受け止めは冷静でしたが、原告の裏アカウントと思われるツイートが発見されて騒然。
そんなわけで、最後に、猛烈「個人の感想」を。
同性であれ、異性であれ、どちらでもない性であれ、この人と同じトイレは使いたくない、少なくとも、10分くらい経ってからでないと嫌だ、くらいのことは、誰でもあるでしょう。にんげんだもの。
もちろん、聞き取り調査とかで、ソレを言う人なんていませんけどね。
たぶん、関連ニュース。
(中日新聞7/1-9面)
うん、まあね・・・男性専用、女性専用をしっかり確保したうえで、それとは別に、ということであれば否定はしません。
(中日新聞7/1-15面)
いや、もう、ヒマなの? って感じです。
男=青・ズボン、女=赤・スカート、でも良いじゃん。
単純に、記号として定着してるし、分かりやすいし。何が気に入らないんだか。
トイレ表示がそうだからって、今時、「うわ〜、男のくせに女色使ってる〜」とか「お前、女のくせにズボンかよ〜」とか、それこそ小学生でも言わないでしょうに。
世の中、種々諸々「間違い」を減らすために、色と形とを分けるのは基本。
そこに「何となく(社会的・文化的に)そんなイメージ」を含ませるのも当たり前。
それをもって「固定的」だの「差別」だの言い出す方が「想像力の欠如」であり「発想の貧困」であり、あるいは、簡単に「らしさ」を押しいただいてしまう弱さの現れ、ではないですか?