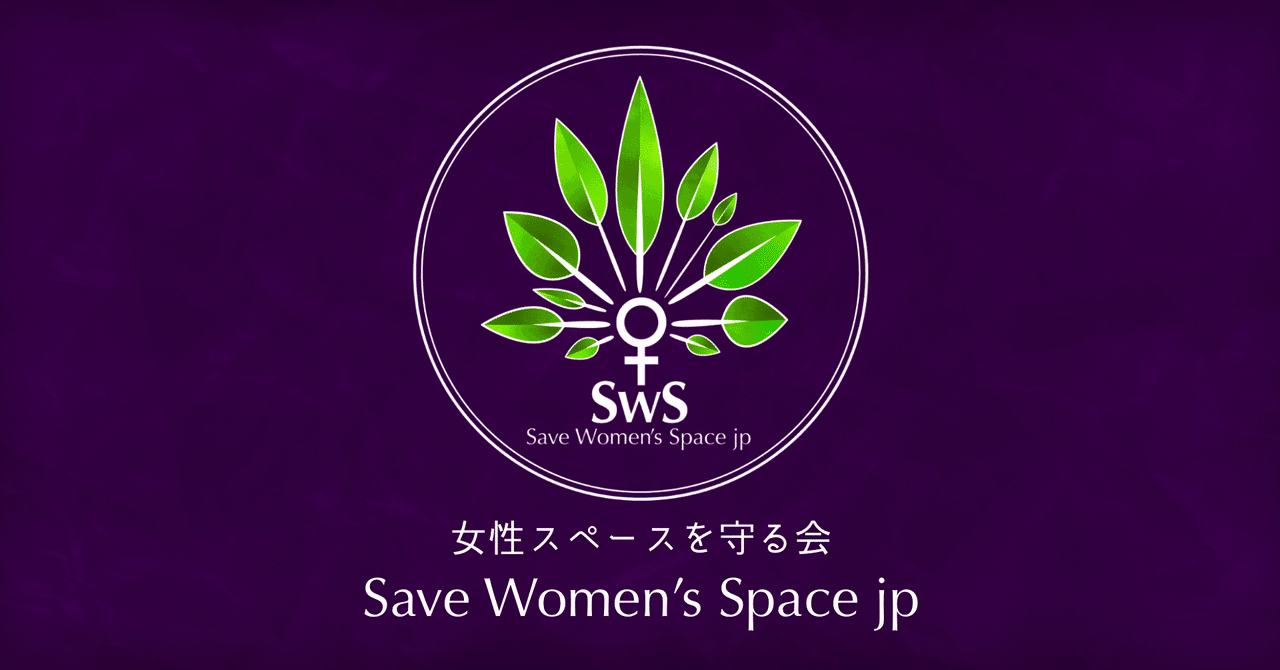「その他・どちらとも言えない」への配慮は必要。だからと言って、青も赤も無くし「みんな」という単色に染めることで「みんな」が生きやすくなるとは限らない。
マスメディアと世論の関心は、高市さん(を貶めること)へと向いたようで、LGBT法案については、あっちゅうまに今は昔の物語。
ただ、ネット上では、こんな話が一瞬蒸し返されて消えました。
●みんなの(多機能)トイレ設置・トイレ洋式化
我が豊橋のお隣、豊川市の、ちょっと前にあった出来事です。
更新日:2019年5月22日
トイレ改修に伴い各校1ヵ所多機能トイレを設置し、和式便器から洋式便器へ改修し施設を整備します。
豊川市教育委員会では、「気兼ねなく行けるトイレ環境づくり」として次の4つを軸に取り組んでいます。
(1)防災機能強化の整備
(2)洋式便器の整備(洋式化率70%以上目標 令和2年度)
(3)3K(くさい・くらい・きたない)のイメージ改革
(4)性の多様性に配慮した取り組み
一読「あー、そうなのね」くらいの話なのですが、「(4)性の多様性に配慮した取り組み」の部分が批判的に取り上げられたようです。
実際、こういった改修事例がありまして。
https://www.school-toilet.jp/book/pdf/21_11.pdf
「この学校ではみんなのトイレがあるから、当たり前にある性的マイノリティのことを普通に伝えることができる。子どもたちの自由選択で、好きなものを使えることも大切」
う〜む・・・
「差別や偏見を無くすには、まず慣れること」を持論とするワタクシとしては「まあ、そうなんでしょう」と言うしかないのだけれども。
上とは別の事例ですが、こちらでは、児童アンケート調査結果も出ています。
https://www.school-toilet.jp/book/pdf/23_08.pdf
「男女別のトイレを使用してきた児童の過半数が男女共用トイレを肯定的に受け止めていることに驚いた。数年後には共用トイレが一般的となり、施設を使うすべての人が気兼ねなく利用できるようになることを望んでいる」
う、うん?
「手洗いまでブースの中でできるのでよい」「使っているときにのぞかれる心配がなくてよい」は、男女共用だから、ではないですよね?
それらへの回答から「過半数が男女共用トイレを肯定的に受け止めている」と判断するのは、ちと無理があるのではないでしょうか。
その上で、個人の感想ではありましょうけれども、うっかり(?)「共用トイレが一般的」となることを望んでいる、なんて言っちゃってます。それは流石に・・・どうなんでしょう?
だいたい、教室横の(従来からあってたぶん古い)「男子と女子が分かれたトイレ」と、(新しくてきれいな)「1階のトイレ」との比較で、それでも、前者を「好き」と答えた児童が49%いるではないですか。
ちなみに、この方、豊川市教育委員会庶務課技師さんであり、そもそもの仕掛け人と言っても良さそうです。「東京五輪を見据えて性的少数者(LGBT)に配慮した公共トイレを普及させていこうという取り組みを新聞で読んだこと」がきっかけだったと中日新聞が(ネットでは会員限定ですが)伝えていました。
学校のトイレ事例、上の二つを含めこちらで。
ま、善悪はともかく(というか、正直、感心しないけれども)柔らか頭のうちに、というのは「理解増進」の観点から「上策」ではありますね。
●共用トイレ=社会的包摂?
「インクルーシブ(inclusive)」すなわち「包摂(ほうせつ)的な、すべてを包み込む」くらいの意味だそうで。「受容と活用」といった意味付けをしている経営者もいるとのこと。
「ダイバーシティ(Diversity):多様性」とならんで、数年前から「絶対的正義」として語られてます。
その文脈で、豊川市の取り組みを紹介している記事がありました(赤字は引用者)。
インクルーシブな教育環境へ
トイレの洋式化に伴い、気兼ねなく使える男子トイレの全個室化やLGBTへの配慮などから男女共用のトイレを設ける学校もある。愛知県豊川市では、トイレの快適性を追求した結果、2016年度から市立小中学校で男女共用化のトイレ設置を始めた。長沢小学校で改修したトイレは、共通の入り口から入る1つのスペースに、女子用、男子用、男女共用、男女共用で車いすでも利用可、男子用小便器の計5つの個室を完備。どれを使うか児童が選ぶことができるようになっているほか、洗面台は自動水栓を採用し、鏡もプライバシーに配慮し個別に設置している。
また、中部小学校は特別支援教室近くの1階トイレ空間全体を「みんなのトイレ」として改修。長沢小と同様に男女共用や小用専用の個室など多様な選択肢を用意したほか、温水洗浄便座の設置や臭いや汚れの発生を抑える床材も採用した。豊小学校は各ブース内に手洗器と鏡を設置し、個室完結型トイレに改修。学校トイレとは思えない、ブースごとに異なる草花や鳥、ハートモチーフなどの絵柄の壁紙も印象的だ。
市によると、改修後の使用状況について行った児童のアンケート結果では、男女別のトイレを使用してきた児童の過半数が男女共用トイレを肯定的に受け止めていると指摘。「みんなのトイレ」を整備した一宮西部小学校の1年間利用後のアンケートでも、5年生112名のうち100名が利用し、1人当たり年間5回使われていることがわかり、先生方も驚いているという。
さらにはトイレ改修を機に5年生を対象に男女の性差を教える中でLGBTについても教えたが、トランスジェンダーの人たちに対して子どもの方が柔軟性のある考え方を持っていた。学校としても「みんなのトイレ」があるから、性的マイノリティーのことも普通に伝えることができたとし、数年後には共用トイレが一般的となり、施設を使うすべての人が気兼ねなく利用できるようになればと期待している。
えっと、小学生並みに柔らか頭なワタクシとしましては、つい「はあ、そうかもしれませんね」と頷いてしまいそうになります。
しかしながら、どこか引っかかりを覚えるのも確かです。
どうもですね、世の人が「包摂」という時、「差」もなく「別」もなく、「等しく包み込む」べきだという考えの人もいるようで。
言うなれば、みんなを「みんな」という一色に染め上げようとしている、ような気配です。
色々な人がいる。それを認めるのが大切だと分かってはいても、やはり個別に対応するのは面倒だ。だったら、いっそ「みんな一緒」にしてしまおう。みたいな?
しかしながら、それをやってしまううと、様々な色が織りなす鮮やかな社会が、グジャグジャに濁った単色の全体になるわけで。
人の世を、青(男性)と赤(女性)とに二分し、それ以外を認めないというのは、それは確かに間違ってます。
けれど、紫だったり、青紫、赤紫、あるいはモザイクだったり、グラデーションだったり、が在るから、青も赤も無いんだ、という話でもない。
大まかな括りとして「青」と「赤」は、やはり存在するわけで。
豊川市の小中学生はもちろん、ワタクシ自身「気を確かに持て」と自らを奮い立たせなければなりません。
結論。
男女共用トイレ自体は、そりゃ有っても良い。
けれど、男性・女性用が無くなって良いという話ではない。
です。
ついでに言えば、ピクトグラムを単色にするの止めてください。男女共同参画云々言い出した頃から俄に増えたのだけれども、分かりにくくて仕方ない。記号(お約束)として「男=青・女=赤」を踏襲したところで、固定的役割分担の刷り込みになるはずもないでしょうに。
●男も女も、LGBTだって十人十色
そもそも、男女共用トイレ(が一般化すること)を求める人が、どれほどいるのでしょうか。
TOTOが興味深い調査をしています。
<調査結果の概要>
外出先トイレ利用で、トランスジェンダーの感じるストレスのトップは、「トイレに入る際の視線」(31.1%)でした。他者の視線を気にせず自由に選択できる場合、トランスジェンダーのうちFtM※3・MtF※4は「からだの性に基づくトイレ」を利用したい人も、「性自認に基づくトイレ」を利用したい人もいました。また、トランスジェンダーはシスジェンダー※5に比べて「多機能トイレ」「男女共用トイレ」の利用意向が高いこともわかりました。さらに、TOTOが提案している「性別に関わりなく利用できる広めトイレ」の普及について、トランスジェンダーの85.7%、シスジェンダーの76.0%が賛意を示しました。トイレサインへのレインボーマーク※6の掲示には、性的マイノリティ当事者でも、意見が分かれる結果となりました。
※1:からだの性とは異なる性自認を持つ人 ※2:商業施設、交通施設、オフィス、学校など、住宅以外のあらゆる施設のトイレを、TOTOではパブリックトイレと呼んでいます ※3:FtM(Female to Male)=からだの性は女性だが、性自認は男性の人 ※4:MtF(Male to Female)=からだの性は男性だが、性自認は女性の人 ※5:からだの性と同一の性自認を持つ人 ※6:レインボーマーク=1978年、サンフランシスコでゲイ解放活動のシンボルとして「レインボーフラッグ」が誕生して以来、性的マイノリティの権利の象徴として広がっているもの。正式に合意されたマークは存在していない
男女共用トイレを使うとそれだけで「特別視」される、だから全てを男女共用にしよう、という考え方も分からないではない。けれどそれは、LGBT当事者の中においても、おそらくは「過激思想」の部類でしょう。
「みんな」に効く薬はない(ワクチン接種も同様)。
「みんな」に適う健康法もない(マスク着用も同様)。
ところが、公衆衛生という絶対正義の前に、全ての人が「包摂」されてしまった。
「みんなのトイレ」もそれと同様、
配慮や思い遣りが正義の衣を纏って暴走している(そして儲ける人がいる)の図・・・
に見えてしまう。
いささか罰当たりですかね。
「性的指向・性自認に関する差別を禁止する法律の早期制定を求める緊急アピール」なんてものを出している連合。
職場に関係ないこともないし、特にダメとは思わないけれども、こんな啓発活動もやってるのね。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/gender/lgbtsogi/data/whats_lgbt_sogi.pdf?5540
んー、性自認なー・・・それが「自認」に留まる限りにおいて、アリで構わないのだけれども・・・
(ウチの女子達の反応を見ても)男女共用トイレ(だけになること)には、むしろ女性の方が厳しい意見を持っているのではないかと思ったりもしてまして。
「女性スペースを守る会」というものがあるそうです。
🟢 女性スペースを守りたいと考えています。
🟢 「性自認」について立ち止まって考え、十分な国会審議を求めていきます。
LGBT法案への懸念
LGBT法案のうちの「T=性自認による差別は許されない」という文言が身体の性別よりも性自認を優先させることに繋がり、身体の性別によって社会的な不利を被ってきた女性の人権を更に後退させる恐れがあると、私たちは考えています。
なるほど、なるほど。
さらに、こんな説明をしています。
いわゆるLGBT新法などにより、女性トイレ等を女性自認者(いわゆるトランスジェンダー女性=身体違和は不要で、性指向は女・男・両性である身体的・法的な男性)が使うことが公認されて良いかを問い、諸々の課題がある『性自認』について立ち止まって十分な国会審議を求める会です。
趣旨書要約
① 先人が血と涙とで確保した「女性スペース」を守りたいと、考えています。
② 「男らしい」女性も、「女らしい」男性も、そのままに尊重することが「性の多様性」を承認することであると考えています。
③ 「性自認」という概念・主張の規定は新しいもので、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の延長ではないことを、周知してほしいと願っています。
④ 理念法であっても「性自認の尊重」とあると女性自認者が女性スペースに入れると公認され、実質的には女性の装いをする男性のすべてが容易に女性スペースに入れるようになってしまうと、憂慮しています。
⑤ LGBT法案で「女性」という性自認が「尊重」されることによって生じる、生物学的・法的女性と女性自認者の法益の衝突を、しっかり検討して欲しいと考えています。
⑥ DVシェルター、女性スポーツ、女子大、政治界での男女同数化に類する「女性枠」など「性自認」には孕む課題が多く、ここで立ち止まり、広く国民の議論を喚起しつつ、十分な国会審議がなされるように、求めています。
女性専用・男子禁制はもちろん、何なら女人禁制についても、その真意は女性を守るための知恵だという側面がありまして。
趣旨書要約の④⑥辺りは、為にする議論とか思い込みとかではなく、「先進的な外国」において、性犯罪を含め、実際に起きていることですからね。