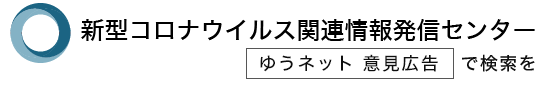「間違いを認めなさいよ!」とか「何かしら謝罪があっても良いんじゃない?」とか、言いたいことは、そりゃ色々あるけれど・・・
期せずして前回の続き、の、ようなもの。
にわかに、政府・厚生労働省が動きました。
さすが、世論追随型内閣。首相自らのノーマスク画像・映像が出回ったおかげで、国民の間でふつふつとした不満が噴出したのを敏感に捉えたようです。
一応褒めてます。
ということで、何となく、この1週間を振り返ってみましょう。
⚫ 新聞意見広第2弾告掲載
まずは、5月17日火曜日。
地元のブロック紙、中日新聞に例の意見広告が掲載されました。
これは、義母さんが購読しているものを頂いたのだけれども・・・
彼女の娘(つまりウチの奥様)に、義母さんが、①気付いただけ ②読んだ ③考えた いずれに当てはまるか聞いといて、とかお願いしましてね。
「あっさり①で玉砕したりして」なんてフラグ立ててたら、実際「わたしゃ広告は読まんよ」と斬り捨て御免食らったそうです。
ま、大抵はそんなもんかな。
だから新聞広告なんて意味がない、効果がない、自己満足だ、等々の批判をしたいわけじゃありませんよ。
何と言っても、政治家・役所関係の皆さんはそれなりに読むでしょうし。
加えて、事前に掲載審査とかもあるわけだから、当の新聞社社員、グループ会社であるCBCテレビなんかは、完全スルーというわけにもいかないはずで。
事実、前回の意見広告と前後して、CBC(TBS系列)は、例の「大石邦彦アンカーマンが深掘り解説!」シリーズでワクチン批判報道を始めてますからね。偶然ではないと思います。
⚫ 「外でマスク外しちゃう?」
ちなみに、同じ日の一面トップは「外でマスク外しちゃう?」でした。
立ち位置として、中日新聞は「朝日新聞よりも左寄り」というもっぱらの評判ですけれども(あのイソコちゃんがウリの東京新聞は中日の関東版です)。
ま、それはこの際置いといて。
5月19日木曜日、厚生労働省で「第84回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」がありまして。
そこで検討され、翌日発出されたのが、こちらの文書(字ばっかでつまらないし、真剣に読まなくて良いです)。
「何ら変更するものではありません」とか「以前の取り扱いに戻す」とか、言外に「変わってないよ」「間違ってないよ」というニュアンスを強調しているのは、役所の性ですかね。
ま、それもこの際置いといて。
⚫ 「マスク着用の考え方」by 厚生労働省
で5月20日金曜日、厚生労働省のツイッターに上がっていたのがこちら。先の文書で「概要については別紙参照」とあるところの「概要」?。
本日、新型コロナウイルス感染症対策について以下の方針を発表しました。
— 厚生労働省 (@MHLWitter) May 20, 2022
・マスク着用は引き続き基本的な感染症対策である
・身体的距離が確保できないが、会話をほとんど行わない場合のマスク着用の考え方を明確化する
・就学前の児童(2歳以上)のマスク着用はオミクロン株対策以前の取り扱いに戻す pic.twitter.com/C9ItjadgBI
「引き続き」とか「以前の取り扱いに戻す」とか・・・以下略で。
それはともかく、
どこに注目したら良いのか微妙なので、ワタクシなりに手を入れたものを再掲。
これだけはっきりと「着用の必要はない」としてくれたのは、実際、大きな一歩だと思います。
しかも「室内」について「外気の流入が妨げられる〜〜〜」という注まで付いてます。
ということは、例えば、屋根はあるものの天井が高く、出入り口、窓等開放、搬入口が大きく取ってあるような工場、倉庫などは「着用を推奨する」「室内」には当てはまらないわけですよね。
加えて、仮に「室内」だとしても「十分な換気など〜〜〜場合は外すことも可」とも言ってくれてます。
事実上「身体的距離を保てないまま長時間会話する場合のみ着用」で構わない、ということになりますね。
ふむふむ。ふむふむ。
したら(都会の方々には申し訳ないのだけれども)、程よく田舎の豊橋、基本車移動のワタクシ、厚生労働省のお墨付きのもと「人目を気にすることなく」ノーマスク生活を満喫できるということで。
素晴らしい! ノーマル星人、雌伏の季節(?)終了!!
ま、そもそも、着用するにしても「推し奨め」られてるだけで、丁重にお断り申し上げる権利はあるはずなんですけれども。
さて、どんなリーフレットが上がってくるのかな?
⚫ 「屋外会話なし マスク不要」
厚労省の発表を受け、5月21日土曜日。産経新聞のトップは「屋外会話なし マスク不要 未就学児 着用求めず 専門家初見解」という記事。
くぅ、涙が出そうです。
もちろん「こういう時は外す」ではなく「こんな場面でのみ着用(した方が良いかもね)」という方向に表現自体を変えてほしい、という気はします。
でも、ま、今のところは、ここまでで良しとしましょうか。
産経相手に限らず、
あんまり欲を出すと碌なことはないですし、本音を言えば・・・
限定なしに「マスク不要」まで行ってほしいのだけれども。
それはさておき、いや、それを含めて、
とりあえず(マスク否定・懐疑派も)、夏場とか子供とかを強調するのは控えた方が良いかな、と思ったりもしてます。
涼しくなって逆戻りじゃ意味ないし、子供は大人の真似をするものだし。
⚫ 自由の精神を取り戻そう
いずれにせよ、
政府・厚生労働省がどうあれ、マスメディアの報道が何であれ、十分な酸素と、考える意欲と、自由の精神を取り戻すことの方が重要なわけでして。
賛否の声、世論調査の結果なんてどうだって良い。
「人がしてもしない、人がしなくてもする」
「みんなちがって、みんないい」とはそういうこと。
だから、本当は、
すごく厳しく、とても難しいのだ。
🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥
与太話その1 「したら、観覧車は屋内 or 屋外? 」
以前、ウチの次女が彼氏さん(?)と、某ハイウェイオアシスに遊びに行きまして。
せっかくだから、観覧車に乗ろうということになりまして。
2人ともずっとノーマスクだったんですが、そこで初めて係員さんに「マスクしてください」と言われたんだそうな。
は、はい?
今まで半日以上一緒にいたんですけど? 車中でもノーマスクだったんですけど?
等々抵抗してみたものの、暖簾に腕押し、糠に釘。馬の耳に念仏、猫に小判。
ということで、猛烈憤慨しておりました。
いや、まったくね。
そもそも「濃厚接触」関係でない男女が観覧車に乗ること自体、そうそうないでしょうに。
ワタクシが責任者なら、むしろ逆に「乗る前にチューして見せたらマスク無しで大丈夫です」くらい言ってやるんですけどね。
🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥
与太話その2 「あごマスクは許可する」
知り合いさんの会社。「マスク着用による熱中症対策は昨年と同様に6月1日から実施する」のだそうで。
リフト作業含め常時着用――いやいや、リフト作業中、そもそも周囲の人は近寄っちゃダメでしょう。
管理監督者は指示をする立場のため常時着用――精神論だ。お気の毒。
外す場合、いつでも着用できるよう携帯する。あごマスクは許可する――アドバイスしているはずの産業医さん、無知丸出し。
うむ、まさしく「昨年と同様」の旧態依然。
なんだけど、これは、厚生労働省発表の前日決定したこと。見直し、変更はあるのかな?
🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥
件の意見広告、原本です。
危険性や弊害もさることながら、それよりも必要性を考えましょう。
さて、愛知が誇る(?)CBCテレビ【大石が深掘り解説】。
先日は、こんなのがありました。
厚生労働省、アドバイザリーボードのデータ修正(ワクチン接種歴、不明を未接種扱いにしていた、という件)について、です。
動画よりも、文字、という方はこちらを。
簡単に言うと、
医師から提出される検査陽性者一人ひとりの「新型コロナウイルス感染症、発生届」には、ワクチン接種歴を書く欄があるのですが、全ての発生届のうち2〜3割は「未記入」だったそうです。その「未記入」の例を全て「未接種」に分類していたというのです。
いやいや、アドバイザリーボード、色々やってくれますね。
こちら5月19日提出資料の中にありました。
入院療養等から重症化を経ずに死亡という方が1,683名いらっしゃるんですが・・・どういうこと?
「専門家」さんは、それを「オミクロンの怖さ」という方へ持っていきたいご様子なんだけれども。
いやいや、むしろ、コロナ特有の症状というわけでもなく亡くなった方を、一応検査してみたら陽性でした、というふうに考えるのが自然なんじゃないかと。
ま、どっちにしても、死亡者全体の数から見たら、何が何でも防がなきゃならないと特別扱いするほどのものではない、のは確かなようで・・・