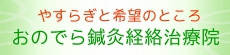昨夜、久しぶりに「毒親」という言葉を聞いたので、本書を紹介してみたい。
「毒親」という概念を作ったのは本著者のスーザン・フォワードである。
彼女は「子供の人生を支配し、子供に害悪を及ぼす親」を指す言葉として用いた。
日本では一般的に虐待やネグレクトを行う親に対してその名が使われるが、内容はもっと複雑であり、子供への支配は単に肉体的暴力あるいは言葉の暴力などにとどまらない。
暴力や暴言なども、言ってみれば「普通」の家庭でもありうるし、いかにそれが継続して子供に加えられ、子供の人格形成に影響を与え、子供が大人になった時に様々な生きづらさの元となっているかが重要なのである。
本著では「毒親」の事例がいくつも挙げられている。どんな毒親がいるのだろうか・・・。
1.「神様」のような親
2.義務を果たさない親
3.コントロールばかりする親
4.アルコール中毒の親
5.残酷な言葉で傷つける親
6.暴力を振るう親
7.性的な行為をする親
などが列記されている。
昨夜TVで紹介されていた毒親はさしずめ「コントロールばかりする親」だろう。
「子供をコントロールすること」自体は、子供の時期においてはその程度が適切であればむしろ必要なことである。
子供が幼く「危険」の認識が低い時は親が積極的にコントロールしなければならない。
しかし、成長につれて子供は様々なことを経験し、多くのことを学んでいかなければならない。
それを親の価値観で取捨選択し「経験させないこと」は、成長の機会を取り上げ、成長を阻害することになる。
言葉を換えれば、それは子どもの人権を侵害し、心を操り、子供の人生を支配することにもなる。
そんな親は常に「子供のためを思って」という言葉を隠れ蓑にする。
しかし、実は子供を思っているのではなく、自分のことが第一で、自分が必要とされなくなることを恐れているだけなのである。
そのため、子供の心の中に非力感を植えつけ、それが永久に消えないようにと望む。
そんな親に育てられた子は、表面的には親に依存しているように見えるが、実は親のほうが子供に依存しているのである。
なぜなら、彼らは「子供の親である」ことにしか自分のアイデンティティーを見出すことができないからだ。
そのコントロールの仕方には二種類あるという。
【 1 】直接的で露骨なコントロール
「言ったとおりにしなさい。さもないと・・・・・」というように、この「・・・・・」の部分には「何も買ってあげない」「もう口を聞いてあげない」「もううちの子供じゃない」などの言葉が入る。
時に直接的な暴力のこともあるが、いずれにしろ「脅し」による方法でコントロールするやり方である。
これにより子供の意見や欲求は圧殺されるのである。
a.自分の都合を押し付けるタイプ
親元を離れて就職・結婚をしたある男性が、両親の結婚記念日を祝うために夫婦で帰郷する予定だった。
ところが妻が病気にかかったために行かれなくなった。
すると、母親は「お前が来なければ死んでしまう」と言う。
仕方がないのでとんぼ返りのつもりで彼は帰郷したが、両親はそろって「一週間泊まっていけ」と言い出した。
彼は無理に戻ったが、すぐに父親から電話が来て「母親が病気になった。お前は母親を殺すつもりか」と責め立てた。
両親は妻を無視し続け、彼も強く両親には言い返せない。
このタイプの親は自己中心的で子供が成人したあとも「脅す」ことでコントロールしようとする。
b.金でコントロールしようとするタイプ
いつの世も、親子関係だけでなく、あらゆる関係において金は大きな力関係を作り出す手段となる。
c.子供の能力を永久に認めないタイプ
幼少時から常に「何も出来やしないくせに」と罵り続け、非力感を子どもの心に植え付ける。
繰り返し心の奥深く植え込まれた非力感は大人になっても、そう簡単にぬぐい去ることはできなくなる。
【 2 】はっきりとわかりにくい心のコントロール
一見ソフトなオブラートに包まれたコントロールは、実は一般的に当たり前に行われている。
夜遅くまで居座る友人にあくびをしてみせるなど、日常的にも行われていることだろう。
これらは善意に根ざしている限り、人間関係を滑らかにする潤滑油としての役割をはたす。
しかし、相手をコントロールするための手段として執拗に、過剰に使うようになると非常に不健康で有毒なものになる。
それは直接的なコントロールにも劣らぬ程の毒を持っている。
a.「干渉をやめぬ母」のタイプ
「手助けをしている姿」を装い、いらぬ干渉をする。
独立した子供に、頼みもしない料理を持っていく、留守中に部屋に上がりこみ掃除や整理をしていくなど、やめてと頼んでも続けるのである。
子はそんな親を疎ましく、時に怒りを感じたりもするが、同時に疎ましさや怒りを感じる自分に対し、悲しく、罪悪感を持ったりもするのである。
その罪悪感ゆえに過干渉を結局は拒みきれず、疎ましさや怒りは心の内に蓄積していくのである。
b.「兄弟姉妹まで親と一緒になって責める家」タイプ
親だけでなく、兄弟が親と一緒になって「お母さん(お父さん)を傷つけて」と責める家は「毒親」ならぬ「毒家」である。
c.「兄弟を比較する親」タイプ
兄弟間で団結しないよう、分断する。
子供の中で最も独立心の強い子がターゲットになりやすい。
こうした親に育てられた子の示す反応としては、服従か反抗である。
この一見正反対に見える二つの反応は、心理的独立を阻まれているという点では同じである。
反抗は親から心理的に独立しようとしている現れのようにも見えるが、単にコントロールに対する反動に過ぎないという。
どうも、自分の家の状態にいくつか共通点があるように思えてならない(笑)。
心理的独立ができているかどうかは、親からコントロールされそうになった時、反射的な怒りで反抗するのか、親の要求内容を冷静に判断して必要性の有無を判断できるかどうかである。
要求が妥当で必要なものと判断して受け入れることは服従ではないし、不必要と判断して毅然と断ることは反抗ではない。
中島みゆきの歌「空と君のあいだに」の中には、「憎むことでいつまでもあいつに縛られないで」というフレーズがある。
誰かを憎み続ける、怒りを感じ続けるということは心が相手に囚われ続けているということなのだ。
「毒親」のほんの触りだけを紹介したが、「毒親」の呪縛は死してなお続くという。
幼少時に埋め込まれた感情、考え方、感覚は、自分が子育てをする際に「良好な親子関係の築き方」を知らないために、同じことを自分の子にもしてしまいがちになる。
とすれば、「毒親」もまたその親によって毒を植えつけられたのである。
この連鎖を断ち切るためには、「毒親に育てられた」と今感じているあなた自身が変化するしかないとスーザン氏は語る。
第二部では「毒になる親」から人生を取り戻す道、が記されている。
熟読した上で、自分で取り戻す道を歩むのは構わないが、どのような「毒親」に育てられたか、「毒」の種類によってはカウンセラーの手助けが必要だという。
また、アルコールやドラッグ中毒の人は、それらの影響を排除するために最低6ヶ月絶ってから取り組むことが推奨されている。
詳細はぜひ読んでみてほしい。
ちなみに、親との関係を振り返ってみた時に、以下の項目のうち4つ以上当てはまるという方は、心が親と相当絡みあっている状態だという。
心当たりのある方は、本書で独立への道を歩み始めてはいかがだろう。
《 親との関係における考え方 》
1. 親は私の行動次第で幸せに感じたり感じなかったりする。
2. 親は私の行動次第で自分を誇らしく感じたり感じなかったりする。
3. 親にとって私は人生の全てだ。
4. 親は私なしでは生きられないと思う。
5. 私は親なしでは生きられないと思う。
6. もし私が本当のこと(例えば、離婚する、中絶した、同性愛である、フィアンセが外国人である、等々)を打ち明けたら、親はショックで(または怒りのあまり)倒れてしまうだろう。
7. もし親に楯突いたら、私はもう永久に縁切りだと言われるだろう。
8. 彼らがどれほど私を傷つけたかを話したら、私はきっと縁を切られてしまうだろう。
9. 私は親の気持ちを傷つけそうなことは何ひとつ言ったりしたりするべきではない。
10. 親の気持ちは自分の気持ちよりも重要だ。
11. 親と話をすることなど意味がない。そんなことをしたところで、ろくなことはないからだ。
12. 親が変わってさえくれれば、私の気分は晴れる。
13. 私は自分が悪い息子(娘)であることについて親に埋め合わせをしなくてはならない。
14. もし彼らがどれほど私を傷つけたか分からせることができたら、彼らも態度を変えるに違いない。
15. 彼らがたとえどんなことをしたにしても、親なんだから敬意を払わなくてはならない。
16. 私は親にコントロールなどされていない。私はいつも親とは闘っている。
自分が患者さんに治療を行う時、古くて頑固な強張りほど、それがほどけていく際に痛みが伴うことがある。
それは変化に伴う痛みなのである。
同様に、毒親に育てられた子が成人して、なお様々な生きづらさに悩まされている時、それを克服する際には残念ながら苦痛が伴うという。
しかし、その苦痛の向こうには解放された世界がある。
今、理由のわからない生きづらさに悩んでおられるとしたら、もしかしたらそれはこれまでの親子関係に遠因があるかもしれない。
ぜひ本書で親子関係を振り返ってみてはいかがだろうか。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
「刺さない鍼」で快適な治療を、
「小野寺式リリース」で癒しを提供します
盛岡・若園町の おのでら鍼灸経絡治療院
URL: http://www.onodera-shinkyu.com/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆