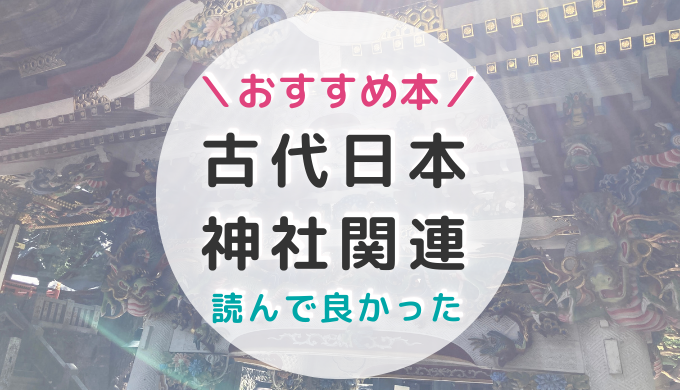![]() はれうさぎ です
はれうさぎ です ![]()
(SUZURI も遊びにきてね ![]() )
)
飛騨 って 古代日本 において とっても重要なポジション だったみたいですね。
でも、よくわからないのですよね~。汗
というわけで、「飛騨王国」について 備忘録的に メモ をまとめました。
いつもありがとうございます
![]()
![]()
![]()
![]()
※ 当ブログは、脳ミソ がポンコツ な私が「自分の為の 備忘録として」を主な目的として書いております。随時、加筆・修正アリ。(作成途中でアップしてしまっているモノもあるかも…?)なんだか いろいろ スミマセン ![]()
![]()
飛騨王国とは?すべてはここから始まった?
成人T細胞白血病(ATL)の原因である新ウイルス の感染者は 九州や四国南部に多い。
→ 特に、沖縄とアイヌに著しく多い(北海道に住む昔からの和人は感染者の割合が極めて低い)
→ 飛騨を中心とする山岳地帯も感染率が極めて低い
南方の感染度の高い民族が暖流に乗って日本の沖縄や九州に漂着し、四国や、中国地方に上陸して次第に本州に入り込んだと推定。
南方の民族より、稲作などの風習だけでなく 遺伝子(ウイルスが感染しやすい→遺伝する)も入ってきた。
・
・
ということは、
古代の飛騨人は、沖縄・アイヌ・ 四国 の民族(南から来た民族)とは別?
(それ以前からいた民族)
・
・
そして、紀国の 名草の民(九州にした その祖たち)も、「飛騨の民」とは 違うということか。
名草の祖は、BC4300前の「鬼界カルデラ大噴火」をきっかけに 南九州から北九州へ移動。
その後、稲作の発展により人口が増えたことで、宮崎・大分付近から和歌山へ移住したとされる。
<参考>
確かに、上記の本「名草戸畔 古代紀国の女王伝説」では
名草民が和歌山に移住してきた際、 既に先住民がいて、先住民を山に追いやった過去 あるとも書かれていた。
もともと「紀国」にいたのは、飛騨関連の人 だったのだろうか?
飛騨周辺にある、「伊太祁曽神社」が和歌山にもたくさんみられる。
「伊太祁曽=いたきそ」というめずらしい名前。
和歌山と飛騨周辺の関係性がずっと気になっているけれど、スッキリ出来ずにいる感じ。
もともと、「日抱(ひだき)」の名前だったのが置き換えられたのか?
元々、同じルーツを持っていたのか?
※「伊太祁曽神社」は「五十猛」なので、後に 置き換えられたパターンっぽい?
「置き換えられた」というと乗っ取りっぽくて言葉が悪いけれど(そうではなくて)
渡来系 と 出雲系が 共存・融合・拡大 していく中で、そうなった感じ?
(とはいえ、飛騨の伝承的には、『飛騨の民(天孫の子孫)は「出雲」と「出雲で生まれたシラギ神崇拝教」により古代被差別部落に落とされた』という話があるので、立場によっては「乗っ取られた」ことになる?)
※シラギ神 = イソタケル(その他)
・
・
あと、「飛騨」と「日高見国」の関係(関係あるのか?どう関係してるのか?)も よくわからず気になっている。
わからないことだらけ~。
<参考>
参考(リンク)
参考(本)
✯
✯
![]() お読みいただきありがとうございました
お読みいただきありがとうございました ![]()
(SUZURI も遊びにきてね ![]() )
)