「危険」「PCにエラーがあります」――IT初心者を狙った警告風の広告に注意 被害者急増中
そういえば、ブログを見ていたりすると上のほうの広告の所などに
出ていることがありますね
記事があったので下記に載せてみました
国民生活センターが、PCに不具合が出たかのように見せかける警告メッセージ風の広告に関して、安易にクリックしたりしないよう注意喚起しています。同センターによると、関連トラブルの相談件数が年々増加しているとのこと。2013年度は、前年度の約4倍となる1505件の相談があったそうです。
みなさんは、Webサイトのバナー広告枠などに「パソコンが脅威にさらされています」「パソコンにエラーがあります」といった警告文のようなメッセージが出たことはありませんか? セキュリティソフトやPCの性能改善をうたうソフトの広告に、こうしたメッセージがよく見られます。
この手の広告は、警告文で消費者を不安にさせて、ソフトを購入させるのが狙い。ネットやPCにある程度詳しいユーザーなら「物騒な広告だな」といぶかしむだけで済むのですが、そうでないユーザーの中には、自分のPCに問題があると勘違いし、誘導されるままソフトを購入してしまうケースがあるようです。
こうしたトラブルの相談件数は、2012年度は400件だったのが、2013年度は1505件と急増しています。ソフトの購入後に不審さに気づいて解約したくなるケースや、「無料」という案内から安易にソフトをダウンロードしてしまったことで、有料ソフトの購入画面が消せなくなるケース、購入後のやり取りが英語のみで容易に解約できないといったケースなど、さまざまな相談が寄せられているそうです。
同センターではこうした相談増加を受け、(1)警告表示が出ても、信頼できる表示か分からない場合はクリックしない、(2)日本語の窓口の有無なども基準にして、複数のソフトを比較検討する、(3)情報処理推進機構(IPA)の情報セキュリティ安心相談窓口のホームページで情報収集する、(4)カード番号の入力前に、商品の料金や有効期間を確認する、(5)トラブルがあった場合は消費生活センターに相談することを推奨しています。
パソコンを操作中に使用中のパソコンの危険などを知らせる警告表示が現れて不安になり、セキュリティーソフトやパソコンの性能を改善するソフトなどをインターネット経由でダウンロードしてしまったが、解約したいという相談が増加している(図1)。
パソコンに突然表示される警告表示等は、本当にそのパソコンの状況を知らせるものとは限らず、消費者を不安にさせてソフトの購入手続きに誘導する広告の可能性もある。
国民生活センターでは、これまでに同様のトラブルも含めて注意喚起をしてきたが、相談件数が増加傾向にある。このため、安易にソフトをダウンロードしないよう、消費者に再び注意を呼びかけるとともに、関係機関等に情報提供する。
PIO-NETにおける相談件数
警告表示をきっかけに、インターネットでソフトをダウンロードした等という相談件数は、年々増加傾向にあり、2012年度は400件、2013年度は1505件である。2012年度の前年同期件数は366件で、2013年度は約4倍に増加している(図1)。
図1 相談件数
()は前年同期の件数
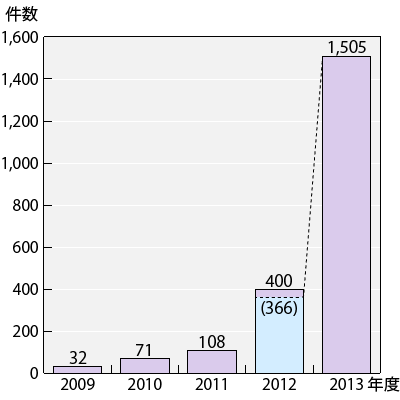
(2014年3月31日までの登録分)
2009年度の相談件数は32件、2010年度は71件、2011年度は108件、2012年度は400件、2013年度は1,505件である。2012年度の2013年度と同時期の相談件数は366件である。
相談事例
- パソコンの画面に出た「危険」という文字に惑わされてソフトを購入した
- ソフトを購入後も、パソコンに同じ警告表示が出て不審だ
- 無料ソフトをダウンロードすると、有料の表示が出た
- 解約の電話をして初めて、海外から購入したと気付いた
- 大手のパソコンの会社のようなマークが表示されたので信用した。自動更新した覚えがないのに請求を受けた
消費者へのアドバイス
- パソコン画面に突然に警告表示が出ても、信頼できる表示かどうかわからない場合には、クリックしないこと
- 日本語で問い合わせができる窓口の有無も購入の1つの基準として、複数のソフトを比較検討して購入すること
- パソコンの危険な状態を回避するために、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の情報セキュリティ安心相談窓口のホームページで情報収集すること
- クレジットカード番号の入力前に、料金や有効期間(契約更新の有無)等を確認する
- 消費生活センターに相談すること