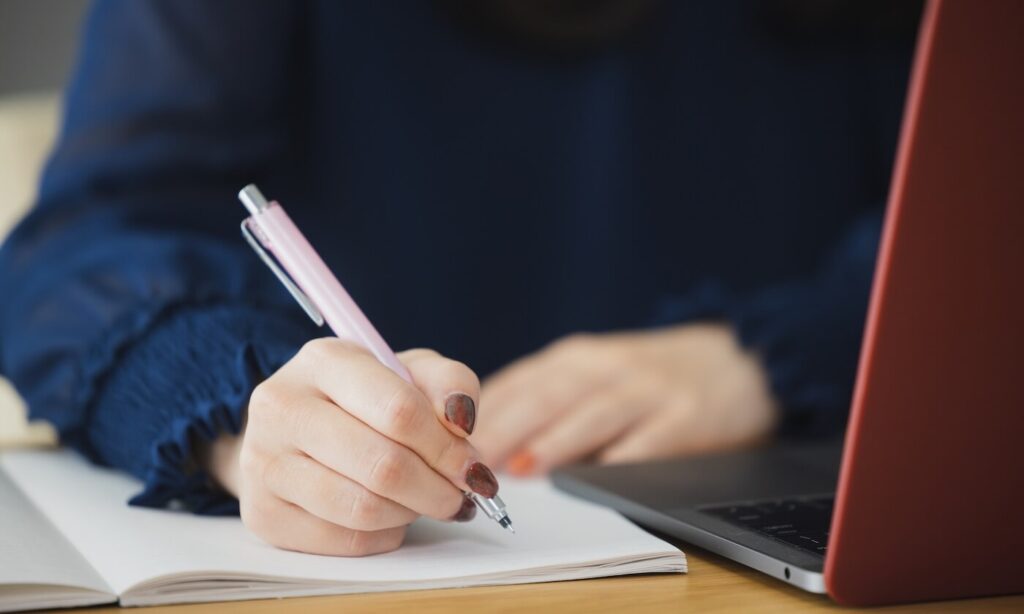(1)ケアマネの専門性とは?
こういう話が出てくるたびに「ケアマネの専門性」って何だろう?と振り返る必要があると思う。つまりよく「ケアマネの質」なんていうキラーワードがあるのと同じで、結局この国の高齢者福祉はどこに向かっているのだろう?という事は明確にしなくてはならないと、何のためのケアマネなのか、意味が無くなってしまう。
そんな中で様々なホームページを見ると下記の論文がまとまっていると思うので掲載する。
https://www.npojmi.com/dl/DL100~/185.pdf
簡単にまとめれば
①要介護者などからの相談に応じ
②要介護者などがその心身の状況などに応じた適切な在宅サービスを利用できるよう
③市町村、サービス提供事業者などとの連携調整を行う
という事である。
つまり我々ケアマネが普段している業務内容そのものである。
だから普通に働いている人は「今更」な話だし、知識を得たいというならそれはその通りだろうと思う。
しかし専門性というからにはそこに評価があっても不思議ではない。そしてその評価によって有名になったり、依頼が増えるという事も他の業界では普通なことだと思う。
とはいえケアマネはそんな事はない。
タダでさえ人不足という面があるにしろ、「こういう問題があるからこのケアマネに担当してもらいたい」というのは無いとは言えないが、絶対ではない。
例えば私だが、ケアマネを始めたころ、地域に在宅緩和の訪問診療があったためか、末期ガンの利用者の受け入れが多かった。そんな状況だったから、私の地域では末期ガンの専門性が高い、実績もあると思われたらしい。
ところが私は老人ホームの相談業務→訪問介護の管理者などを経由してケアマネになったので、医療的な専門性があるわけでは無い。
それでもそんな風に評価されるのは不思議なものだが、おそらく研修期間が求めている専門性と、実際の現場レベルでの専門性というのは似て非なるものかもしれない。
(2)実際に求められる専門職とは
この論文でケアマネに必要な資質として「要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的な知識・技術を 有する者」と定義している。
それで「自立」支援としては
①自己決定の尊重
②残存能力の活用
③生活の継続性
が挙げられており。これも反論の余地はないと思う。
更に得るべき知識・視点としては「①健康状態②ADL③IADL④認知障害⑤コミュニケーション⑥社会とのかかわり⑦排尿・排便⑧褥瘡と皮膚の問題⑨口腔衛生⑩食事摂取⑪問題行動⑫介護力⑬居住環境⑭特別な状況」が挙げられている。
これは認定調査で聞く事もあれば、アセスメントとして聞く場合もある。
まあ、要するにこういうことが出来ているかどうか、不足して補える環境があるかどうかなどをチェックするという事である。
これも日常的に行っていることだから、これを「専門性」と言われてもピンとこない人も多いだろうと思う。
(3)利用者や家族が求めるもの
勿論、知識が豊富なのは利用者や家族と話す時に安心感を与える絶対なものである。
しかし、だ。
今はネットで色々調べられるから、病気や薬、介護に関してはどんなサービスがあるかくらいは簡単に調べられる。また近所の人があそこのデイサービスに行っていた、なんていう情報は我々ケアマネよりも詳しい人も多い。
おそらくケアマネが何たるかを調べた人もいるだろう。
そういう時代で、利用者や家族がケアマネに求めるものは何かと言えば「迅速な対応」であり、「された相談に対する明確な回答」である。中でも迅速な対応は一番利用者に安心感を与えるのではないだろうか。
私はモニタリングの時に利用者からの相談でサービス事業所に連絡が必要な時は、その場で電話あすることもしばしばだ。それは私自身が忘れないという事もあるが、利用者の目の前で話をすることによって、素早く対応が出来るというメリットがある。
いくら知識があってもなかなか動いてくれないとか、書類が届かないというのであれば、利用者や家族、それにサービス事業所としてもやりにくいだろう。
そう考えると、知識の量というか幅はあった方が良いが、要はそれを使う人の使い方という事なのだ。
(4)結局は「更新研修」と同じ
最近、ケアマネの更新研修廃止の要望が高まっている。これを受けないとケアマネの仕事が出来なくなるという脅迫のようなものだが、内容のずさんさは言うまでもなく、時間も費用も取られ、ケアマネとしては研修の必要性は認めつつも、研修のあり方について疑問を呈されている。
そして何かよく分からない「ケアマネの質」の問題を出され、結局のところ、この研修で質が上がったという話は聞いたことが無い。つまり「質」というぼんやりとした、更に定義づけることも無いキラーワードを使う事で研修は継続し、天下りの温床になっているのだ。
勿論、知識を高めるのは必要だが、それが「質を高める」かは疑問であろう。だってそれが利用者や家族との信頼関係を深めるものになるかは疑問だからだ。
要は天下り団体が更新研修をやっておいしい汁を吸っているから、自分たちもそれにあやかろうとしているのではないかと思ってしまうのだ。
しかしこれは強制力は無いから、会員が我慢して受講するしかない。
こんなことに時間を費やすなら、どうやって信頼関係を作り、スムーズに仕事をするかという事を考えた方が良いと思うのだが。