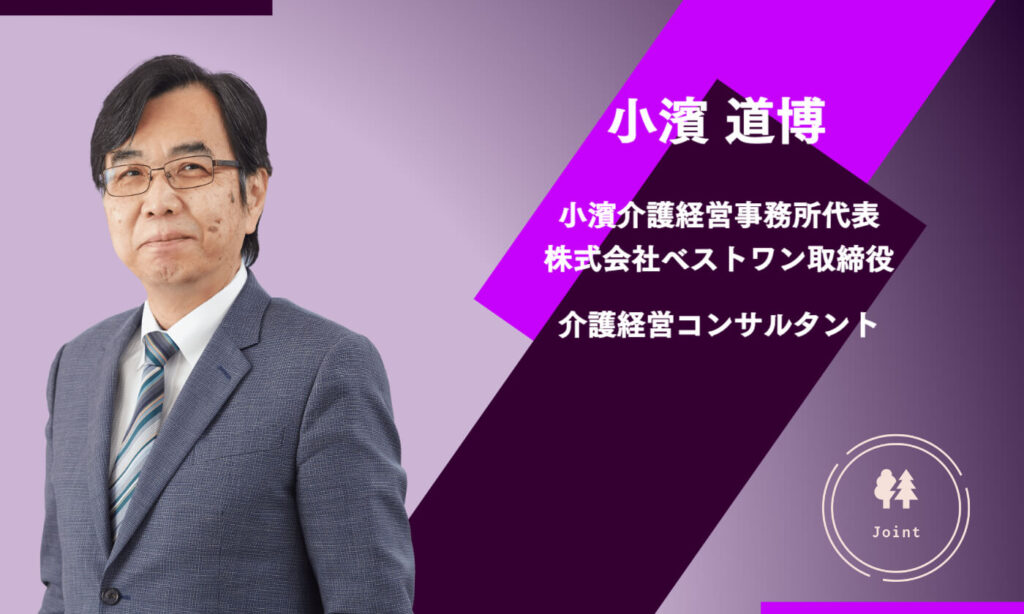(1)訪問介護事業者は今後も続ける気があるか?
訪問介護事業所の倒産、廃止件数が去年は過去最多。厚生労働省、財務省も訪問介護の報酬を挙げようという動きは今のところ見られない。むしろ報酬を上げることには否定的で、選ばれる事業所を目指すべきと、完全に人のせいにしている。
まずこれが国の介護に対する基本的な考え方だという事で把握しておくべきものである。そしてそれを踏まえて何をすべきかという事を考えるのが必要だ。
まず、今の訪問介護事業者が今後も事業を継続する意思がある、もしくは安定経営できる能力があるかという事業者側の都合は大きい。もしそれで地域のサービス量が確保できないのであれば、どんな形でもやらなければならない。
(2)外国人が日本で働くメリット
今、日本人が外国人によって迷惑を被っている事例が多くなっている。そこでは不法移民であったり法の抜け道で日本で事業をしたりという事があるようで、そもそも自国で医療や介護を受けることが難しい人でも日本であれば受けられるという事で悪用されるという事が社会問題になっている。
中には日本で犯罪を犯すものもいる、そして驚くことに不起訴になる事もあるという事だ。
そういう外国人はお引き取り願いたい。それは当然である。強制退去でも国にはそういう処置を強く求めたい。
一方、日本で働きたいという人が多いという話も聞く。そして記事のようなインドネシアの人が介護で日本に行きたいので、どこか事業所を紹介して欲しいという話は私もプライベートで相談を受けたことがある。
私のような一介のケアマネにもそういう情報が来るのだから、これは事実なんだろうと思う。
そして日本で働くことに喜びを感じ、迷惑をかけずに日本に貢献できる人は来てもらいたい。日本人はそういう人なら歓迎するだろう。
そして外国人の方も、自国よりも高い給料を貰えて家族を養えるならメリットもあろうと思う。
そもそも日本人にとって介護の仕事は選ばれる仕事、やりたい仕事なのかという根本問題を探る努力は重要だ。
介護保険スタート時に隆盛を誇った介護の専門学校は閉鎖したところも多い。データによれば10年間で110校が閉鎖した。
(3)台湾に学ぶ
平成初期の不況時代、完全失業率が4%を超え、介護職への求職者が爆増した時代があった。高齢者のこれからの生き方、措置制度の不備から応能負担から受益負担になり、サービスという概念を取り入れた「新しい福祉のあり方、産業」への期待に群がった時代は今はもう昔の話だ。
つまり日本人にとって、介護は既に選ばれない、避けられている仕事なのだ。
ではだれもやりたがらない仕事は誰がどうするのかという事である。
先日旅行に行った台湾は「メイド文化」である。お寺に行くと車いすに乗った高齢者がいてヘルパーが介助している。
このヘルパー、メイドたちはフィリピンやインドネシアの外国人だそうだ。台湾の人が介護をやりたがらないからと割り切ったかは分からないが、台湾ではそういう外国人を受け入れる制度も整え、定着している。
記事には大手しかメリットが無いというが、スケールメリットを出し、事務作業なども効率化を図ることが安定経営と考える国の方針とも合致している。そもそも零細の訪問介護は生き残れないと割り切り、撤退することを考える時期なのだ。
中小零細企業の訪問介護は、こうした割り切りも必要なのかもしれない。