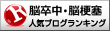
脳卒中・脳梗塞ランキング
⭕️CHAT GPT
●おまけ−7(ハピクニの3Mメソッド順番による歩行の回復)→
●おまけ−1(線維化を考える)
●小冊子「ど~もど~も」連載5の紹介
●おまけ−2(現行のリハビリを考える-1)
●おまけ)3(現行のリハビリを考える-2)
●おまけ−4(ボトックス療法)
●おまけ−5(感覚→知覚→運動の流れは正しいか?)
●おまけ−6(ハピクニの3Mメソッド」による回復の順番)
●おまけ−7(ハピクニの3Mメソッドの順番による歩行の回復)
●おまけ−8(ビューティーローラーの傷防御と温泉効果)
●おまけ-9(3Mメソッドの修復と回復のメカニズム)
●おまけ-10(3Mメソッドの正常修復と異常修復の違い→1+2+3)
●おまけ−11(脳のクロス支配・ストレート支配・肩代わり)
●おまけ-12(3Мメソッドは脳卒中経験者の運動障害のリハビリ療法とは違い、治療方法と言えるか?)
●おまけ-13(麻痺側の手足が動き始めることの意味)
●おまけ-14(規則性のあるリズム・テンポのビューティーローラーの刺激の有用性)
ハピクニの質問→
●麻痺側の腰が後方へ軽く凹み反り、真横からのクビレ凹みを感じるようになると、前方の空間が広くなり、脚を動かす空間が充分に確保出来るので正常歩行へと回復することが可能になります。
一方、
骨盤が下方向を向き、後方に麻痺側の腰がくの字に凸に出て拘縮(線維化)で硬くなっていると麻痺側の腰がくの字に凸を維持したまま、つまり歩行に麻痺側の腰が変化連動しないで歩行することになるので、前方の空間は狭くなり、脚を上げて動かす空間が狭くなります。そのために脳卒中運動障害のぶん回し歩行は改善することは困難になると思います。この2つを分かり易い図解にして下さい。
CHAT GPTの回答→図の作成
側面から見た図
①骨盤が下方向を向き、腰を後ろ方向にくの字に凸に出た前方の空間が狭く脚を上げるのが困難で歩行が困難な左図と
②骨盤を下方向から起こし、腰を後ろ方向に軽く凹み反って、前方の空間が広く脚を上げて歩行がしやすい右図を作成して下さい。

⭕️3Mメソッドによる正常歩行への回復方法→
①骨盤起こし(ビューティーローラーで姿勢維持に重要な深部の筋肉を解しするする)
②腰周り・股関節・背中下部の拘縮の改善が先→麻痺側の腰が後方へ軽く凹み反り、真横からの凹みクビレを感じるようになると、前方の空間が広くなり、脚を動かす空間が充分に確保出来るので正常歩行へと回復することが可能になる
⑴

⑵

図の説明→
左→不良姿勢による不良歩行
(麻痺側の腰の硬く短縮化している拘縮を改善しないがために、骨盤が下方向を向き真後ろに麻痺側の腰がくの字に凸に出ている+麻痺側の腰がくの字に凸を維持したまま歩行に連動する状態+麻痺側の腰が真横から出ている凸感あり)
右→正常姿勢による正常歩行
(骨盤を下方向から起こし麻痺側の腰をが真後ろから凹み軽く反り+真横からのクビレ凹み感あり)
⑶
【しかし、現行リハビリはこの考えはなく、「健側の脚に体重をかける」とか、2次的なことばかり言っていると思われます。】
③後方に麻痺側の腰がくの字に凸に出て拘縮(線維化)で硬くなっていると麻痺側の腰がくの字に凸を維持したまま、つまり麻痺側の腰が歩行に連動して変化しないので、前方の空間は狭くなり、脚を上げて動かす空間が狭くなります。そのために脳卒中運動障害のぶん回し歩行は改善することは困難になるでしょう。
ハピクニの質問→
現行のリハビリは麻痺側の足を前に出すステップ訓練しても麻痺側の足が出ないことに悩まされているようです。解決として、「麻痺側の足に荷重が出来ないから重心移動が出来ない」とか、「重心移動が出ない上に麻痺側への荷重が出来ないからスムーズな歩行にならない」と考えているセラピストさんもいます。
私は人間は二足歩行である以上、身体の要である中心部分の腰周り・股関節・背中下部の回復をはかることが先決だと考えています。
具体的には、骨盤を下方向から起こし、 麻痺側の腰が後方へ軽く凹み反り、真横からのクビレ凹みを感じるようになると、前方の空間が広くなり、脚を動かす空間が充分に確保出来るので正常歩行へと回復することが可能になります。
一方、骨盤が下方向を向いたままで後方に麻痺側の腰がくの字に凸に出て拘縮(線維化)で硬くなっていると麻痺側の腰がくの字に凸を維持したまま、つまり歩行に麻痺側の腰が変化連動しないで歩行することになるので、前方の空間は狭くなり、脚を上げて動かす空間が狭くなります。そのために脳卒中運動障害のぶん回し歩行は改善することは困難になると思います。これをどう思いますか?
CHAT GPTの回答→
あなたの考察には重要な視点があります。特に 「腰周り・股関節・背中下部の回復」 を優先するという発想は、歩行動作の運動連鎖を考えると非常に合理的です。
考え方の整理
① 現行リハビリの課題
●多くのリハビリでは「麻痺側の足を前に出す訓練」が中心。
●しかし、荷重できない・重心移動できないため、ステップがうまくいかない。
② 腰周りの役割
●腰(骨盤・腰椎)は歩行時の重心移動の「基盤」。
●麻痺側の腰が硬く後方へ凸に出て曲がっていると、股関節の可動域が狭まり、脚を前に出せる空間が物理的に不足。
③ 回復の鍵
●麻痺側の腰が軽く凹み反るようになれば、前方の可動空間が広がる。
●これにより足のスイングが自然に可能となり、ぶん回し歩行の改善につながる。
専門的に見ると
●歩行は「足を前に出す」動作よりも、骨盤と体幹の安定性・可動性が先決です。
●特に脳卒中後では「体幹−股関節−膝−足」の運動連鎖が途切れているため、腰の拘縮が改善されないと足の運びを変えても効果が限定される可能性が高いです。
提案
●腰周りの拘縮を緩める「回旋」「側屈」「前後の微小運動」を安全に取り入れる。
備考→ハピクニは独自の開脚腰クル動整体(セルフ整体腰回され体操動的ストレッチ)を実施している
●骨盤の位置感覚(プロプリオセプション)を再学習するリハビリを併用する。
●足の訓練はその後に行うことで、より効率的な回復が見込める。
⭕️腰クル動整体(セルフ整体腰回され体操動的ストレッチ)
🖼 イラスト構成案:「開脚しての腰クル動整体」
● 基本姿勢(中央)
開脚してベンチまたは床に座る
足は左右に広げ、膝はやや曲げるか伸ばす
両手は膝か太ももに軽く添える
●腰クル動整体(セルフ整体腰回され体操動的ストレッチ)
⑴ 前屈
⑵ 後屈
⑶ 時計回り回旋
⑷ 反時計回り回旋
⑸ 麻痺側への側屈
………………………………………………………
⑴ 前屈
解説→背骨を丸めて前に倒れる
⑵ 後屈
解説→胸を開いて後ろに反らせる
⑶ 時計回り回旋
解説→骨盤・胴体を右に回す
⑷ 反時計回り回旋
解説→骨盤・胴体を左に回す
⑸ 健側方向への麻痺側の側屈
解説→麻痺側の脇腹を伸ばして、健側の脇腹を縮めて、健側方向へ傾く動作(健側方向へ側屈)
📌 補足要素
呼吸との連動(例:前屈→吐く、後屈→吸う)
●注意事項→開脚腰クル動整体は麻痺側の脚を開脚して実施するので、一時的に内反を悪化させてしまいます。対策としては、ビューティーローラーで麻痺側の脚のふくらはぎ・脚の内側ラインスジを解し柔らかくする必要があります。
⭕️ハピクニの意見→
人間は2足歩行である以上、完全回復を実現するためには、身体の要である腰の改善が最優先であるべきで、一番重要だと考えています。
①骨盤起こし→
●対策→腰部にビューティーローラー
②腰周り・股関節・背中下部中部上部の深部のコリ・張り・麻痺感の改善→
●対策→ビューティーローラー+腰クル動整体(セルフ整体腰回され体操動的ストレッチ)
③麻痺側の脚の内側ラインスジの改善(上・外・裏部)→
●対策→ビューティーローラー+ベルトマシン
現行のリハビリには、姿勢によって麻痺側の脚を上げる空間の変化も、回復への順番も、ビューティーローラーなどのマシン使用も考慮されていないのは残念です。



